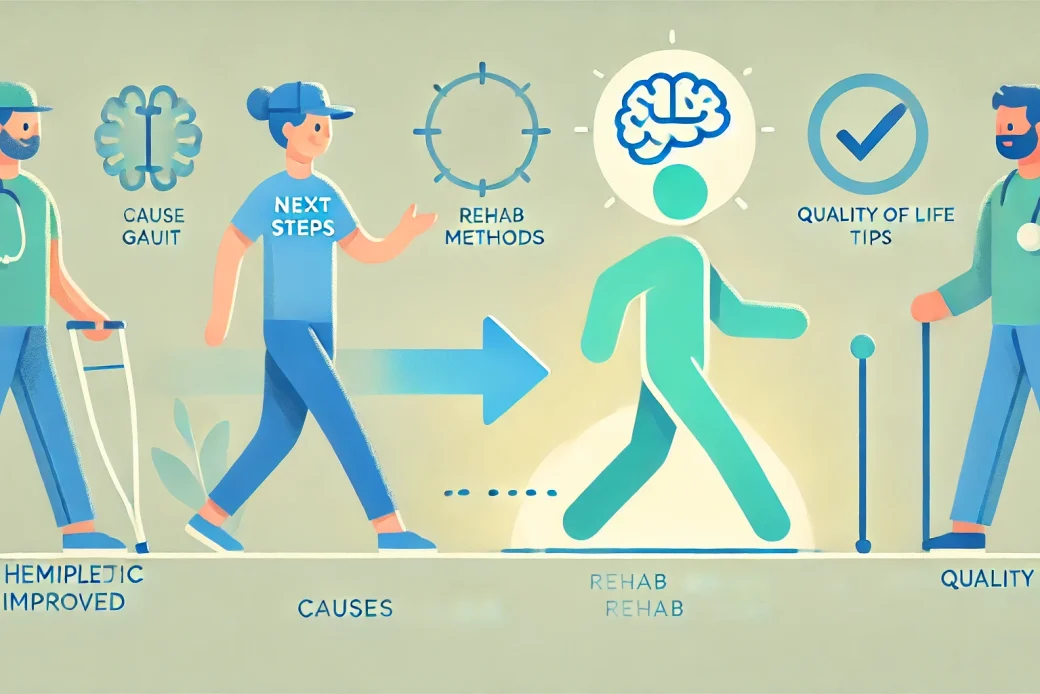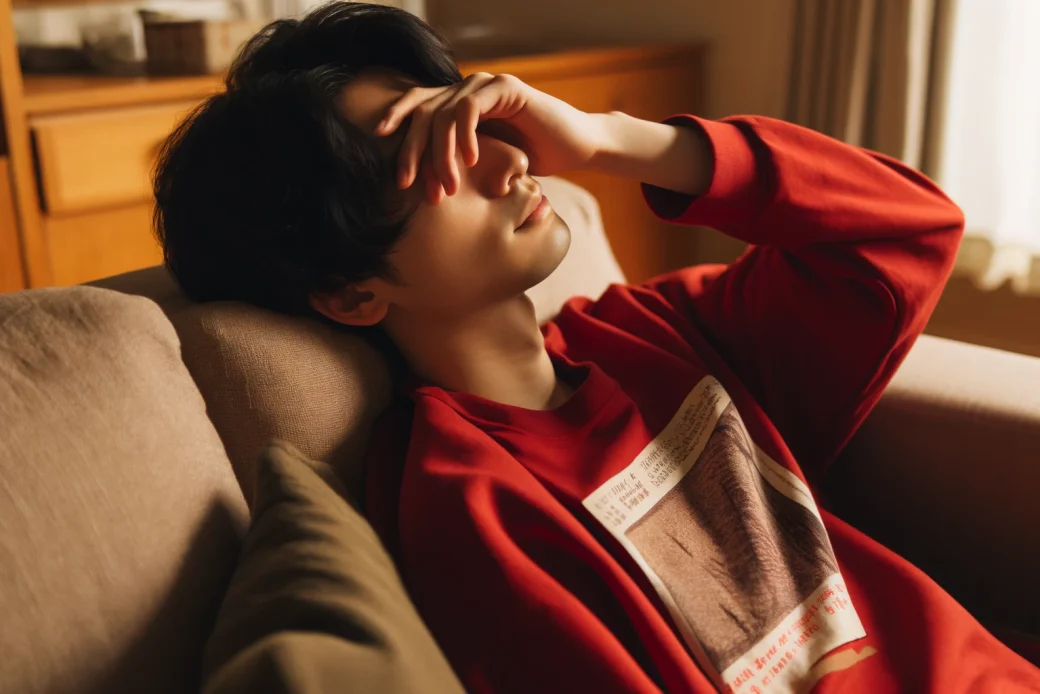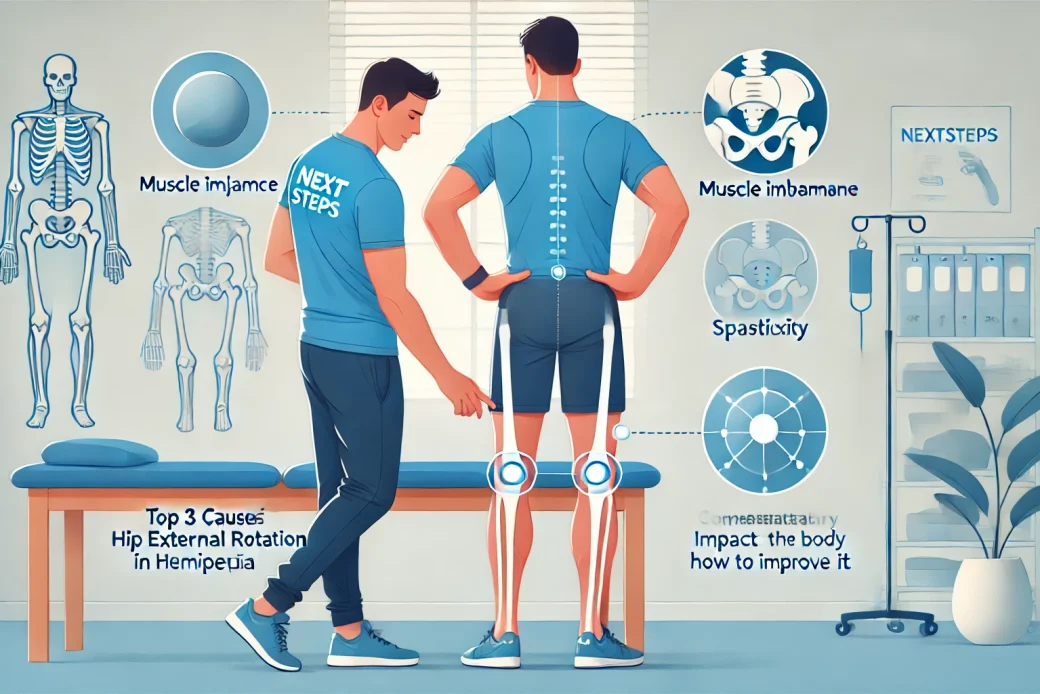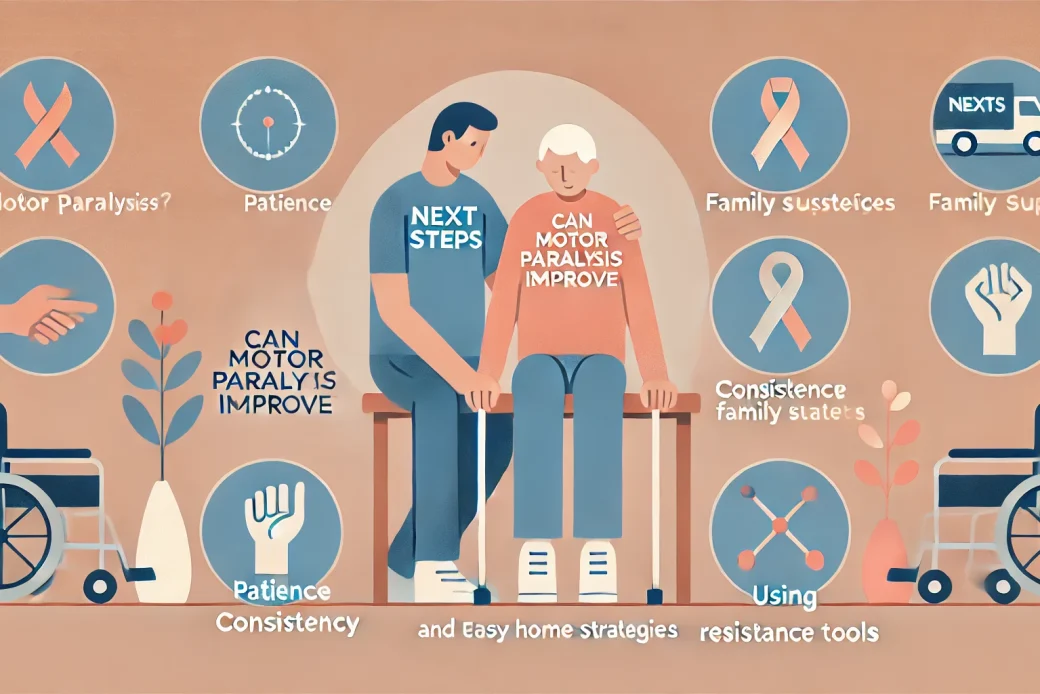脳出血家族ができることは?時期に応じたサポート方法と介護者の負担を防ぐ具体例
2025.10.24
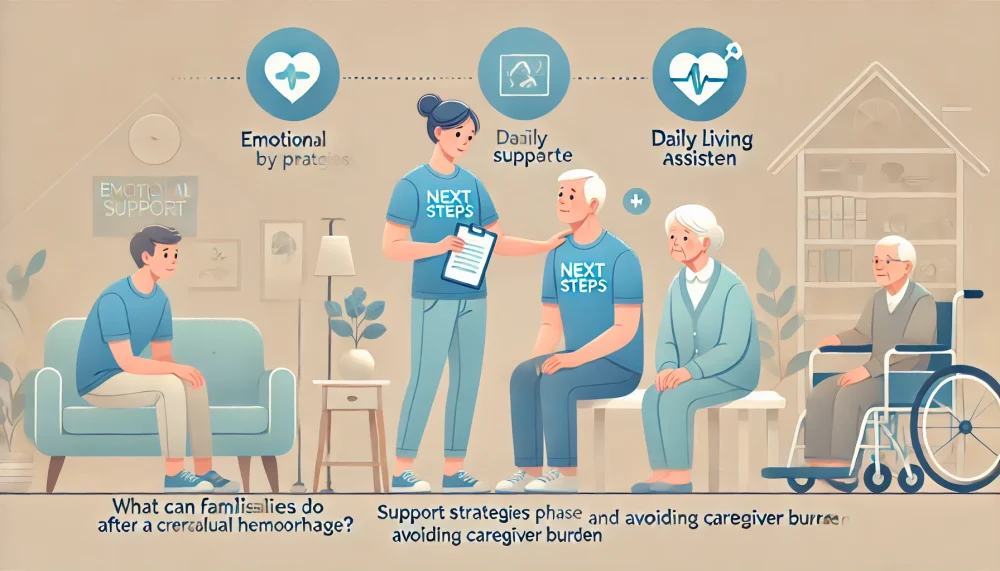
家族に脳出血が起こると、「何をしたら良いの?」「どのように支えたら支えたら良いの?」など、多くの方が不安になるでしょう。
脳出血後はさまざまな後遺症を抱える可能性があり、家族によるサポートが大切です。脳出血において家族ができることを具体的に知ると、患者さんに対して適切なサポートができるようになるでしょう。
安心して生活を送るためにも、時期に応じたサポート方法を理解しておきましょう。脳出血後の介護は家族への負担が大きくなるため、介護者の負担を減らす方法や制度に関する理解も大切です。
目次
【入院中】脳出血家族ができること|精神のケアでリハビリに集中

脳出血において家族ができることは、入院中にもたくさんあります。入院期間中は、患者さんの精神面のケアや自主トレの支援、介助方法の勉強が大切です。適切なケアを行うために、それぞれの内容やポイントをおさえておきましょう。
メンタルケアでモチベーションを保つ
脳出血を発症するとさまざまな後遺症に悩まされるため、入院中はリハビリが必要不可欠です。リハビリの効果は患者さんのモチベーションによって左右されるため、家族のメンタルケアが欠かせません。
メンタルが不安定な状態では、毎日リハビリを行っても思うような効果が得られない可能性があります。入院期間中のリハビリ効果を最大限発揮するためにも、精神面を支える意識を持つことが大切です。
自主トレの支援と見守り
脳出血で入院した場合、1日最大3回のリハビリを行うのが一般的です。体が動くのであれば自由に過ごせる時間も多いため、訓練時間以外の過ごし方を工夫するとよいでしょう。その際は、必ずリハビリ担当者から許可を得る必要があります。
<おすすめの自主トレ方法>
- 廊下を歩く練習をする
- 病室で起立練習を行う
- 認知症予防に机上課題を行う
家族ができることは、自主トレ内容の確認や安全面への配慮です。適度な距離感で見守り、過度に干渉しすぎないことを意識してサポートしましょう。
参考:J-stage「回復期リハビリテーション病棟における脳卒中患者に対する自主練習の考え方」
専門家に介助方法を学ぶ
脳出血の重症度が高く後遺症が残る場合は、入院期間中に適切な介助方法を学んでおきましょう。特に、歩行や階段などに介助が必要な場合、適切な方法で補助しなければ動きを邪魔してしまう恐れがあります。
退院後の日常生活での転倒やケガを防ぎ、安心して生活を送るためにも、家族が適切な介助方法を知っておくことが大切です。
【退院後】脳出血家族ができること|日常生活を考えて環境を整える

脳出血において家族ができることは、退院後にもさまざまあります。例えば、脳出血後は運動機能障害などの後遺症を抱える可能性があるため、住宅改修や介護サービスの手配を行います。
他にも、再発予防の知識を身に着け、生活習慣改善をサポートするのも家族ができることの一つです。それぞれにあったサポートをできるように、どのような支援方法があるのかを理解しておきましょう。
必要に応じて住宅改修を行う
脳出血を発症すると運動機能が障害されるため、転倒によるケガの危険性が高まります。退院後に安心して生活するためにも、事前に住宅改修を行うのもおすすめです。
- 廊下やトイレ、浴室に手すりを設置
- 段差を解消する
- 寝室を1階に移動する(ベッドに変更する)
住宅改修の必要度は、脳出血後の後遺症の程度によって異なります。入院期間中にリハビリ担当者による家屋調査が実施されることもあるため、専門家のアドバイスも受けながら、安全な生活が送れるように準備しておきましょう。
介護保険サービスの手配
脳出血の後遺症をかかえたままの自宅生活は、さまざまな場面で支障をきたす可能性があります。そのため、脳出血の治療が完了したら、介護保険サービスを手配しておくと安心です。
<日常生活に影響が出る場面の例>
- 家にいる時間が長く認知症リスク増大
- 運動機会が少なく、体力が低下する
- 家族ではお風呂の介助が大変
介護保険を利用すると、デイサービスや訪問リハビリ、訪問介護などのさまざまなサービスを受けられます。家族だけではケアできない部分を介護の専門家に任せられるため、家族の介護負担軽減にもつながるでしょう。
再発予防の知識を身に着ける
脳出血は再発率が高い病気のため、食事や運動などの生活習慣の改善が必要です。しかし、病気に対する理解が不十分だと、十分なサポートができません。脳出血を再発すると重篤な後遺症や死に至る危険もあるため、患者さんと家族が協力して、生活習慣を改善する努力をしましょう。
- 一汁三菜を意識したバランスの良い食事
- 飲酒量を減らす
- 減塩をする
- ウォーキングやラジオ体操などの運動習慣
家族全体が健康を意識した習慣を取り入れると、改善した生活が長続きしやすくなります。
脳出血家族ができることは?介護者の負担も考慮した生活が大切

脳出血において家族ができることは、退院後の介護だけでなく、介護者の負担軽減も見逃してはいけません。介護負担による怪我や心の病気を抱える方も多いため、家族の負担を減らす方法についても理解を深めましょう。
無理な介助での怪我を防ぐ
脳出血後は、「立つ」「歩く」などの日常生活動作に介助が必要になるケースも少なくありません。男性の介助を女性が行うと、体格差や力の強さなどの影響から怪我の危険が高まります。
無理な介助を続けて、腰や膝などを痛める方も多いため、適切な介助方法や介護サービスの利用を検討しましょう。
家族の心理面もサポートする体制
先の見えない介護の日々は、家族の精神的な負担が懸念されます。家族ができることを探すのも大切ですが、介護者自身のストレスを抱え込まない工夫も大切です。
介護サービスを活用しながら、家族の肉体的、精神的負担を最小限にしましょう。必要に応じて、かかりつけ医やケアマネージャーに相談するのもおすすめです。介護者は、悩みやストレスを抱え込まないようにすることを心がけましょう。
レスパイト入院やショートステイ
脳出血後の患者を介護する家族をサポートする制度として、「レスパイト入院」や「ショートステイ」があるため、必要に応じて利用を検討しましょう。
- レスパイト入院
…介護する家族の休養を目的とした短期入院。病院での滞在のため、急変時も安心できる。
- ショートステイ
…介護施設に短期間滞在する仕組み。医療的ケアが必要でない人が対象。
介護疲れを感じたときは、上述した制度を利用しながら、家族の精神面をケアするのが大切です。どちらを利用するかは患者の状態によって異なるため、ケアマネージャーに相談すると良いでしょう。
まとめ|【脳出血】家族ができることを理解して体と心を支えよう
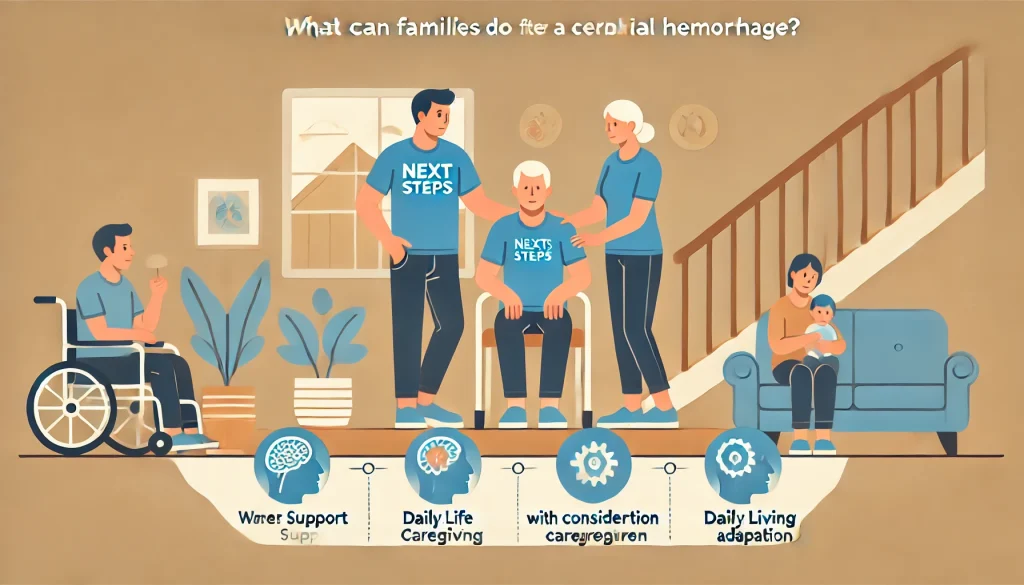
脳出血を発症した方に対して、家族ができるサポートは、入院中から退院後まで幅広く存在します。それぞれの時期に応じた支え方を知っておくことが、患者さんの回復を助け、家族自身の心の負担を減らすためにも大切です。
入院期間中は、本人がリハビリに前向きに取り組めるように、精神的なサポートを行うことが重要です。たとえば、「一緒に頑張ろう」という声かけや、リハビリの成果を一緒に喜ぶなど、モチベーションを維持できる関わり方が効果的です。また、医療スタッフの指導のもとで安全にできる自主トレーニングを手伝うことも、回復を後押しします。
退院後は、後遺症を抱えながらも安全に生活できる環境づくりが必要です。たとえば、転倒を防ぐために手すりを設置する、段差をなくす、滑りにくい床材に変えるなど、住宅環境を整える工夫をしましょう。さらに、介護サービスや訪問リハビリの利用も、家族の負担を軽減しながら患者さんの生活を支える有効な手段です。
ただし、脳出血後の介護は、身体的にも精神的にも家族に大きな負担を与えることがあります。 不安やストレスを一人で抱え込まないように、介護者向けの支援制度や相談サービスを積極的に活用することが大切です。
家族だけで頑張りすぎず、医療・介護の専門家と協力しながらサポート体制を整えることで、患者さんと介護者の双方が安心して生活できる環境をつくることができます。