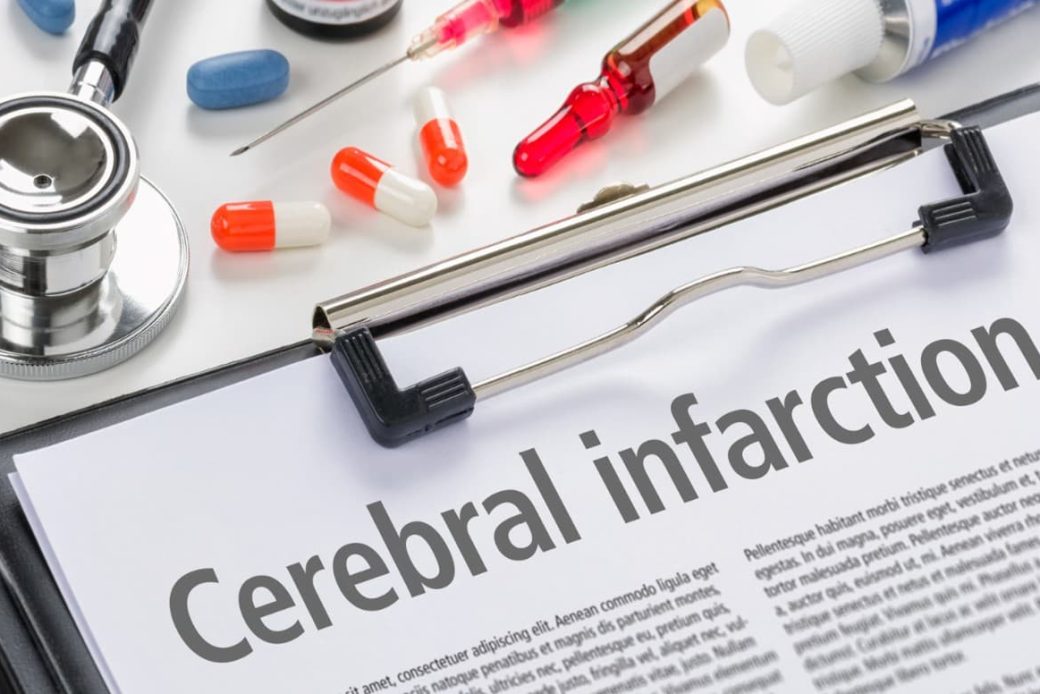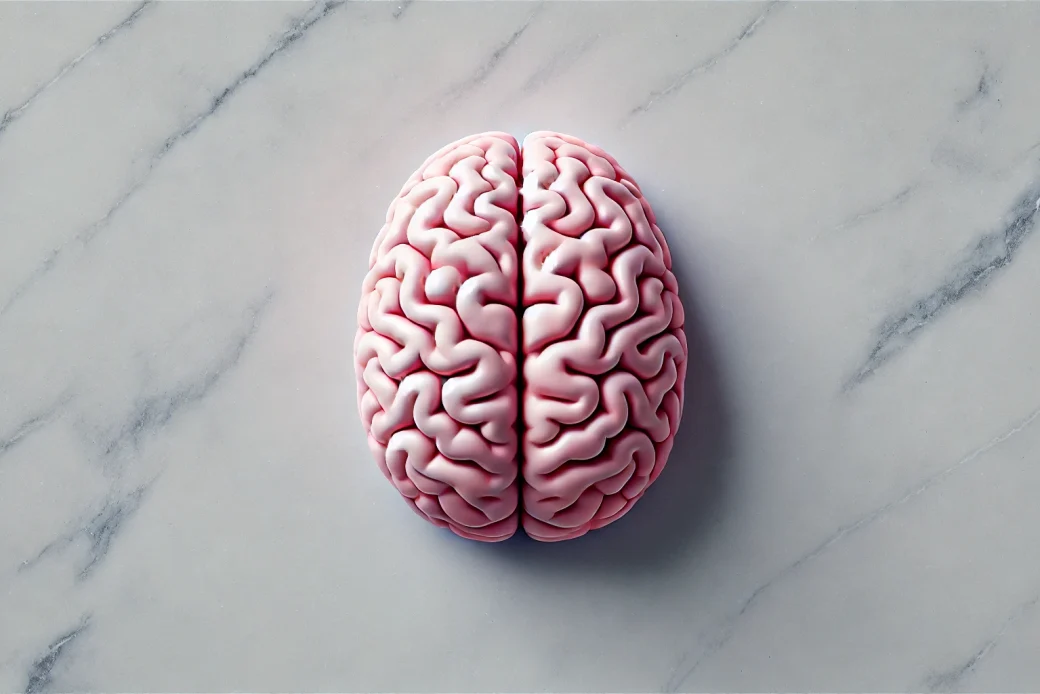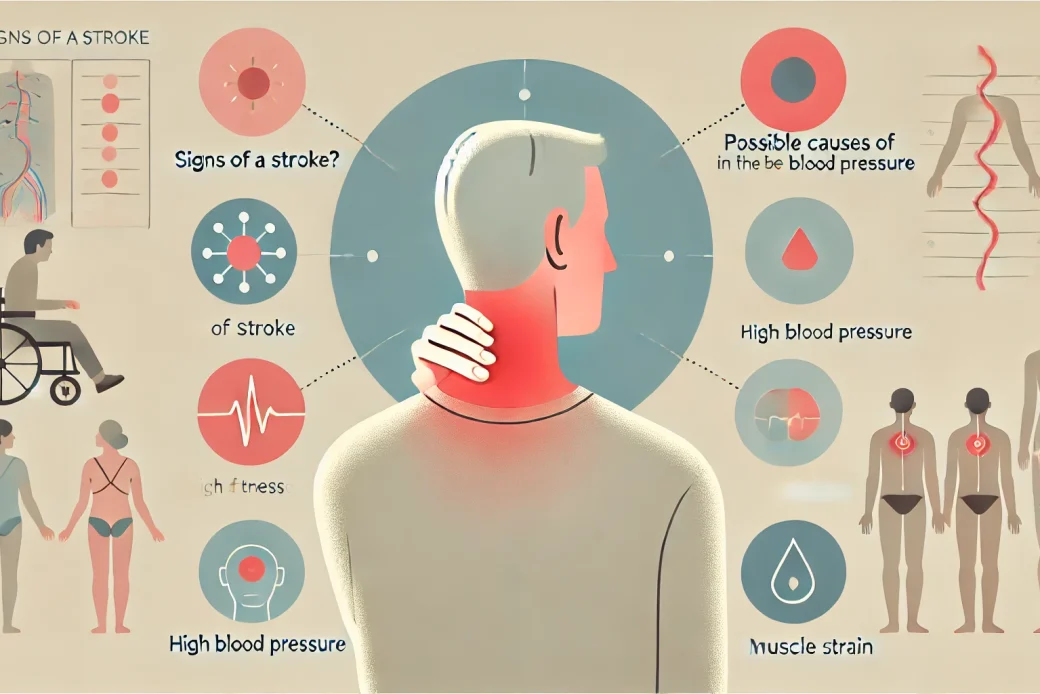【脳出血から仕事復帰】復職までの期間やリハビリの内容・注意点について解説
2025.10.20

「脳出血から仕事復帰できるのか心配」「復帰までにどのくらい期間がかかるかな?」など、脳出血後の社会復帰に不安を抱えている方は少なくありません。
脳出血は、10万人あたり年間約50〜60人が発症するといわれる身近な病気で、仕事盛りの若い世代も発症する可能性があります。脳出血後に仕事復帰できる確率は、約50%といわれていますが、後遺症の程度や種類によって復職率が変化することを理解しておきましょう。
脳出血後に安心して仕事復帰できるよう、具体的なリハビリ方法や生活の注意点を解説します。復職には、上司や職場と連携しながら事前に決めるべき内容もあるため、理解を深めることが大切です。
目次
脳出血から仕事復帰は可能!?目安の期間や予後を左右する因子

脳出血後の仕事復帰は、後遺症の程度や復帰する仕事内容によって期間が異なるため、注意が必要です。仕事復帰は、身体機能だけでなく、社会的背景などさまざまな要因が関係してきます。脳出血後の仕事復帰に考慮するべき点を理解しましょう。
脳出血から仕事復帰できる人の割合
脳出血を含む脳卒中から仕事復帰できる人の割合は、約50%程度といわれています。しかし、脳出血にも複数のタイプがあるため、復職率は異なるというデータがあります。
例えば、後遺症の程度が重い場合は、回復に時間がかかったり復職率が低くなったりする可能性があるため注意しましょう。
復帰の可否を左右する要因とは
脳出血後の仕事復帰は、医学的な要因以外にもさまざまな要因が影響しています。復職に影響を与える主な因子は以下の3つです。
- 医学的因子:後遺症の程度や発症年齢、合併症など
- 労働環境因子:職種や仕事内容、勤務体制、上司や周囲の理解など
- 社会的因子:家族や周りのサポート、経済的背景など
仕事復帰は、体の状態だけでなく「後遺症を抱えたままでも働ける職種か?」「周囲のサポートを受けられる環境か?」など、社会的因子も考慮する必要があるのです。
仕事復帰までの一般的な期間の目安
脳出血から仕事復帰までの期間は、出血の程度や後遺症の重症度、仕事内容によって異なります。例えば、軽傷例で後遺症がほとんど見られない場合なら、3〜6ヶ月程度で職場復帰が可能になります。
しかし、運動麻痺や言語障害、高次脳機能障害が見られる中等度から重症例になると、6ヶ月〜1年以上かかるケースも珍しくありません。仕事復帰までの期間は一概にいえませんが、「個人差が大きく不確実」と覚えておきましょう。
脳出血後の仕事復帰に向けたリハビリは?後遺症別に最適な方法を

脳出血から仕事復帰を目指すには、後遺症に合わせた適切なリハビリを行う必要があります。脳にダメージを負うと、身体機能や認知面、言語障害などにさまざまな影響を及ぼすため注意が必要です。ここでは、それぞれの具体的なリハビリ方法を解説します。
身体機能改善のリハビリ
脳出血から仕事復帰を目指す場合、筋力低下やバランス機能などの身体機能を改善するリハビリが大切です。脳出血では、半身麻痺の影響で歩行や着替えなどの日常生活動作が不安定になるため、状態にあわせた専門的なリハビリを行いましょう。
社会復帰を考えると、通勤に必要な体力や階段昇降なども欠かせません。そのため、身体機能改善のリハビリでは、職種や生活を考慮したリハビリを行うのが大切です。
職業訓練や認知機能の向上
脳出血では記憶や注意力、判断力が低下する可能性もあるため、リハビリによる改善が必要です。認知機能に後遺症を抱えたままでは、仕事復帰してもミスを繰り返したり、業務の効率が低下したりする恐れがあります。
入院期間中も理学療法士を中心に、メモを取るなどの記憶訓練や、複数の作業を同時に行うなどの機能訓練を行いましょう。
職場でのミスは、メンタルに影響を与えて仕事を継続するのが困難になる恐れがあるため、認知機能向上のリハビリも重要です。
必要に応じて言語リハビリ
脳出血の影響で「失語症」や「構音障害」を患う可能性があることを理解しておきましょう。復職を考えると、言葉でのコミュニケーションが必要になるため、言語聴覚士のリハビリが必要です。
具体的には、「発語練習」や「発声練習」を行い、必要に応じてタブレッドなどの補助ツールを利用する練習も行います。言語のリハビリを行っても後遺症に悩まされる場合は、上司に部署異動や仕事内容の変更などを相談しましょう。
脳出血から仕事復帰後の注意点!周囲の理解と継続した体調管理
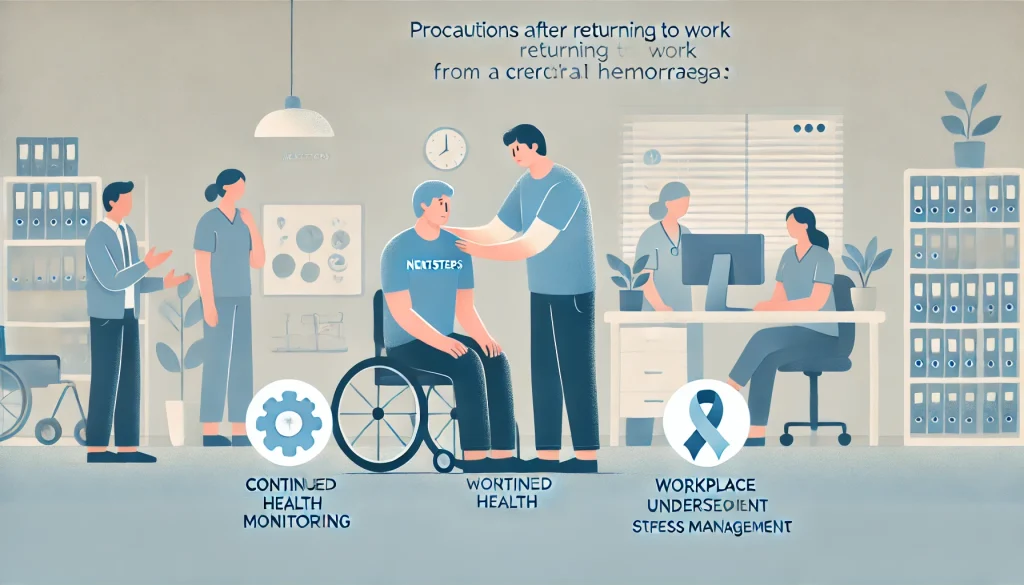
脳出血から仕事復帰する際は、自身の状態を職場や上司にしっかり理解してもらい、連携を取ることが大切です。他にも、脳出血後は生活習慣の改善や精神面のケアも必要になるため、退院後に意識すべきポイントを解説します。
職場との連携や上司の理解
脳出血後の仕事復帰には、職場との連携や上司、同僚に理解してもらうことが大切です。復職の話を進める際は、以下の項目を意識しましょう。
- フルタイム復帰ではなく、段階的な復職が望ましい
- 後遺症の状態に合わせて業務内容を調整する
- 高次脳機能障害など目に見えにくい後遺症を伝えておく
- 継続した通院の必要性を理解してもらう
療養中の体力低下や脳出血後遺症の影響を踏まえて、仕事復帰は慎重に進め、体や心への負担を減らしましょう。
再発予防の生活習慣
脳出血は再発の危険が高い病気のため、復帰後は生活習慣の改善を心がけましょう。再発すると重篤な後遺症の発症や、死に至る危険も否定できないため、再発予防には生活習慣の改善が大切です。
- 禁煙
- 飲酒は適正量を意識
- 適度な運動
- バランスの良い食事
脳出血の再発を防ぐには、特に高血圧を改善する生活習慣を心がけるのが望ましいです。食事や運動を工夫しながら、定期的な血圧測定も行いましょう。
メンタルヘルスのケア
脳出血後の仕事復帰は精神的な負担も大きいため、メンタルヘルスケアも大切です。仕事復帰後は、「周りに迷惑をかけているかも」という不安から、精神的不調に繫がるケースも珍しくありません。
精神的な負担を軽減するためには、「家族や周囲のサポート」「職場の理解」「専門家によるサポート」などが必要です。脳出血後も安心して仕事が継続できるように、身体面へのリハビリに加えて、精神面のケアを並行して行うのが重要といえるでしょう。
参考:厚生労働省「事業場における治療と職業生活の両立支援のためのガイドライン参考資料-脳卒中に関する留意事項-」
まとめ|脳出血から仕事復帰までの流れを把握しリハビリを進める
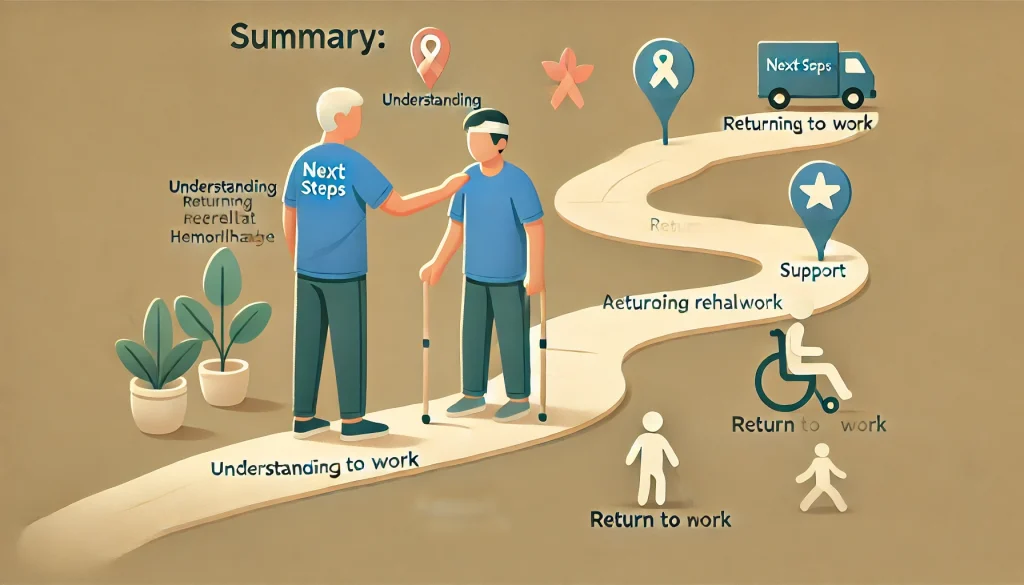
脳出血は高齢者だけでなく、若い世代でも発症する可能性がある病気です。そのため、もし発症した場合に備えて、仕事復帰までの流れや目安を理解しておくことがとても大切です。
脳出血の後遺症は人によって異なり、手足の動きやバランスといった身体機能の障害だけでなく、記憶力・集中力・判断力などの認知機能の低下が見られることもあります。そのため、仕事に復帰できる確率や復職までにかかる期間には大きな個人差があることを知っておきましょう。
仕事復帰を目指すうえでは、リハビリによる身体機能の回復だけでなく、職場との連携や周囲からのサポート体制を整えることも欠かせません。職場側と相談しながら、業務内容や勤務時間を段階的に調整していくことが、無理のない復職への近道です。
また、外からは見えにくい後遺症や精神的な不安を抱える人も少なくありません。 焦って復職を急ぐよりも、自分の体調や気持ちを確認しながら、慎重に一歩ずつ進めることが大切です。
脳出血後も長く仕事を続けるためには、体と心の負担をできるだけ軽くする工夫が必要です。例えば、休憩を多めに取る、リモートワークを活用する、サポートを頼みやすい環境を整えるなど、無理をせず続けられる働き方を見つけることが、安定した社会復帰につながります。