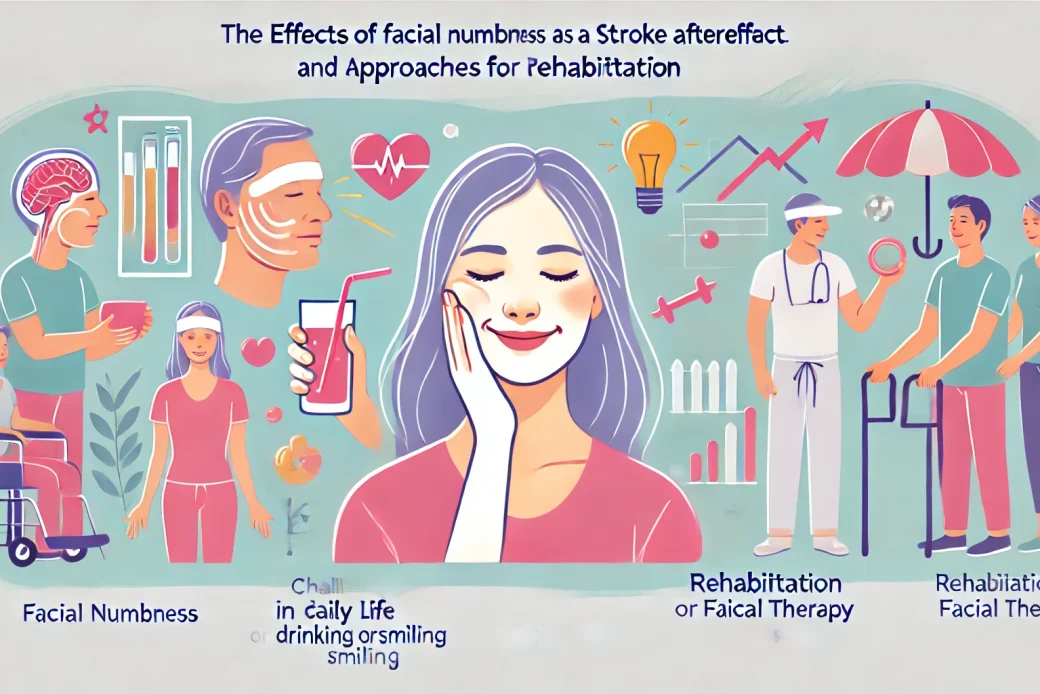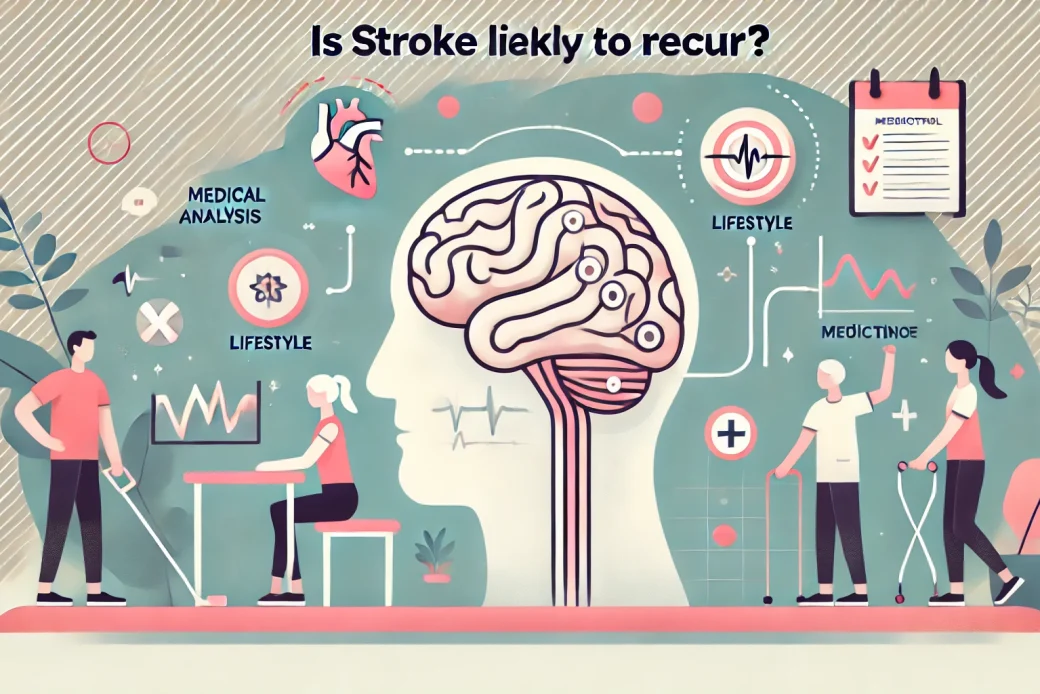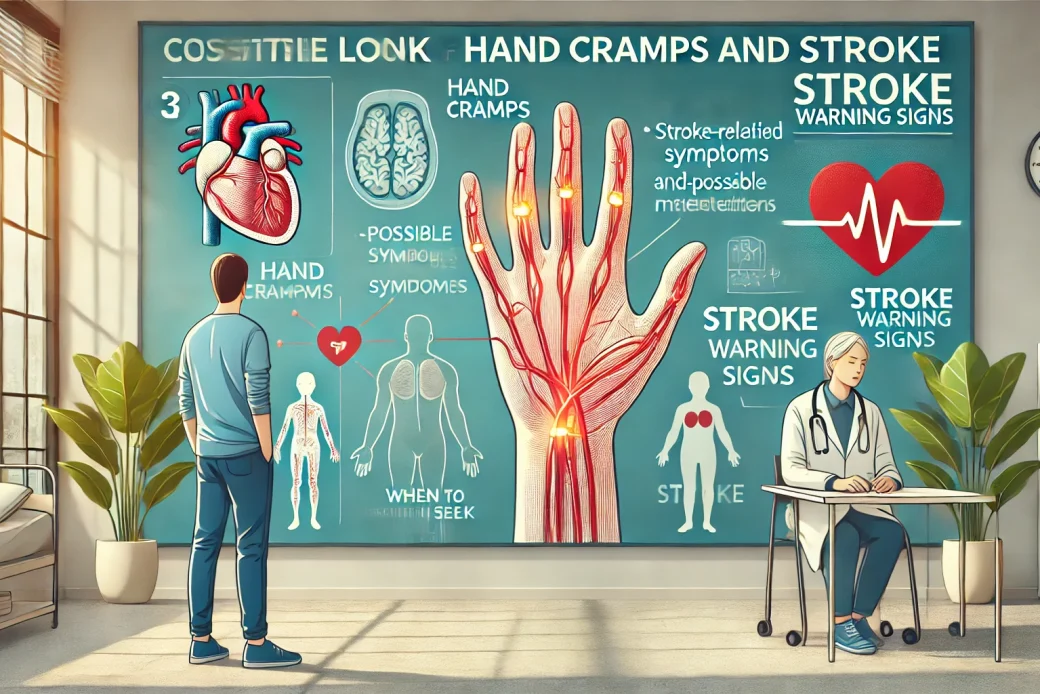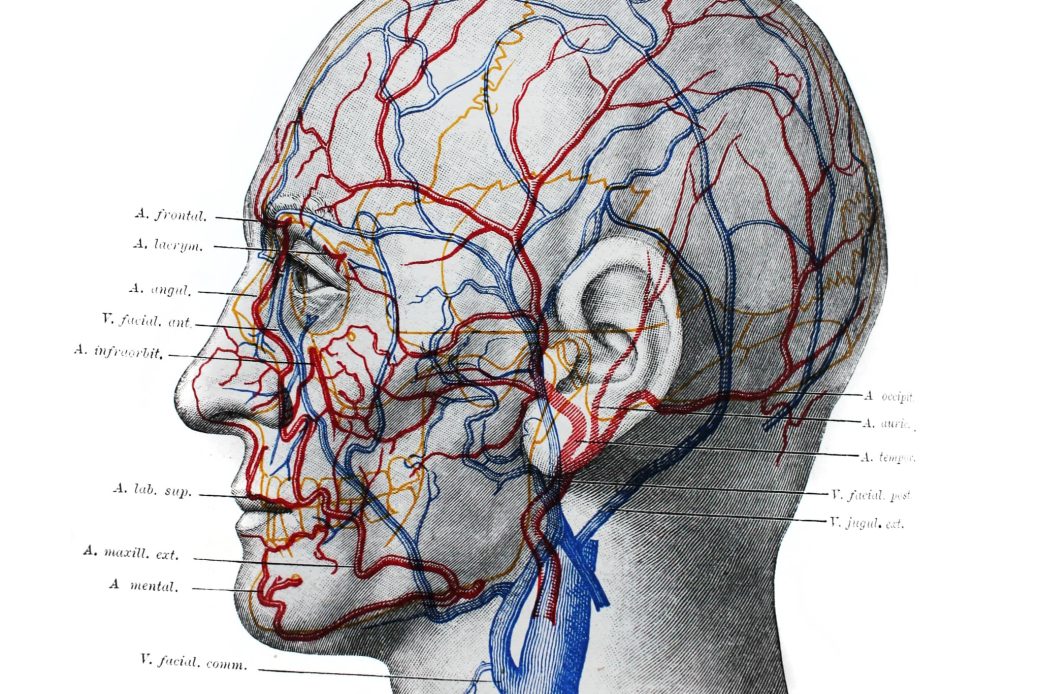【見える化】脳卒中リハビリで使えるサイアス評価|回復を数字で確認
2025.10.06

脳卒中のリハビリに取り組むなかで、「感覚だけでは回復の度合いが分かりにくい」と感じる方は少なくありません。リハビリ計画を立てる際に、どの指標を基準にすべきか悩む場面も多いでしょう。
そのようなときに役立つのが、脳卒中患者の機能回復を数値で見える化できるサイアス評価です。本記事では、サイアス評価 SIAS(Stroke Impairment Assessment Set)の目的や特徴、9種類の評価項目を解説します。
広く活用されている信頼性の高い指標を理解することで、経過を客観的に見られるようになるはずです。
目次
サイアス評価とは?脳卒中患者の回復を測る評価スケールの基本
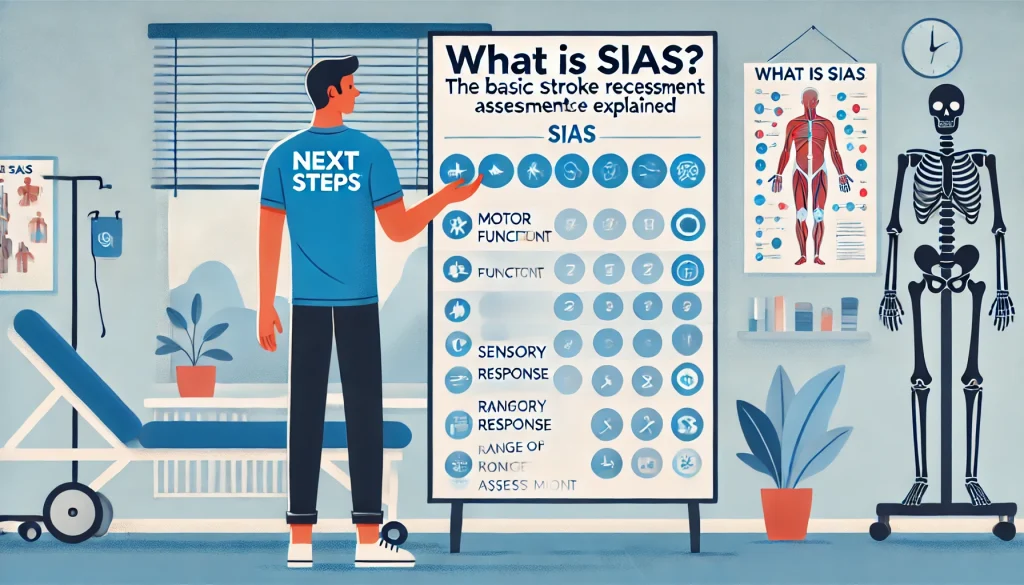
SIAS(サイアス)評価は、脳卒中患者の運動機能や感覚の回復度合いを「数値」で表すための評価法です。リハビリの場では、患者の状態を客観的に把握し、回復の進み具合を確認するために用いられます。
医療者や患者本人が同じ基準で状態を共有できる、サイアス評価の基本を確認しましょう。
サイアス評価の目的
サイアス評価の最大の目的は、「患者の機能回復を数値で見える化すること」です。感覚的な印象に頼るのではなく、具体的な点数で評価できるため、リハビリの経過を正確に追跡できます。これにより、次のようなメリットが生まれます。
- 患者本人や家族が、現在の状態や回復状況を客観的に理解できる
- 医師、理学療法士、作業療法士、看護師など多職種間での情報共有がスムーズになる
- 治療やリハビリの方針を科学的根拠に基づいて検討できる
- 患者ごとに適したリハビリメニューを調整しやすくなる
つまりサイアス評価は、患者・家族・医療者が「同じ基準」を持つための共通言語のような役割を果たし、チーム全体で一貫性のある支援を行う基盤といえます。
サイアス評価と他の方法の違い
脳卒中患者の評価には、「FIM(機能的自立度評価法)」や「バーセルインデックス」といった方法もあります。これらは、食事や着替え、トイレ動作などの生活全般における自立度を測ることを目的としています。
一方でサイアス評価は、筋力や感覚、協調性などの身体機能そのものに焦点を当てている点が大きな特徴です。例えば、歩行が可能かどうかを判断するだけでなく、足首をどの程度動かせるのか、手で物をつかむ力がどのくらいあるのかなどの細かい動作まで数値化します。
つまり、生活動作の改善に直結する前段階として、「身体の基礎的な力」を把握するのに適している方法です。サイアス評価は、脳卒中リハビリにおける身体機能の変化を正確に追跡できるツールといえるでしょう。
他の評価法と併用することで、より患者に合わせたリハビリ方針を立てやすくなります。
【9種類】回復を測るサイアス評価項目と読み取りポイント
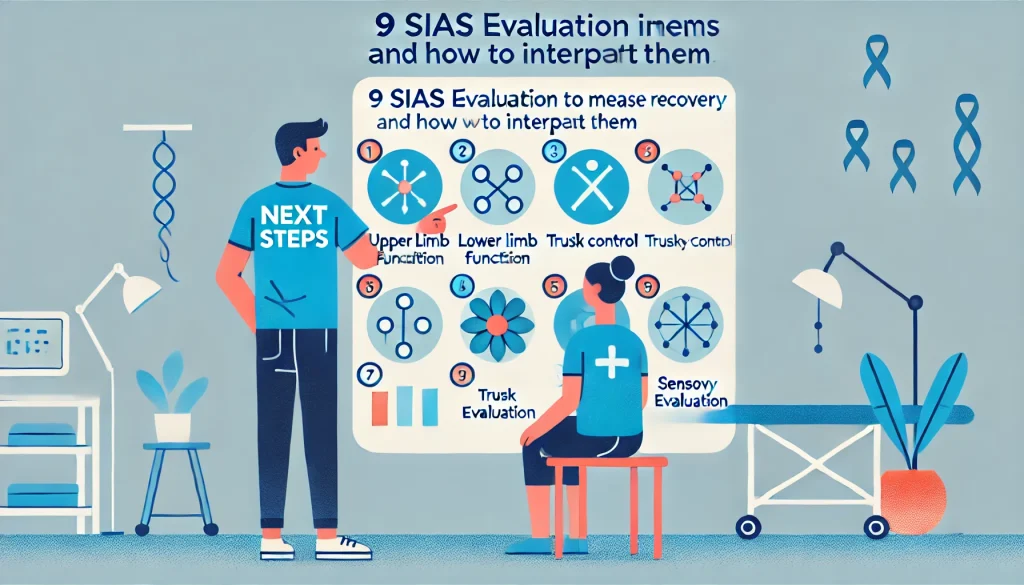
サイアス評価は、脳卒中患者の回復を「9種類の項目」に分けて測定します。これにより、患者がどの機能で回復しているのか、またどこに課題が残っているのかを明確にできる点が大きな特徴です。
評価項目9種類
サイアス評価では、以下の9つの機能を確認します。
- 麻痺側運動機能
- 感覚機能
- 筋緊張
- 非麻痺側麻痺側機能
- 関節可動域
- 痛みの有無
- 体幹の安定性
- 視覚や空間認知
- 言語やコミュニケーション
これら9つの評価項目は、それぞれ単独で判断するだけでなく、総合的に組み合わせて評価することが重要です。
例えば、麻痺側の運動機能と関節可動域は密接に関係しており、感覚機能や筋緊張の状態によっても影響を受けます。また、体幹の安定性や視覚・空間認知、言語・コミュニケーション能力などは、日常生活の質やリハビリ効果の全体像を把握する上で欠かせません。
回復の傾向と課題
回復期リハビリテーションにおける歩行獲得の予後予測とSIAS評価の研究によると、SIASを用いることで、過去の研究結果を定量的に検証できることが示されています。さらに、回復期病棟への入院時におけるSIAS体幹・非麻痺側項目の評価によって、退院時の歩行獲得が可能かどうかを予測できる可能性が示唆されました。
臨床現場では、下肢の筋力が改善して歩行が安定してきても手の細かい動きがまだ弱い場合や、感覚機能は回復していても協調性が低く転倒リスクが残るケースが見られます。このような詳細な評価は、リハビリ方針を的確に調整するために活用されます。
サイアス評価による点数化は、回復過程を可視化し、患者一人ひとりに合わせた訓練内容の決定や効果的な介入を可能にする重要な指標です。
参考:J-stage「回復期リハビリテーションにおける歩行獲得の予後予測とSIAS評価」
脳卒中リハビリで役立つ!サイアス評価の点数の付け方と流れ

サイアス評価は、脳卒中患者の回復度を数値で表すことができるため、リハビリの効果を客観的に確認するのに役立ちます。点数の付け方や評価の流れを理解しておくことで、より適切なリハビリ計画を立てられるでしょう。
評価手順の流れ
サイアス評価は、決められた手順に沿って行うことで、より正確に回復の経過を捉えることができます。基本的な流れは次のとおりです。
- 評価表を準備し、必要な環境を整える
- 患者の基本姿勢を確認し、安全に動作できる状態を整える
- 上肢・下肢・体幹などの各項目について動作を観察し、その都度点数を記録する
- すべての評価が終わったら総合点を算出する
- 前回の評価と比較し、どの部分が改善しているか、課題が残っているかを分析する
- 結果をもとに次のリハビリの重点を決める
このように、一連の流れが明確に定められているため、評価者による差を減らして時間の経過に応じたリハビリ効果を定量的に把握することが可能となります。
点数化の基準
サイアス評価では、各項目の点数は0〜3点または0〜5点です。点数が高いほど機能障害が軽度であると判断されます。
例えば、0点は全く動作できない状態を示し、3点または5点に近づくほど動作能力が改善していることを意味します。数値化することで、患者ごとの回復度合いや改善の傾向を客観的に把握でき、リハビリ計画の精度向上につながっています。
評価結果のまとめ方
評価結果は、単に点数を記録するだけではなく、「どの項目が改善しているのか」「どの項目が課題として残っているのか」を整理することが重要です。例えば、前回の評価と比較して下肢の点数が上がっていれば歩行練習の効果が出ている、上肢の点数に変化がなければ手先の訓練を強化する必要がある、と判断できます。
このように、点数化された結果はリハビリ方針を決定する重要な指標になります。総じて、サイアス評価による点数付けとその分析の流れを理解することは、リハビリ効果を最大化するために欠かせない要素といえるでしょう。
まとめ|サイアス評価の項目と点数を使って回復状態を把握しよう
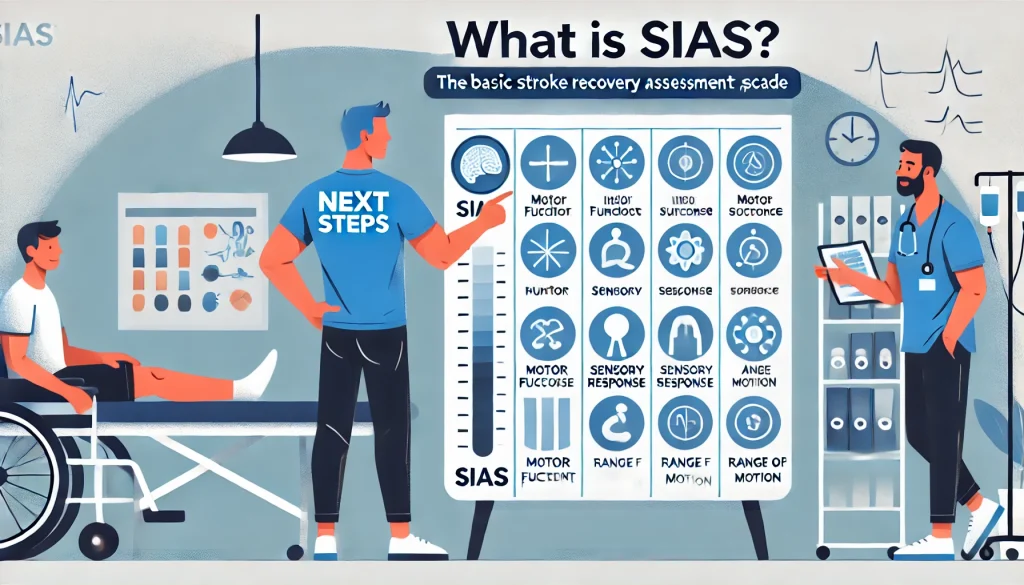
サイアス評価(SIAS:Stroke Impairment Assessment Set)は、脳卒中のリハビリにおける回復の状況を「見える化」するための重要な評価方法です。点数化することで、どの部分の機能が回復してきているのか、あるいはまだ課題が残っているのかを具体的に把握できるため、次にどのリハビリに力を入れるべきかを判断しやすくなるという大きな利点があります。
また、評価項目や手順を正しく理解しておくことで、リハビリの効果をより高めることができます。加えて、サイアス評価の結果を共有することで、患者本人や家族も回復の過程を客観的に確認できるという点も大きなメリットです。
サイアス評価は単なる数値の記録ではなく、リハビリの方向性を導くための大切な指標です。基礎知識として理解するだけでなく、実際のリハビリの現場で正しく活用することで、より効果的で質の高いリハビリの実現につながるでしょう。