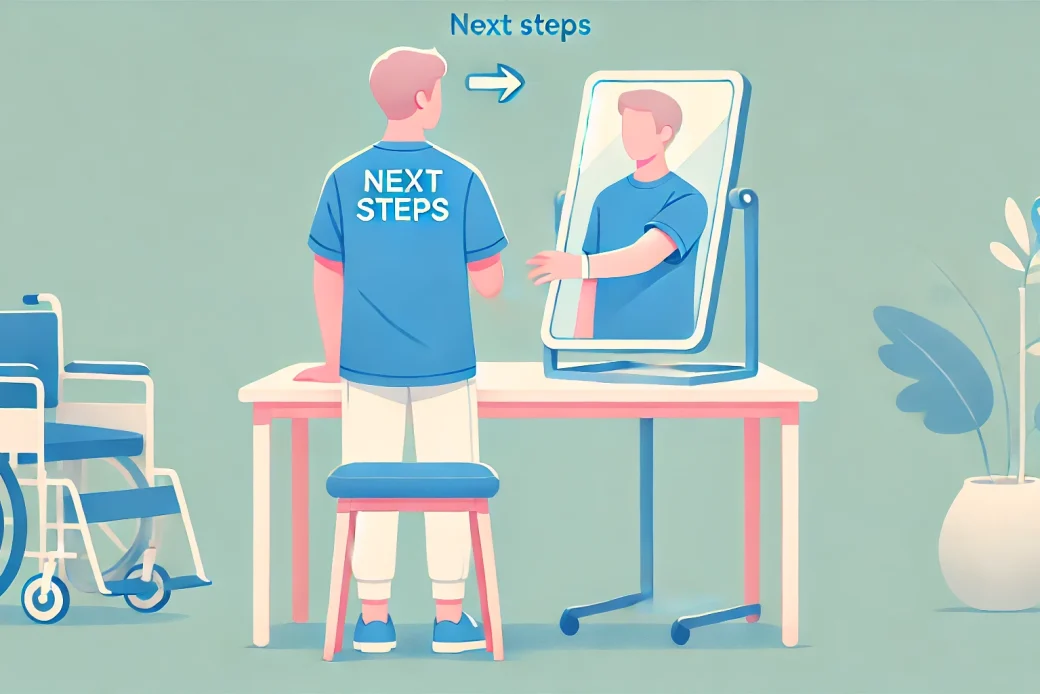リハビリのプレーシングで運動失調は改善するのか…内容や効果の有無とは
2025.04.14

運動失調という言葉を聞いたことがありますか?運動失調とは、身体を動かそうとする際に動作がうまく協調できず、目的とした運動がスムーズにできなくなる状態を指します。たとえば、起き上がる際や歩く際にふらついてしまう、食事で箸をうまく使えなくなるなどが代表です。
運動失調に対して効果的なリハビリ方法の一つとして、『プレーシング』があります。脳卒中や神経疾患のリハビリ現場で使用されているプレーシングですが、「本当に運動失調が改善するの?」と疑問を持つ方も多くいるのではないでしょうか。
今回はリハビリで行うプレーシングとは何か、実際に効果はあるのかを解説していきます。さらに、自分で実施できるのか、プレーシング以外の方法はあるのかといった気になるポイントも紹介します。
目次
リハビリで行うプレーシングとは何?対象疾患や使われる場面を解説

プレーシングは、姿勢の安定性を高めることを目的としたリハビリの一種です。神経系のリハビリ法である『ボバース法(神経発達学的アプローチ)』に含まれるアプローチのひとつで、特に運動失調のある方によく使われます。
プレーシングの基本的な考え方やどんな方が対象なのか、そして似た言葉との違いを分かりやすく解説していきます。
プレーシングリハビリの一種
プレーシングとは、『姿勢を保つ練習』です。たとえば、腕や足を一定の位置で止めて保つことで、筋肉のバランスや動きをコントロールする力を培います。反復して行っていくことで、身体の感覚と運動のつながりが高まることで、自然とスムーズな動作がしやすくなります。
見た目は筋トレのように見えますが、無理のない動き方を思い出せるようになったり、バランスがとりやすくなる効果が期待できます。
プレーシングを行う対象疾患
プレーシングは脳や神経に障害がある方に用いられるリハビリ方法です。脳卒中、脳性まひ、パーキンソン病などに対して、体の動かし方や感覚を整える目的で使われます。
プレーシングのメリットは、リハビリの初期段階から使えること。まだ動きが少ない状態でも、安全に取り組むことができ、入院中や寝た状態の方にも取り入れやすい方法です。
似たような言葉との違いは?
プレーシングと混同される言葉に『ポジショニング』があります。どちらも姿勢に対して介入しますが、目的や方法が違います。
ポジショニングは、クッションやタオルなどを使用して、寝ている人や座っている人の姿勢を外から整える方法です。
プレーシングは姿勢を調整するのはスタッフが行いますが、タオルなどを使用せず、ご本人が自分で姿勢を保つ練習です。
リハビリでのプレーシングとは何をする?効果や期待できること

プレーシングが有用だという事は理解していただいた方も多いと思います。では、実際にリハビリの現場では、プレーシングはどのように使われているのでしょうか。
評価やトレーニングとしての活用、筋緊張の調整、姿勢制御の促進といった具体的な効果について解説していきます。
評価やトレーニングとして使われる
プレーシングは、リハビリでは「体の状態を確認する評価」と「動きをよくする練習」の両方に使われています。
評価では、姿勢を保つ力やバランス感覚のチェックをします。練習では、腕を水平にあげて、30秒キープするなどの課題を行い、筋肉の使い方や身体の感覚を何度も確認していきます。
プレーシングは、簡単に見えてとても大切です。実際、運動失調のある人は、少しの姿勢保持でも難しい場合があります。反復して行うことで、身体が姿勢を記憶し、日常の動きにもつながっていきます。『姿勢のコントロールの再学習』が目的です。
筋緊張を調整する効果がある
運動失調のある人は、筋肉が固くなったり、ゆるくなったりします。プレーシングには、この「筋緊張」を整える効果があります。たとえば、手を前に出して一定の姿勢をキープするだけで、徐々に筋肉の緊張が整ってきます。これは、脳や神経が姿勢を正しく認識して、必要な筋肉を適切量働かせることができるようになるためです。
実際に麻痺している足にプレーシングを行って股関節周囲の緊張を調整してから動作を行うことで、しっかりと床を踏むことができた研究もありました。
プレーシングは、力まない姿勢を作る練習にもなります。無理なく筋肉を働かせることができると、身体の負担も少なくなります。
姿勢制御の促進ができる
プレーシングの一番の目的は、「自分で身体を安定させられる力(=姿勢制御)」を高めることです。
運動失調のある人は、座ったり立ったりするだけでもバランスを崩しやすくなります。プレーシングは、そういった基本動作を支える土台作りに役立ちます。
体の中心を意識し、左右のバランスを取る力を身につけることで、転倒のリスクも減らせます。姿勢を保つことは、歩く・座る・立つといった動作すべての基本です。
参考:最新のボバースアプローチの紹介―立位から臥位への姿勢変換を中心に―
【自主リハビリ方法】プレーシング以外に機能回復に役立つ運動とは

プレーシングだけでなく、自分で行えるリハビリは他にもあります。日常に取り入れることで、リハビリの効果をより高めることができます。
自分だけでもできるプレーシングや、フレンケル体操、重りを使った運動などを紹介するので、日々の生活に取り入れてみましょう。
プレーシングは自分でもできる?
プレーシングは、自宅でも取り組めます。簡単な姿勢保持から始めるのがポイントです。
たとえば、座っているときに背筋を伸ばし、手を膝の上に置いて30秒間そのまま保つ練習などがあります。これでも十分、姿勢を制御する練習になります。
最初は無理をせず、1日1回〜2回でもOK。短時間でも、毎日コツコツ継続することで効果が期待できます。
しかし、適切なポジションを見つけることが難しく、初めから自分だけで行うことは困難です。リハビリスタッフに見てもらい、どのようにやればよいかを指導してもらってから行いましょう。
運動を視覚的に確認するフレンケル体操
フレンケル体操は、目で見て動きのズレを修正しながら身体を動かすリハビリです。たとえば、足の動きを見ながらゆっくり持ち上げたり、決まった位置に足を置いたりします。
この体操も、プレーシング同様に運動失調に有効です。目で確認しながら反復して動くことで、身体の動きを調整しやすくなります。
フレンケル体操は、寝たまま・座ったままでもできるものが多く、実践しやすいです。ゆっくりとした難易度が低い動きが多いため、高齢者にも適しています。
まとめ|リハビリ・プレーシング

リハビリで行われるプレーシングという方法は、座ったり立ったりするときに体を安定させる練習です。人の体は、普段からバランスをとりながら動いていますが、うまくコントロールできないと転びやすくなったり、体がフラフラしてしまいます。そこで、プレーシングを使って、自分で体をしっかり支えられる力、つまり姿勢制御を高めようとするのです。
また、運動失調という、うまく体を動かせない状態に対しては、腕や足などに重りをつけて動かす方法も役立ちます。これは重りをつけることで筋肉や関節が刺激を受け、動きが安定しやすくなるからです。たとえば、手首に軽い重りを巻いて物を持ち上げると、感覚がわかりやすくなって、動きを正確にしやすくなります。
プレーシングをリハビリに取り入れるときは、自分で練習することもできますが、安全に効果を出すためには、リハビリスタッフや専門家に相談して進めるのがおすすめです。正しい姿勢や動かし方を知りながら行えば、無理なく体の機能を高めることができます。