
リハビリ現場で活用されるレベルの種類を紹介|状態に応じて使い分けることがポイント
2025.08.04

自宅での生活を続けながらリハビリを行う場合、本人の状態にあった支援や介護の目安を知ることが大切です。その指標となるのが「リハビリのレベル」です。
回復の段階や活動範囲に応じてレベルがあり、理解しているとどのくらい介助が必要か、今後どのようなリハビリが必要かをイメージしやすくなります。
今回は、レベルの基本的な考え方から種類や評価方法まで、家族や支援者が日常生活のサポートに活かせる内容を解説します。リハビリのレベルを知ることで、介護やリハビリの方向性を決めやすくなり、安心して生活を続けられるでしょう。
目次
リハビリにおけるレベルの意味は?大きく3つのステップにわけられる
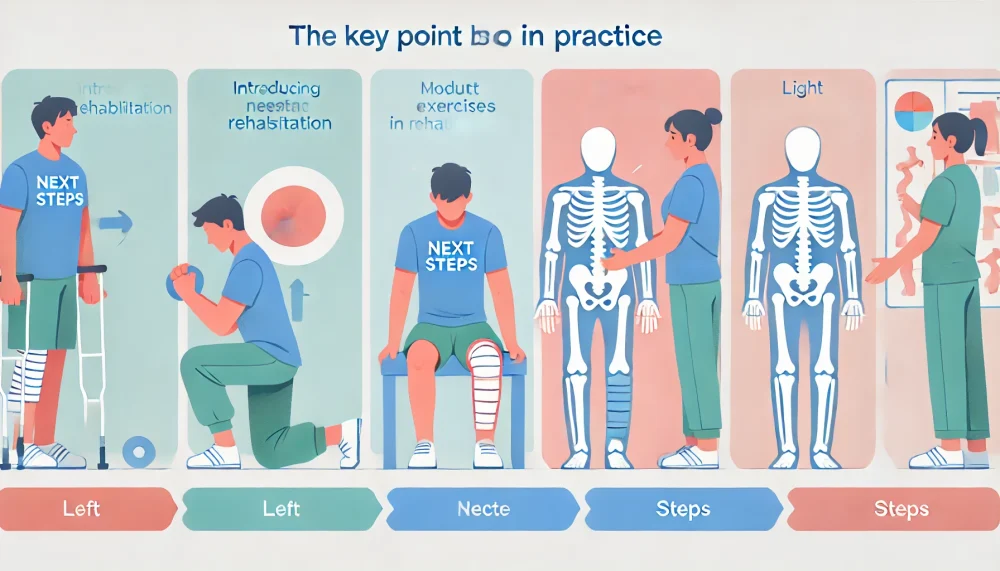
リハビリにおけるレベルとは、回復の段階や支援の必要度を示す目安です。状態にあわせて適切に把握することで、無理のないリハビリ計画や介護方針を立てられます。レベルの基本的な考え方と、急性期・回復期・維持期の3つの段階について理解しておきましょう。
リハビリにおけるレベルとは
リハビリの現場で用いられるレベルとは、患者の身体機能や活動能力の程度を段階的に評価したものです。
例えば「見守りが必要なレベル」や「自立して活動できるレベル」など、医療従事者や介護職が共通の指標として使うことで、支援の度合いを適切に調整できます。
急性期・回復期・維持期の3段階
リハビリは、大きく3段階に分けて進められます。
〇急性期:病気やけがの直後で、命を守るための治療と並行しながら合併症予防や関節が固まらないようにする軽いリハビリが始まる
- ベッド上での体位変換や関節可動域運動が中心
- 呼吸機能や血流の維持、褥瘡(床ずれ)予防が目的
- 医療スタッフが細かく状態を観察し、安全を最優先に進める
この段階では、家族が患者の状態を理解して過度な刺激や無理な動作を避けることが大切です。
〇回復期
症状が安定し、積極的な機能回復や動作練習が可能になる時期
- ベッドから車いすへの移乗、歩行練習、食事や着替えなどのADL(日常生活動作)訓練
- 訪問リハビリや通所リハビリに切り替わるケースも多い
- 「どこまで自立できるか」「どの動作に介助が必要か」を見極めるのが重要
家族にとっては、退院後の生活に備えて住宅環境の調整(手すり設置・段差解消)や介護方法の習得が始まる段階でもあります。
〇維持期
在宅や施設で生活しながらこれ以上の機能低下を防ぎ、生活の質を維持することが目標
- 筋力維持や関節の柔軟性を保つ運動を継続
- 趣味や地域活動の参加を支援し、社会とのつながりを保つ
- 介助方法や福祉用具の見直しも定期的に行う
維持期は「現状を守るリハビリ」と誤解されやすいですが、生活の安定や介護負担の軽減に直結する重要な段階です。家族がレベルや目標を理解していると、支援者との情報共有がスムーズになり安心して在宅生活を続けられます。
上記の3段階は、厚生労働省のリハビリテーション関連指針でも用いられており、医療から介護への切り替えや支援計画を考える基準として広く活用されています。
リハビリにおけるレベルの種類を網羅的に解説|適切に評価することが大切

リハビリの計画を立てる際には、患者の状態に合わせていくつかのレベルを把握することが重要です。それぞれの特徴を理解できれば、介助の量やリハビリ内容の調整がしやすくなり、安心して生活できる環境づくりにつながります。
エビデンスレベル
エビデンスレベルとは、リハビリで行う方法や介入の効果を裏付ける科学的根拠の強さを表す指標です。根拠がしっかりしている方法ほど安全性と有効性が高く、医師やリハビリ専門職が治療方針を決める際の重要な材料となります。
家族がこの概念を知っておくと、説明を理解しやすくなり、治療選択に納得感を持てるでしょう。
見守りのレベル
見守りのレベルは、患者が日常動作を行う際に、どの程度の観察や声掛けが必要かを示す目安です。例えば、動作自体は自立していても安全確認のためにそばで見守る段階や、転倒のリスクが高いため介助者が声を掛けながら近くで待機する段階があります。
見守りのレベルを把握できていると、必要以上の介助を避けつつ安全性を確保でき、家族の負担も減らしやすくなるのです。
活動レベル
活動レベルとは、患者が日常生活や社会参加でどの程度活動できるかを示す指標です。歩行距離や外出頻度・家事・趣味への参加状況などが評価対象となり、身体機能だけでなく生活の質を測る目安となります。
活動レベルを定期的に確認して、リハビリの効果や次の目標設定を明確にしましょう。
介助レベル
介助レベルは、動作の一部または全体でどの程度の支援が必要かを示す段階です。
- 全介助:ほぼすべての動作で介助が必要
- 部分介助:立ち上がりや移乗など、一部だけ補助が必要
- 自立:介助なしで安全に動作可能
介助レベルを共有することで、家族・介護スタッフ間の認識をそろえて安全かつ効率的なケアが可能となります。
リハビリ現場で活用されるレベルの分類法|多角的な評価でよりよい生活を実現
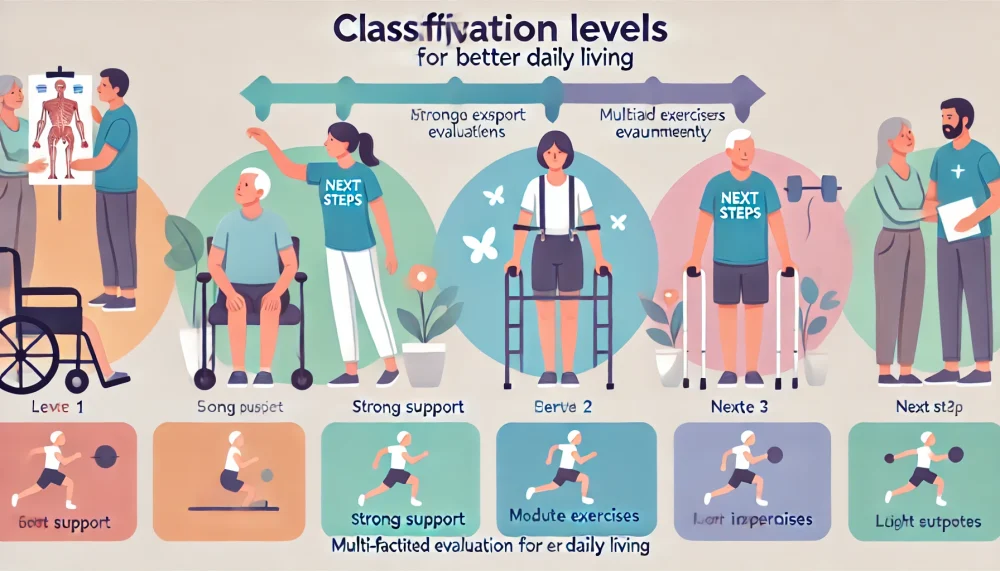
リハビリのレベルを正確に把握するには、身体機能だけでなく生活全体を評価することが大切です。ICFは身体機能や活動だけでなく、生活環境や個人の背景まで含めて評価でき、本人に合った支援や介護方法を考える際に役立ちます。
ICF(国際生活機能分類)における3つの要素
ICFでは、生活機能を「心身機能・活動・参加」の3つに分けて評価します。
- 心身機能と構造:筋力や関節の動き、感覚機能など身体の機能や構造
- 活動:立つ・歩く・食事するなど日常的な行動ができるかどうか
- 参加:社会生活や家庭での役割、趣味や地域活動への参加度
上記の3つを総合的に評価することで、単なる身体機能の回復だけでなく、生活の質や社会参加のしやすさまで含めたリハビリ計画が立てられます。例えば、「歩ける」ことがゴールではなく「外出して買い物に行ける」「家族と一緒に食卓を囲める」など、具体的な生活目標につなげやすくなるでしょう。
2つの背景因子
ICFでは、生活機能に影響を与える要素として環境因子と個人因子の2つを考慮します。
- 環境因子:家の段差、介助者の有無、福祉用具など周囲の環境
- 個人因子:年齢、性格、生活習慣、価値観など個人の特性
同じ身体機能でも、住環境が整っていれば自立可能な場合と介助が必要な場合があるように、背景因子によって支援の方法は大きく変わります。この視点を取り入れることで、より個別性の高いリハビリ計画や生活支援を実現できるのです。
ICFを活用するポイント
ICFを活用する際は、身体機能だけに注目せずに生活全体を見渡す視点が大切です。
- 自立度や活動範囲だけでなく、社会参加や役割の回復も重視する
- 環境や家族のサポート体制を評価し、必要な福祉サービスや住環境の調整に活かす
- 継続的に評価を行い、回復状況や生活変化に応じて計画を見直す
こうした評価により、本人にとって本当に必要な支援やリハビリレベルを見極めやすくなります。
まとめ|リハビリにおけるレベルの適切な活用が身体機能の維持・向上につながる

リハビリを進めていくうえで大切なのは、今の体の状態に合ったレベルを知ることです。レベルを理解することで、その人にあったリハビリの計画を立てやすくなります。
リハビリには大きく分けて「急性期」「回復期」「維持期」という段階があります。たとえば、入院直後の体調が不安定なときは急性期、少しずつ体を動かせるようになってきたときは回復期、その後の日常生活を安定させるための時期は維持期です。
さらに、リハビリの目標を決めるときには、活動レベルや介助がどれくらい必要かといったこともあわせて考えます。これらを組み合わせることで、一人ひとりに合った具体的な目標を立てることができます。
また、ICF(国際生活機能分類)という考え方を使うと、体の動きだけでなく、生活環境や家族のサポートなどもふくめて幅広く評価できます。その結果、介護する人の負担を減らしたり、生活の質を高めたりすることが可能になります。
リハビリは患者本人だけでなく、家族や支援する人も一緒にレベルを理解して共有することが大切です。そうすることで、安心して取り組めるリハビリの環境が整います。










