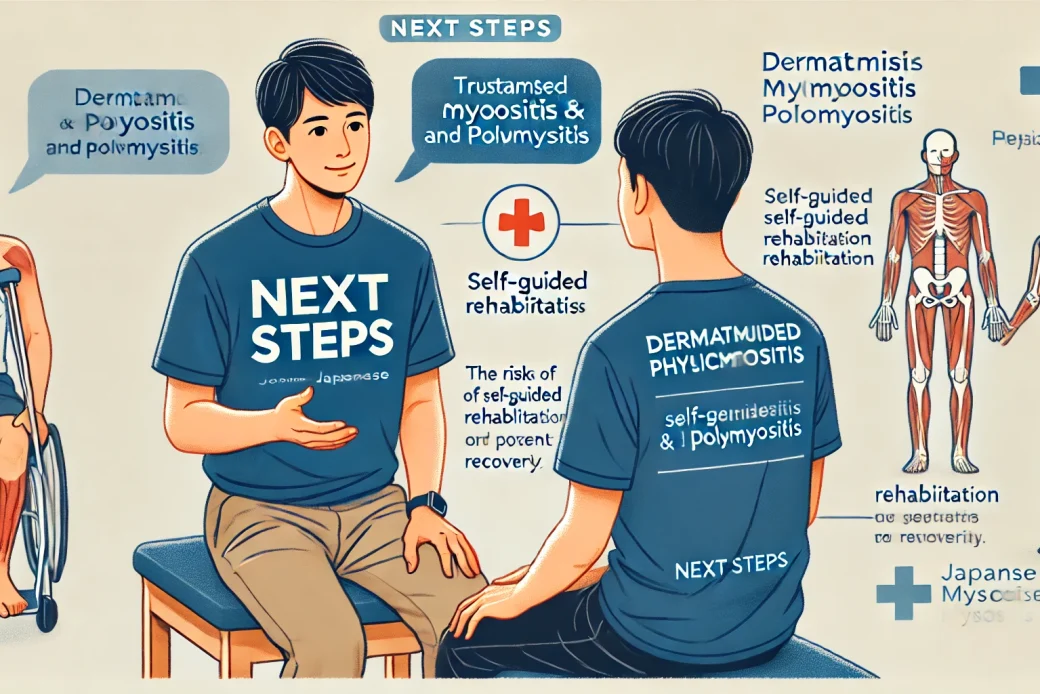パーキンソン病のリハビリは誰に頼るべき?体力・筋力維持に必要な運動とは?
2025.05.09

パーキンソン病は、回復が難しいとされる進行性の神経疾患です。手足の震えや筋肉のこわばり、動作に不自由さが出るなど、進行すると日常生活に支障がでる病気です。
現在は、薬物療法が中心になっていますが、リハビリテーションによる運動機能の維持・向上も非常に重要な治療の柱となっています。
しかし、リハビリと言っても、どのように取り組めばよいのか、誰にサポートを頼ればよいのか、悩む方も多いでしょう。また、家族がサポートする場合も、無理を重ねて共倒れにならないための「支援体制づくり」が欠かせません。
今回は、パーキンソン病におけるリハビリの必要性と、体力・筋力維持に効果的な運動方法を解説します。また、専門家の役割や家族が頼れる支援先を理解しておくことで、過度に自分自身への負担をかけずにパーキンソン病と向き合うことが可能でしょう。
目次
パーキンソン病のリハビリはなぜ必要?症状が軽くなる効果とは?

まず、前提としてパーキンソン病が発症するとなぜリハビリが必要になるのでしょうか?具体的に日常生活に対して生じる「支障」に焦点をあててチェックしていきます。
パーキンソン病による日常生活への支障
パーキンソン病の進行は、ちょっとした運動機能への影響や表情の不自由さだけでなく、生命維持のために必要な行動を制限させてしまいます。
・歩行時のふらつき、すり足歩行
・立ち上がり・寝返りなど動作開始の困難
・書字・食事動作の細かい動作の困難
・嚥下障害による誤嚥リスク
=生活の質(QOL)を著しく低下させるきっかけとなります。
パーキンソン病のリハビリに対する必要性を考える
パーキンソン病は「進行性」ですが、リハビリによって「筋力低下の防止」「柔軟性・可動域の維持」「姿勢・バランスの改善や維持」「歩行能力の維持、向上」への効果が期待できます。
もちろん、重症度が高くなってからでは手遅れになる可能性があるため、早期対応が求められます。
もちろん、リハビリに取り組むことはパーキンソン病を治すわけではなく、進行を遅らせる行為ですが、少しでも長く日常生活の快適さ、自立した生活を送るきっかけ作りになるでしょう。
実際に症状が軽減された事例はあるの?
パーキンソン病患者に対する運動療法は、2025年現在、多くの改善報告が挙げられています。患者の症状自体の大きな改善、介助量の減少など、成果事例として出ているため「パーキンソン病のリハビリ」は、昨今当たり前のように必要な行動と考えていいでしょう。
転倒リスクの低減やADLと言われる日常生活動作能力が、向上することは患者にも、そのご家族にも大きなメリットがあると考えられます。
たとえば、週2回の理学療法介入を6か月続けた事例では、立ち上がり動作や屋外歩行の安定性が大きく改善し、介助量が減ったという報告も。
【進行を抑える】パーキンソン病にはリハビリプログラムのガイドラインが?

パーキンソン病は、継続的にリハビリを行う必要があります。ここで解説するパーキンソン病のリハビリプログラムのガイドラインをもとに、専門家と適切な方法で取り組むことが大切です。
パーキンソン病のリハビリ…ガイドラインとは?
日本神経学会や各国の神経学会では、パーキンソン病リハビリに関するガイドラインが作成されており、以下のリハビリ目標が掲げられています。
・身体活動量を増やす
・バランス感覚と転倒防止
・可動域と筋力の維持
・自立した日常生活の促進
パーキンソン病のリハビリにおいては、定期的な評価と、個々の患者の症状に応じたリハビリプログラムが推奨されています。
参考:J-Stage「パーキンソン病に対するリハビリテーション」
パーキンソン病のリハビリは専門家の指導が必要?
パーキンソン病は、単なる運動機能低下だけでなく、自律神経障害や認知機能障害を伴うことがあります。そのため、専門家の指導のもと、患者ごとに適切な負荷設定やリスク管理が必要となるのです。
〈主な専門職と役割〉
・理学療法士:歩行・バランス訓練
・作業療法士:日常生活動作の訓練
・言語聴覚士:発声・嚥下リハビリ
〈なぜ必要なの?〉
端的にまとめると専門家の指導があることによって「改善具合の進捗を測れる」、「適切な方法でリハビリができる」という2つの点が考えられるでしょう。
なんとなく行うリハビリよりも、やり方や目的・目標が明確である方が改善度やリハビリの意味は大きいです。
体力・筋力維持に必要な運動とは
パーキンソン病患者の方には、以下の運動が推奨されています。
・大股歩き練習(すり足防止)
・柔軟体操(ストレッチ)
・下肢筋トレーニング(椅子からの立ち上がり反復など)
・バランスボールを使った体幹トレーニング
・音楽に合わせたリズム運動(リズムが動作開始を助ける)
ただし、体調や病期に応じて強度調整が必要なため、自己流ではなく専門家の指導のもと行うようにしましょう。
もし家族が…パーキンソン病のリハビリは誰に頼るべきか

高齢者ほど発症リスクの高いパーキンソン病ですが、どのような方でも発症する可能性があります。もしも…のときに備えて、パーキンソン病のリハビリを行う際、誰に頼るべきなのかを確認しておきましょう。
パーキンソン病のリハビリに関わる専門家
パーキンソン病のリハビリでは、次のような専門職が関わってきます。
- 主治医:診断、治療方針の決定など
- 理学療法士:歩行訓練、筋力強化、転倒予防プログラムなど
- 作業療法士:日常生活動作の支援、生活環境の調整など
- 言語聴覚士:発声訓練、嚥下機能改善訓練など
- 訪問リハビリスタッフ:自宅でのリハビリ、家族の介護負担軽減の支援など
- 介護支援専門員(ケアマネジャー):介護サービスの調整、行政手続きの支援など
とくに訪問リハビリでは、自宅という安心できる環境で、個々の生活スタイルに合わせた専門的な運動指導や生活動作訓練を受けることが可能です。「専門家に頼る」ことは、患者本人の生活の質の向上だけでなく、家族全体の負担軽減につながります。
施設利用と自宅でのリハビリはどちらも大切
通所リハビリやデイサービスでは、体力維持や社会参加、刺激のある生活リズムを作ることができます。一方、在宅リハビリでは、住環境に即した訓練・個別対応・継続性の高い支援などを受けることが可能です。
両方を適切に組み合わせることが、より効果的なリハビリにつながります。家族だけで支えようとせず、専門家と連携しながら、「支援を受けながら暮らす」仕組み作りを進めましょう。
まとめ|パーキンソン病のリハビリ

パーキンソン病は、少しずつ症状が進んでいく病気です。でも、正しいリハビリを受けることで、進行をゆっくりにしたり、自分でできることを長く続けたりすることができます。
たとえば、歩く力をつけたり、転ばないようにバランスをよくしたり、トイレや着替えなどの日常の動作を自分でできるようにしたりと、リハビリにはたくさんの良い効果があります。気持ちが前向きになることも、リハビリの大切なポイントです。
また、”家族やまわりの人の負担を減らすためにも、「ひとりでがんばらないこと」”が大切です。お医者さん、訪問してくれるリハビリの先生、介護の相談にのってくれる専門家など、信頼できる人たちと協力することが必要です。
「困ったときに相談できる場所がある」ことは、大きな安心になります。それが、リハビリを続ける力にもなります。
これからも自分らしく、家で快適に生活を続けるために、できることから一歩ずつ始めてみましょう。