
運動麻痺は改善できるの?改善のポイントと自宅でできる対策とは
2025.07.25
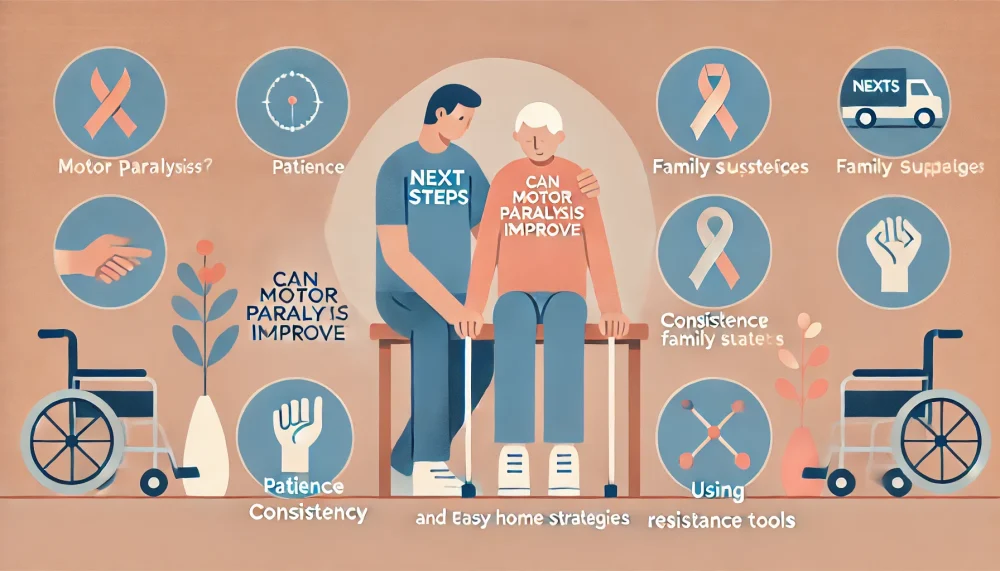
運動麻痺によって手足が思うように動かせないと、「麻痺は改善できるの?」と不安に感じる方もいるでしょう。リハビリに励むご本人やご家族にとって、麻痺が良くなる可能性や取り組み方は大きな関心事です。
運動麻痺は、適切な治療とリハビリを行うことで改善に期待ができます。そのためには、正しい知識を身につけ、継続的に取り組むことが大切です。
この記事では、脳と身体のメカニズムや効果的なリハビリのステップ、事故防止のポイントを具体的に解説します。効果的なリハビリを行うためにも、運動麻痺の改善に必要な知識やコツを理解しておきましょう。
目次
運動麻痺とは?改善のため脳と身体のメカニズムを知ろう
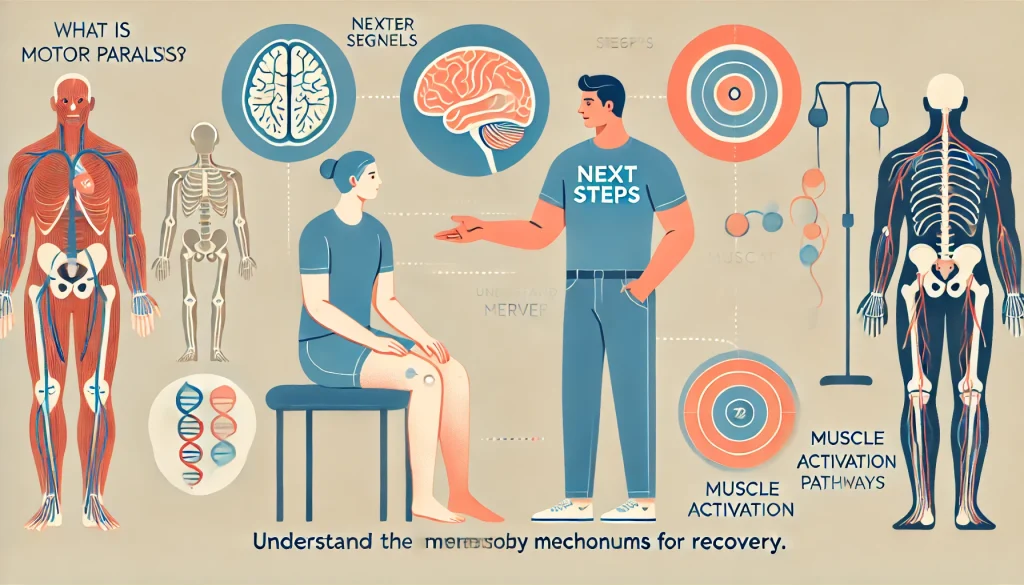
運動麻痺とは何か、原因とメカニズムを理解しましょう。脳と神経のしくみを知ることで、なぜ麻痺が起こるのか、そしてどのようにすれば改善を目指せるのかが見えてきます。
運動麻痺の主な原因は
運動麻痺の主な原因は、脳卒中(脳梗塞や脳出血)です。脳の血管が詰まったり破れたりすると脳細胞がダメージを受け、手足を動かすための神経回路がうまく働かなくなります。
そのほか、脊髄損傷や頭部の外傷、神経系の病気なども原因になります。
運動を指示する脳と神経のつながり
身体を動かそうとするとき、脳の運動をつかさどる部分から「腕を上げろ」「足を動かせ」と指令が出て、神経を通じて筋肉に伝わります。指令が筋肉に届くことで、手足が自分の意思どおりに動くようになるのです。
脳や脊髄の伝達経路が損傷すると、傷ついた箇所より下の神経に指令が届かず、麻痺が起こります。筋肉に損傷がなくても、神経の「配線」が途切れると自分の意思で動かせない状態になってしまうのです。
片麻痺・両麻痺などの分類と特徴
運動麻痺が起こる部位や範囲によって、いくつかの種類に分類されます。代表的なのが片麻痺と両麻痺です。
片麻痺は身体の右半身または左半身、片側の上下肢に麻痺が起こる状態をいい、主に脳卒中で現れます。両麻痺は四肢麻痺ともいわれており、両手両足すべてに麻痺が起こる状態です。ほかにも、1本の手か足だけが麻痺する単麻痺や、両方の下肢に麻痺が出る対麻痺(下半身麻痺)などもあります。
麻痺の程度や筋緊張によって分類もされ、症状に応じてケアの内容も異なることを理解しておきましょう。
参考:健康長寿ネット「麻痺」
運動麻痺は改善が期待できる
運動麻痺は適切なリハビリによって改善が期待できます。『麻痺して動かない手足でも、繰り返し動かすことで脳の可塑性が働き麻痺の改善が期待できる』ことが研究で明らかになっています。可塑性(かそせい)とは、損傷した神経回路の役割を別の神経部分が代わりに担ってくれる力のことです。
訓練を続ければ、新たな神経の通り道が生まれ、徐々に動きが取り戻せる可能性があります。麻痺が残っても適切なリハビリを行えば機能回復に期待できるため、継続的に行うことが大切です。
運動麻痺の改善を目指すために必要な3つのステップ紹介
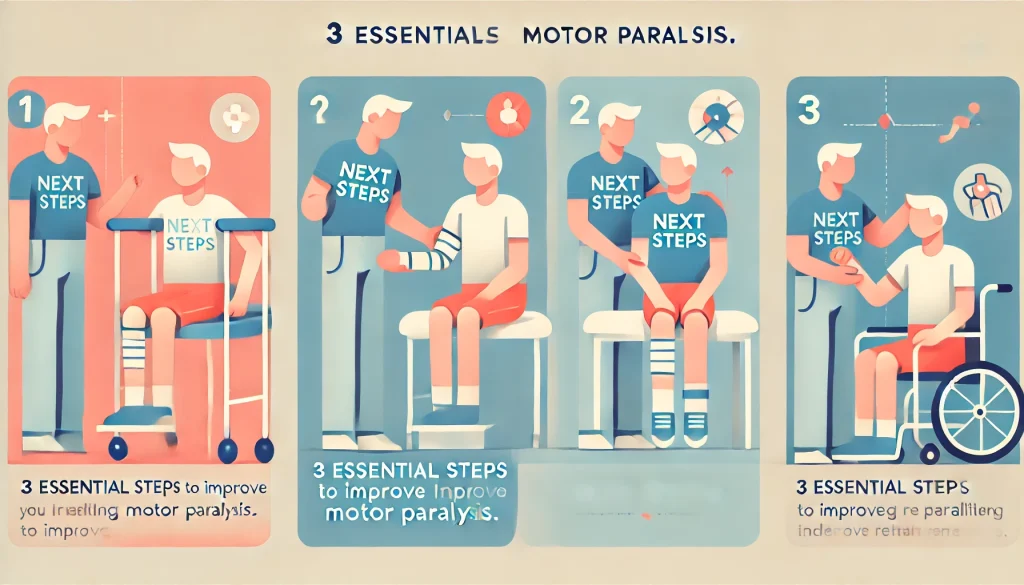
運動麻痺を改善するリハビリに臨む上で、押さえておきたい3つのステップがあります。早期リハビリ・適切な運動療法・メンタルケアをしながらの継続です。具体的な内容とポイントをおさえておきましょう。
発症直後からの早期リハビリの重要性
発症直後からリハビリを開始することで早期回復に期待ができるため、運動麻痺の改善にはスタートの早さが重要です。
早期にベッド上で座る・立つなど基本的な動作を始めることで、筋力の低下や関節の拘縮を防ぐだけでなく、脳や神経系への刺激となり機能回復を促す効果が期待できます。長期間にわたって安静にし過ぎていると、いざリハビリを始めても思うように動かせない状態になるため、できるだけ早期に身体を動かし始めることが肝心です。
適切な運動療法の種類と頻度
麻痺の改善には、リハビリの継続が欠かせません。主に、以下のような内容が挙げられます。
- ストレッチ
- 関節運動
- 筋力トレーニング
- 作業練習
- 歩行練習
- 立ち上がり練習
上記はほんの一部で、症状に応じてさまざまなプログラムがあります。ポイントは、麻痺した部分をなるべく使うことです。
基本的にはリハビリは毎日行うのが理想的ですが、難しい場合は、毎日15分でも30分でもこまめに動く時間を作るとよいでしょう。
心が折れないためのメンタルケアと継続のコツ
リハビリは短距離走ではなく長い道のりのマラソンです。思うようにいかず落ち込んだり、心が折れそうになったりするときもあるかもしれません。そこで、メンタルケアとモチベーションの維持が重要です。実際、発症から半年以上経ってからも機能が回復していく方はたくさんおり、そうした方々はリハビリへの意欲が高い傾向にあると報告されています。
諦めてしまったら本来得られるはずの回復も得られなくなるため、モチベーションを保つためにも目標設定を行うことがおすすめです。
目標設定の際は、大きな目標だけではなく小さな段階目標も設定し、ひとつずつクリアすることで達成感を得られます。うまくいかない日があっても、自分を責めすぎず、改善策をセラピストと相談しながら前向きに取り組みましょう。さらに、周囲からの支えもメンタル面では大きな力になります。
自宅でできる!運動麻痺を改善のためのエクササイズと対策

運動麻痺は日常生活で自主的に身体を動かすことで、より効率的な改善に期待ができます。病院や施設でのリハビリ時間は限りがあるため、自宅でできる自主トレーニングを並行して行うのもおすすめです。無理のない正しいやり方を心がけ、安全性に留意しながら取り組みましょう。
自分でできるストレッチ
ストレッチは、自宅で簡単に行える効果的なリハビリです。毎日続けることで筋肉の緊張が和らぎ、痙縮の予防や関節可動域の維持に役立ちます。
・肩のストレッチ
- 椅子に座り両手の指を組むまたは麻痺している腕を掴む
- 肘をまっすぐに伸ばしたまま腕をゆっくりと頭上に持ち上げる
- 床の方へ下ろす
反動をつけず、痛みのない範囲でゆっくり行うのがポイントです。肩関節や肘の可動域が広がり、血行も促進されます。
・足のストレッチ
- 仰向けに寝て両足を組む
- 麻痺側の足を上にする
- つま先(足の指先)をゆっくりと反り返らせて足首から足の指まで伸ばす
足の指が強く曲がって硬くなっている場合は、無理に伸ばそうとせず痛みのない程度にゆっくりと行いましょう。
そのほかに、膝裏を伸ばすハムストリングスのストレッチや、ふくらはぎのストレッチも効果的です。
注意すべき動作と事故防止のポイント
日常生活では、転倒などの事故の予防が必要です。麻痺によってバランスが取りづらく、油断すると転んでしまう危険があります。特に片麻痺の方は、転倒や転落のリスクが高く骨折やケガにつながりやすいため、以下のポイントに注意しましょう。
- 動作はゆっくりと丁寧に行う
- 補助具や福祉用具を活用する
- 家の中の環境を整える
- 視野の死角に注意する
- 麻痺側の手足の保護
一つひとつ意識して、事故を防止していきましょう。
まとめ|運動麻痺の改善には正しい知識と継続がカギ

運動麻痺とは、手や足がうまく動かなくなる状態のことです。これは、脳卒中などの病気で脳や神経がダメージを受け、体に「動け」という命令がうまく届かなくなることが原因です。
でも、ここで希望を持ってほしいのは、人の脳には「可塑性(かそせい)」という力があることです。これは、傷ついた部分の代わりをほかの場所が助けてくれる仕組みです。この働きのおかげで、リハビリをしっかり続ければ、少しずつ動きが戻ることが期待できます。
運動麻痺をよくするためには、なるべく早い時期からリハビリを始めることがとても大切です。そして、状態に合った運動を毎日コツコツ続けることが回復のカギになります。
病院や施設で行う専門的なリハビリだけでなく、自宅でできる簡単な運動や、日常の動きを意識して行うことも大事です。たとえば、「立ち上がる」「手を動かす」「座ったまま足を動かす」など、小さな積み重ねが回復につながります。
それと同じくらい大切なのが、気持ちのケアです。リハビリは、すぐに成果が見えるわけではないので、時には不安になったり落ち込んだりすることもあるかもしれません。だからこそ、「少しずつで大丈夫」「今できることから始めよう」という気持ちで続けることが大切です。
また、目標をはっきり決めることもポイントです。いきなり大きなことを目指すのではなく、「今日は5回イスから立つ」「手を10回上げる」など、実現できる小さな目標を立てて、毎日すこしずつ前に進みましょう。
リハビリ中は、転ばないようにまわりの安全にも気をつけることが必要です。無理をせず、でもあきらめずに続けることが、運動麻痺の改善につながる一番の近道になります。










