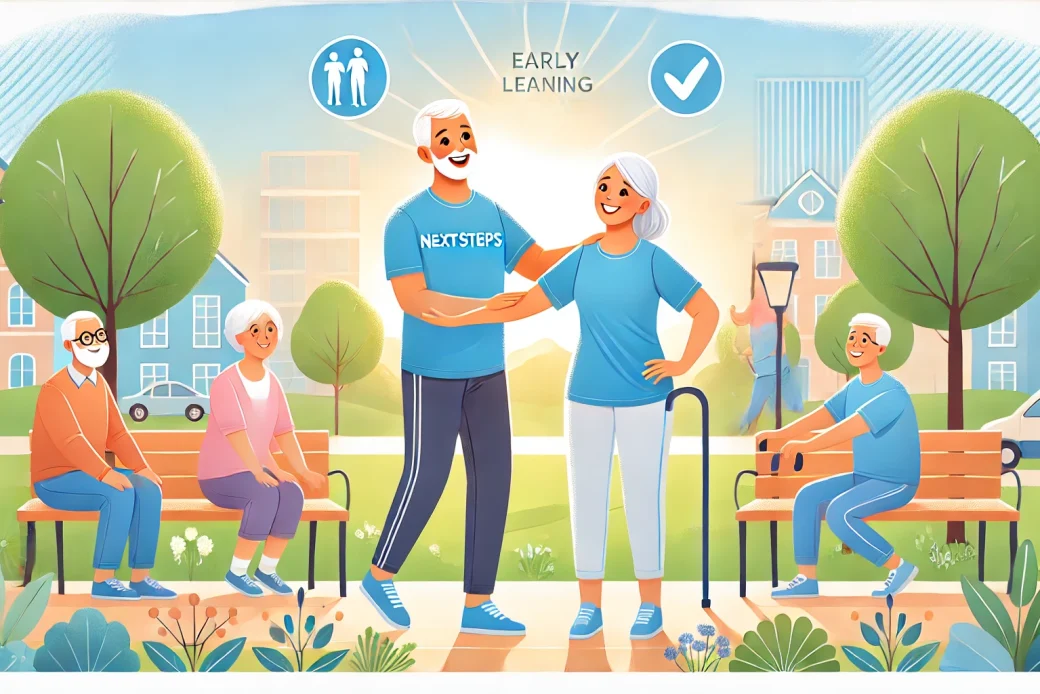「最近歩きにくそう…」は危険信号。訪問リハのプロが教える高齢者の筋力低下対策
2025.01.27

「最近、立ち上がる時に机に手をつくようになった」 「歩くスピードが落ちて、信号を渡りきるのがギリギリ……」
ご家族のそんな姿を見て、不安を感じていませんか? 筋力が落ちていくのは、年齢のせいだけではありません。実は、日々のちょっとした「動きのコツ」や「食事の選び方」を知っているかどうかで、その後の生活は大きく変わります。
私たちは日々、訪問リハビリの現場で多くの高齢者の方やそのご家族と向き合っています。そこでよく耳にするのが、「もっと早く対策を知っていればよかった」という言葉です。
この記事では、難しい医学用語は横に置いておいて、「今日から家で、無理なく、安全にできること」だけを、リハビリのプロの視点でまとめました。
大切なのは、特別なトレーニングマシンではなく、今ある暮らしの中での工夫です。
目次
高齢者と筋力の関係性|「つまずきやすくなった」は危険の合図

高齢者筋力低下は、加齢により誰もが起こる生理現象です。まずは加齢による筋力低下の原因と、早急に対処すべき症状についてみていきましょう。
【30秒チェック】あなたの筋肉は大丈夫?「指輪っかテスト」
自分の両手を使って、今すぐ「ふくらはぎ」の太さを測ってみましょう。
- 指で輪を作る:両手の親指と人差し指を合わせて輪っかを作ります。
- ふくらはぎを囲む:椅子に座り、利き足ではない方のふくらはぎの一番太い部分を、力を入れずに囲みます。
判定結果
- 【囲めない】:筋肉量が維持されており、健康な状態です。
- 【ちょうど囲める】:サルコペニア予備軍です。対策を始めましょう。
- 【隙間ができる】:サルコペニア(筋力低下)の可能性が非常に高いです。
※東京大学の飯島勝矢教授らが提唱したチェック法で、隙間ができる人はできない人に比べて、将来の要介護リスクが約6.6倍になるというデータもあります。
【30秒で確認】筋力低下のサイン・セルフチェック表
以下の項目に1つでも当てはまる場合、早期の対策が必要です。
| チェック項目 | 日常生活での具体例 |
| 歩行速度 | 横断歩道を青信号のうちに渡りきれない |
| 立ち上がり | 手すりや机を使わないと椅子から立ち上がれない |
| 握力・腕力 | ペットボトルの蓋が開けにくくなった、重い買い物が辛い |
| 段差 | 何もない平らな場所でつまずくことがある |
| 外出頻度 | 以前に比べて外出するのが億劫になった |
筋力や身体機能の低下に関する主な原因
高齢者筋力低下の主な原因として、以下の3つが挙げられます。
- 加齢によるもの
筋肉量の低下は25〜30歳くらいから始まり、その後も徐々に低下していきます。また筋線維の減少や萎縮といった変化もみられ、筋力やバランス力なども低下します。
- 運動不足によるもの
筋肉は活動により強化されるものです。加齢による活動量の減少や長期間の安静は、廃用性筋萎縮の原因となり、筋力を低下させます。
- 栄養不足によるもの
高齢者は、咀嚼・嚥下機能の低下や食欲の減退により低栄養になりやすい傾向があります。低栄養状態では必要なエネルギーやタンパク質が不足し、筋力の維持が困難になります。
こんな症状があったらすぐに対処しよう
筋力低下により現れる症状をご紹介します。
- 歩行時につまずきやすくなった
- 立ち上がり時、何かにつかまったり支えが必要
- これまでに比べ疲れやすくなった
- 青信号で横断歩道を渡れないなど歩行速度の低下
- 階段の上り下りが辛く、手すりが必要
- ふらつきやすくなった
症状が現れたら早めの対処が必要です。特に、症状が急速に現れたり進行する場合、早急に医療機関に相談しましょう。
【高齢者筋力低下】3つのリスクは要介護となる可能性も…?

筋力の低下は、対処が遅れるとどんどん進行し、最終的には要介護となる可能性もあります。高齢者筋力低下による3つのリスクをみていきましょう。
①高齢者筋力低下はサルコペニアを発症するケースも
加齢に伴う筋力低下は自然な生理現象です。一方、サルコペニアは、日常生活機能が著しく低下するほどの筋力低下がみられる状態を指します。
筋力低下は、徐々に進行していきます。歩行時に何度もつまずく、手をつかなければ立ち上がりができない、などの症状を放置すると症状はさらに進行し、サルコペニアを発症することも。深刻な場合は寝たきりになるケースもあるため、見過ごしてはいけません。
②転倒による怪我や骨折のリスク増加
加齢による筋力やバランス能力の低下によって、転倒のリスクが高まります。転倒による骨折や頭部外傷等をきっかけに、要介護となるケースもあるため注意が必要です。
高齢になると怪我の回復に時間がかかります。長期間の安静は筋力の低下を招くため、そのまま寝たきりへ移行するケースも少なくありません。特に骨折は注意が必要です。高齢者は骨密度の低下により骨折を起こしやすいため、転倒予防は重要な課題の一つです。
③高齢者筋力低下はフレイルサイクルへの突入のきっかけ
フレイルとは、加齢に伴い身体的、精神的、社会的機能が低下し、心身の健康を害しやすくなった状態を指します。フレイルの要因には低栄養やサルコペニアなどが含まれ、これらの要因が互いに影響し合うことで起こる負の連鎖をフレイルサイクルと言います。
例えば、筋力の低下により活動量が減る→食欲が減る→食事量が減り栄養不足になる→更に筋力が低下する、といった流れは高齢者に起こりやすいフレイルサイクルです。
フレイルサイクルが進行すると、要介護リスクは非常に高まります。筋力の低下によってフレイルサイクルに入るのを防ぐため、早期から適切な対処をとることが重要です。
参考:厚生労働省「高齢者」
政府広報オンライン「たった一度の転倒で寝たきりになることも。転倒事故の起こりやすい箇所は?」
高齢者筋力低下|予防と対処法について…運動療法だけが全てではない理由

筋力低下への対処として、運動やリハビリを思い浮かべる方が多いでしょう。しかし、高齢者筋力低下は様々な要因が影響し合っているため、いくつかの治療を組み合わせる必要があります。詳しくみていきましょう。
高齢者筋力低下は運動療法だけでは解決できない
高齢者筋力低下は、加齢や活動不足、栄養不足など複数の原因が影響し合う場合が多く、個々の状況に応じて多方面からアプローチする必要があります。
有効な予防・治療は、運動療法と栄養療法です。運動療法では、筋力アップや日常動作の維持・改善が期待できます。また栄養療法により、必要な栄養を十分摂取することで、筋力の低下を防ぐことが期待できます。
症状が進行してからではなく、自分の体の変化に気づいた段階で予防的に取り組むことが大切です。
【高齢者筋力低下】に対する予防法
筋力低下を予防する方法をみていきましょう。
- 運動習慣をつける
| 運動名 | 目標回数 | 意識するポイント |
| 椅子スクワット | 10回×3セット | 椅子に座る寸前で3秒止まる。手すりを持ってもOK。 |
| かかと上げ | 20回 | 台所仕事の合間に。ふくらはぎをしっかり収縮させる。 |
| 片足立ち | 左右30秒ずつ | 必ずテーブルなどを支えにして、転倒に注意する。 |
プロのアドバイス: 「毎日やろう」とすると挫折します。まずは「月・水・金」など、1日おきの実施が筋肉の回復(超回復)に効果的です。
適切な運動習慣により、全身の筋力をつけましょう。特にウォーキングや水泳などの有酸素運動や筋肉に負荷をかけるレジスタンス運動が有効です。できれば週に2〜3回行うことが望ましいですが、無理なく継続できることが最も重要です。
- タンパク質を摂る<1日に必要なタンパク質量は「手のひら3枚分」>
「タンパク質を摂ってください」と言われても、何g食べればいいかピンとこない方が多いはずです。現場では「毎食、手のひら1枚分のタンパク質を摂る」ことを推奨しています。
★1食の目安: 肉、魚、卵、大豆製品などのメインおかずが「自分の指を含まない手のひら」に乗るサイズ。
※高齢者の注意点: 若い頃と同じ量では足りません。加齢とともに吸収率が落ちるため、意識的に「プラス1品(納豆1パックや卵1個)」を足すのが正解です。
- 積極的に外出し人と交流する
外出することにより活動量が増える他、人との交流による精神面での安定も得られます。適度な活動や人との交流は食欲増進につながり、栄養状態の維持や改善が期待できます。
家族や周囲の人も予防の声かけを
高齢者筋力低下に対する治療や予防には、運動や食事など様々なアプローチが必要です。しかしそれら全てを一人で行うには限界があります。周囲の人が一緒に運動を楽しんだり、調理の工夫をこらしてあげることも、治療や予防の継続のためにはとても重要です。
また、普段から本人の様子をよく見守り、歩行や立ち上がりの様子などに変化を感じたら、早急に専門医に相談しましょう。専門医に現状を把握してもらい、症状に応じた治療法を選択する必要があります。
高齢者の筋力低下に関するよくある質問

Q. 筋トレは何歳から始めても効果がありますか?
A. はい、90代から始めても筋肉の細胞は発達することが研究で証明されています。「もう遅い」ということはありません。
Q. ウォーキングだけではダメですか?
A. 歩くだけでは、階段を上るのに必要な「瞬発的な力」は鍛えにくいです。上記のスクワットなど、少し負荷のかかる運動を組み合わせるのがベストです。
Q. 膝や腰が痛くても運動すべきですか?
A. 痛みを我慢しての運動は逆効果です。まずは痛みの原因を専門家に相談し、関節に負担をかけない「座ったままできる運動」からスタートしましょう。
まとめ|筋肉は「何歳からでも」増やせます

「もう年だから、足が弱くなるのは仕方ない」というのは大きな間違いです。リハビリの現場では、90代の方でも適切な負荷と栄養で、歩行が安定するケースを数多く見てきました。
まずは、理屈よりも以下の3つのアクションを今日から始めてください。
- 「指輪っかテスト」で現実を見る 自分の指でふくらはぎを囲み、隙間ができたら「イエローカード」です。今の筋肉量では、近い将来、転倒・骨折するリスクが高いと自覚してください。
- 「タンパク質ファースト」の食事 運動以前に、筋肉の材料が足りていません。毎食「手のひら1枚分」の肉・魚・卵・豆腐を絶対に抜かないでください。
- 「1日3回のスクワット」から いきなり散歩に出る必要はありません。まずは手すりに捕まっていいので、椅子からゆっくり立ち上がる練習を3回だけ。そこが自立した生活を守る境界線になります。
私たちが一番避けたいのは、「あの時やっておけば、車椅子にならずに済んだのに」という後悔です。 自分の力でトイレに行ける、外に出られる。その自由を1日でも長く守るために、私たちプロの知識を使い倒してください。