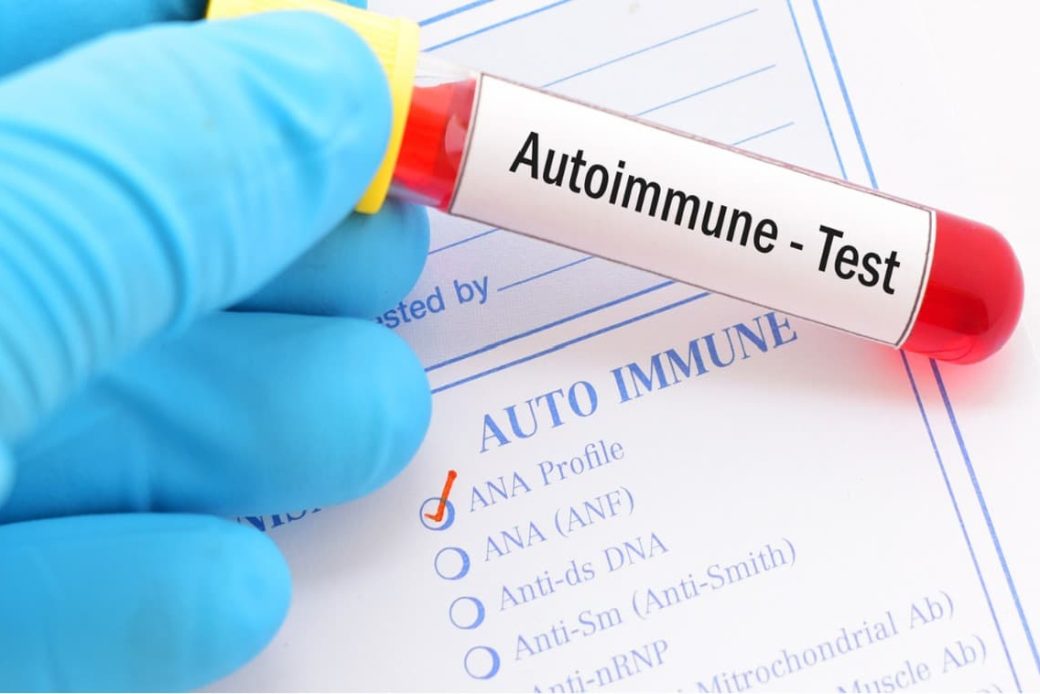肘リハビリの正しい進め方|確実に治す3ステップと完治までの目安を解説
2025.09.26

肘を骨折したとき「どのくらいの期間で治るのか」「元通りに動かせるようになるのか」不安に感じる方は多いです。肘は、日常生活で頻繁に使う部位です。完治までに時間がかかったり後遺症が残ったりすると、普段の生活に大きな支障をきたします。
肘の骨折を乗り越えて元の生活にスムーズに戻るため、重要なカギとなるのがリハビリです。リハビリの内容や進め方によって、治るスピードや生活のしやすさが大きく変わることも珍しくありません。
今回は、肘の骨折に関する情報や肘リハビリを効果的に進める方法を解説します。基本情報を把握し、肘の骨折からの着実な回復を目指しましょう。
目次
肘リハビリの前に知っておきたい!肘の骨折に関する基本情報
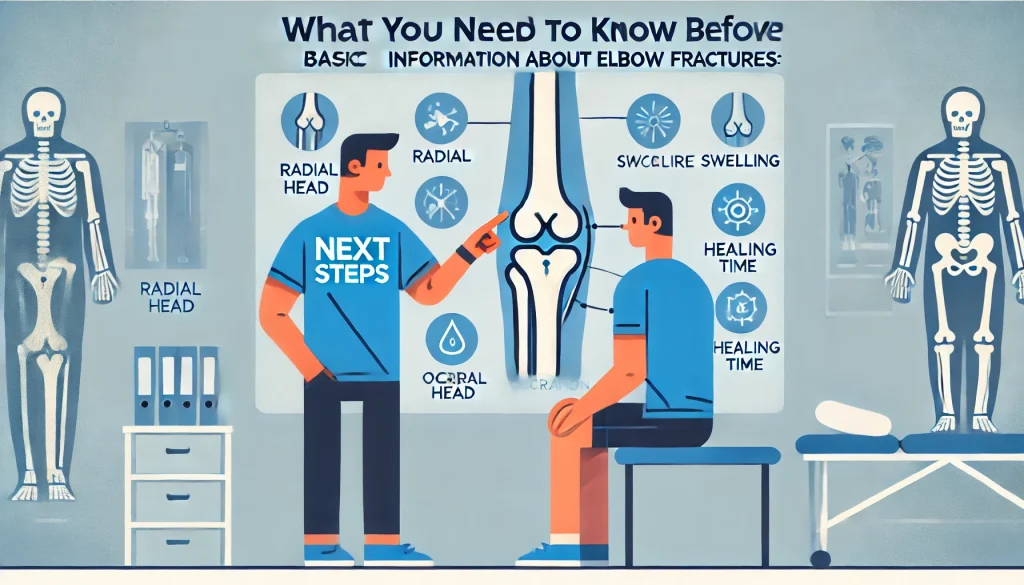
肘の骨折を正しく治療しなかった場合、関節の可動域が狭くなるなどの後遺症が残るリスクがあります。目標をもち前向きな気持ちで肘リハビリに取り組めるよう、完治までの目安や肘の骨折に関する基本情報を把握しましょう。
どんな種類がある?肘の骨折の種類3つ
ひと言で肘の骨折と言っても、大きく以下の3種類があります。
| 種類 | 特徴 |
| 上腕骨遠位端骨折 | 肘に近い上腕の先端が折れる骨折 転倒時に手をついた際に起こりやすく、関節の可動域に影響が出る場合もある。 |
| 橈骨頭骨折 | 肘の外側にある橈骨の先端が折れる骨折 手をついたときの衝撃で生じ、腕を回す動作に支障をきたす場合がある。 |
| 肘頭骨折 | 肘のとがった部分(肘頭)が折れる骨折 強く肘を打った際に発症するケースが多く、肘の曲げ伸ばしに影響する。 |
骨折の種類によって影響する動作や治療内容が異なるため、症状に応じた対応が必要です。
どう治療する?保存療法と手術の違い
肘を骨折した場合の治療法としては、大きく2種類があります。
1つ目は「保存的治療」です。比較的軽度の骨折の場合に用いられ、ギプスやスプリントを使い患部を固定して骨の回復を促します。定期的にX線撮影を行い、骨の位置がずれていないかをチェックしながら治療を進める方法です。
2つ目は外科的治療である「手術」で、骨折により骨が大きくずれている場合や、骨片が皮膚から飛び出しているケースに用いられます。
多くの場合は保存的療法が選ばれますが、いずれの方法も専門医の診断が欠かせません。必ず整形外科を受診し、医師の指導のもとで治療を進めましょう。
肘の骨折はいつ治る?完治までの目安
肘の骨折が治るまでの期間は骨折の種類や重症度によって異なりますが、骨が回復しギプスなどの固定が外れるまでの期間は3~6週間が目安です。その後リハビリを始め、動きの回復までにかかる期間は、3~4カ月とされます。
ただし、骨が大きくズレている場合や合併症などがあれば、1年以上かかるケースも少なくありません。焦って早く治そうとせず、長期目線でじっくり治療に取り組む姿勢が必要です。
気を付けたい肘の骨折の後遺症とは
肘の骨折に正しく対処しなかった場合、以下のような後遺症が残るおそれがあります。
| 症状 | 特徴 |
| 肘がかたくなる | 肘が伸びない・曲がらない状態になり、日常生活に支障をきたす |
| 軟骨がすり減る | 骨折後の負担や変形が原因で関節の軟骨が摩耗し、痛みや可動域の制限につながるケースも |
肘の骨折は治療に長い時間がかかる場合もありますが、じっくりリハビリに取り組めば後遺症を防ぎ骨折前の生活に近づけることが可能です。主治医やリハビリ担当者の指導のもと、根気強くリハビリに取り組んでいきましょう。
もう悩まない!確実に回復する肘リハビリの進め方3ステップ
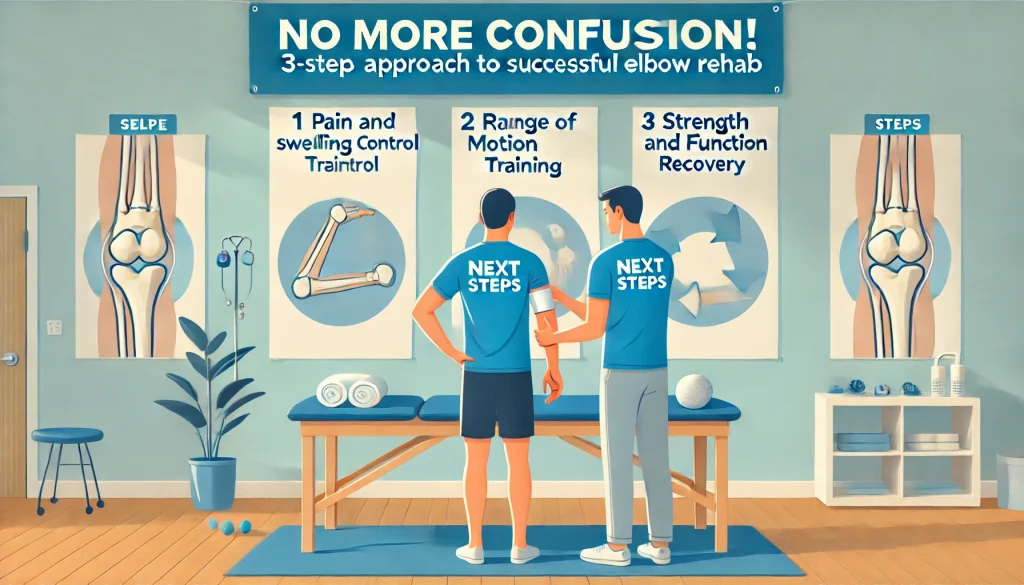
骨折後の後遺症を防ぎ日常生活をストレスなく送るには、肘リハビリが不可欠です。しかし、正しい順序で行わなければ十分な効果が得られない可能性があるため、注意しましょう。ここでは、肘リハビリの正しい進め方を3ステップで解説します。
負担の少ないマッサージから徐々に慣らす
骨折後は、一定期間肘を固定しておかなければなりませんが、その間に筋力や関節がかたくなり、可動域が狭くなります。筋力も低下するため、無理に動かしたり重いものを持ったりすると、新たなケガにつながるかもしれません。
リハビリの初期段階では、肘の可動域を少しずつ広げていくことが大切です。まずはマッサージで肘の筋肉や関節をほぐし、本格的なリハビリに向けて体を慣らしていきましょう。
次は筋力・柔軟性を強化するリハビリへ
肘の可動域が広がってきたら、次のステップとして、筋力や柔軟性を高める運動を取り入れていきます。
たとえば、やわらかいボールを握ったり軽めのダンベルを使った運動は、自宅でも手軽に取り組むことが可能です。テーブルの上に腕を置き、ゆっくりと肘を曲げ伸ばしするだけでも、十分な肘リハビリになります。
また、リハビリの効果を高めるには、関節や筋肉を温めてほぐすことも重要です。入浴時には10~15分ほど湯船につかり、しっかり温めたうえでリハビリを行うのも良いでしょう。
仕上げは再発予防!肘を守る筋トレ法
リハビリが進み筋力や柔軟性がある程度戻ってきたら、仕上げとして再発を防ぐ筋トレを取り入れていきます。
たとえば、ゴムバンドを使った軽い負荷のトレーニングや、軽いダンベルなどを使った運動が効果的です。こうしたトレーニングを取り入れれば肘周りの筋力が強化され、再発リスクを軽減できます。
ただし、自己判断でのトレーニングは再発のリスクを高める可能性があるため、医師や担当の理学療法士の指導のもとで行うようにしましょう。
肘リハビリで失敗しないために!知っておきたいポイント

肘の骨折後は肘リハビリが必要ですが、やり方を間違えると痛みが長引いたり可動域が戻らなかったりして、逆効果になるケースも考えられます。しっかりと肘の機能を回復させられるよう、リハビリ成功のコツを押さえましょう。
無理のないペースで取り組む
肘リハビリに多く取り組んだからといって、早く治るわけではありません。やりすぎは再発や新しいケガを引き起こす原因にもなり得ます。
骨折は短期間で治るケガではなく、リハビリが終わるまでに1年以上かかるケースも少なくありません。リハビリメニューを決める際は、毎日無理なく続けられるメニューになっているか、十分に検討することが大切です。長期目線で、じっくりとリハビリに取り組んでいきましょう。
骨折のリスクを減らす環境を整える
せっかくリハビリを進めても、骨折しやすい環境のままで生活をしていれば、再び肘を痛めてしまうかもしれません。
たとえば、骨密度の低下は骨折のリスクを高め、回復を妨げる要因となります。カルシウムやビタミンDといった、骨の健康を支える栄養素を意識して取り入れることが大切です。
また、転倒を防ぐ環境作りも欠かせません。階段に手すりをつける、吸盤付きのマットを使うなどして、安心して過ごせる環境を整えましょう。
まとめ|諦めずに肘リハビリに取り組んで着実に回復を目指そう!

肘を骨折したときには、機能を取り戻すためのリハビリがとても大切です。骨がくっつくだけでは不十分で、正しいリハビリを怠ると回復が遅れるだけでなく、関節が固まってしまうなどの後遺症が残る可能性もあります。
肘の骨折は、他の部位に比べても治るまでに長い時間がかかるケースが多いといわれています。そのため、焦らずに長期的な計画を立ててリハビリに取り組むことが必要です。最初は小さな動きから始め、少しずつ可動域を広げていくのがポイントになります。
また、リハビリは病院で行うだけでなく、毎日コツコツと自宅で続けられるメニューを取り入れることも大切です。無理をせず、自分のペースで続けることで、肘の機能をしっかり回復させることにつながります。