
在宅復帰を目指すためのリハビリ計画とは?退院後も安心して暮らすために
2025.06.06

入院をすると、退院のためにリハビリが必要となることがあります。怪我や症状を考慮し、どのようにして在宅復帰を目指すのか決めるために、リハビリの計画が必要です。
現状の能力や目標となる能力はどの程度なのか、退院後にどのような生活を目指すのか、などを検討するものです。さらに、生活に必要なサービスや支援の検討も行います。
この記事では、リハビリ計画の立て方や重要性、退院後の家での過ごし方とモチベーション維持について解説します。退院後も安心して暮らすために、在宅復帰に向けたリハビリの重要性を理解しておきましょう。
目次
在宅復帰に向けたリハビリ計画|在宅生活の難しさと計画の重要性

在宅復帰は嬉しい反面、環境が変化するため、不安にかられる方は少なくありません。医師や看護師、リハビリスタッフなどがチームを組み、在宅復帰の支援が行えるようにリハビリの計画を立てることが必要です。
なぜ在宅復帰にリハビリの計画が必要なのか
病院ではベッドや手すり、介助者のサポートなど安全に配慮された環境で過ごせますが、自宅はそうはいきません。日本の住宅は段差が多く、靴を脱ぐ生活様式や浴槽での入浴習慣もあり、高齢者や病後の身体にはハードルが高いことが多いです。
治療を終えて体力が回復しただけで退院するのではなく、自宅でどう生活するかを見据えるために、リハビリ計画を立てる必要があります。
厚生労働省も、高齢者が住み慣れた地域や自宅で人生の最後まで過ごせるよう、医療や介護、生活支援などを一体的に提供する『地域包括ケアシステム』を推進しています。リハビリ計画はその一部を担うもので、在宅復帰に向けた準備が、安心と生活の質の向上にもつながるでしょう。
病院と在宅生活のギャップに潜むリスク
病院生活と自宅生活の間には、環境・サポート体制・心身の状態変化で大きなギャップがあり、このギャップを埋めずに退院すると様々なリスクが現れます。
まず、環境の違いによるリスクです。病院では平坦で安全な環境ですが、自宅は玄関の上がりかまちや浴室の段差、狭いトイレなど危険な箇所が多くあります。退院直後は、慎重に動いていても自信が出て油断した頃に転倒し、再入院というケースも少なくありません。
次に、サポート体制の違いです。病院では24時間医師や看護師がいますが、自宅では必要な時にすぐ駆けつけることができません。服薬管理や食事管理などを自分で行いながら、塩分が多すぎる食事や水分量などにも注意する必要があります。再発予防のための工夫やサポート体制を整えておくことが重要です。
最後は、心身の状態変化です。病院ではリハビリや入浴、消灯時間が決まっていたりと規則正しい生活でしたが、退院後は運動量が減ったり、逆に無理しすぎてしまったりすることがあります。
リハビリ計画がないとどうなる?
リハビリ計画をせずに退院した場合、ギャップによるリスクが現実になります。
- 再入院や在宅生活の挫折
- 機能低下と寝たきり
- 介護者(家族)の負担増大など
計画を立てずに退院すると在宅生活のつまずきを招きますが、しっかりとした計画を立てることで、退院後の課題を把握して対策を立てられます。
在宅復帰までのリハビリの計画はどのように進行する?

「在宅復帰を行うためには、どのようにリハビリの計画を進行していくの?」と悩む方もいるでしょう。
ここでは、リハビリの3つの段階と役割の違いについて整理していきます。また、在宅復帰に向けたリハビリに必要なものと、退院前カンファレンスで確認すべきポイントも確認しておきましょう。
リハビリの3つの段と役割の違い
リハビリテーションは急性期・回復期・生活期の3段階にわかれます。基本的に3段階ですが、その人に合わせたリハビリが重要です。
急性期は発症・手術直後で、治療と並行して筋力低下や拘縮を防ぎつつ、立ち上がる・歩くなどの基本的な動作訓練も早期に取り入れます。
回復期は、リハビリ効果が高く期待できる時期です。集中的なリハビリで心身機能を改善し、退院後の生活を見据えた準備もします。
生活期は、退院後の自宅や施設での生活を支える段階です。継続的に運動能力を高めつつ、その人らしい自立した暮らしを目標に支援します。
在宅復帰に向けたリハビリには何が必要?
在宅復帰を成功させるためのリハビリには、4つの重要なポイントがあります。
- 生活環境の評価と整備
- 日常生活動作(ADL)の練習
- 家族への介助方法の指導
- 退院後のサービス調整
これらを総合的に計画して実行することで、退院後の生活を安心してスタートする土台を築けます。
退院前カンファレンスで確認すべきポイント
退院前カンファレンスは、退院前に病院スタッフと在宅側の担当スタッフ(ケアマネジャーや訪問看護師など)が、退院後の生活について話し合う会議です。カンファレンスでは、主に以下の4点を確認します。
- 現在の健康状態と治療方針
- 医療処置の有無
- 患者さん本人や家族の希望
- 必要性が高いサービスや支援
多職種で話し合うことで、支援内容や役割分担が明確になります。「誰に連絡をすればいいのか」がはっきりすると、本人や家族が退院後の生活を安心して見据えられるでしょう。
【在宅でのケア】退院後は家での過ごし方とモチベーション維持を

在宅復帰は、ゴールではなく新たなスタートです。自宅での生活が始まってからも、リハビリとケアは続きます。在宅復帰に向けてリハビリの計画を立てる際は、住宅改修や福祉用具の活用方法、家族の支え方などの確認が重要です。また、目標を持って生活することの重要性も理解しておきましょう。
住宅改修と福祉用具はいつ・何が必要?
在宅復帰には、住宅改修と福祉用具の活用が重要です。退院前から、手すりの設置や段差解消など、住宅改修の計画をしておくことをおすすめします。
福祉用具はレンタルが基本で、身体状態に応じて調整を行いましょう。杖や歩行器などは、退院前から借りて、リハビリスタッフと調整を行っていくこともあります。
在宅ケアを支える支援サービスと家族の役割
在宅生活を支えるには、介護保険による訪問・通所リハビリ、訪問看護・介護などの公的サービスの活用が大切です。ケアマネジャー支援のもと、本人の状態にあったサービスを調整できます。
家族は大切なパートナーですが、すべてを抱え込まずプロに頼ることが在宅生活を長続きさせるコツです。家族自身の休息や気分転換も重要で、笑顔が本人の意欲にもつながります。困ったときは地域包括支援センターに相談し、地域の支援や情報も活用しましょう。
あなたのしたいことは?目標設定の重要性
在宅復帰後の生活で大切なのは、患者さん本人の『やりたいこと』を中心に目標を立てることです。「孫と遊びたい」「趣味を再開したい」「一人で買い物に行きたい」など人それぞれやりたいことはあります。
支援するスタッフやご家族は応援団です。些細なことでも自分で決めた目標が重要で、必要に応じた見直しも大切になります。
まとめ|在宅復帰のためにはリハビリ計画が成功を導くカギ
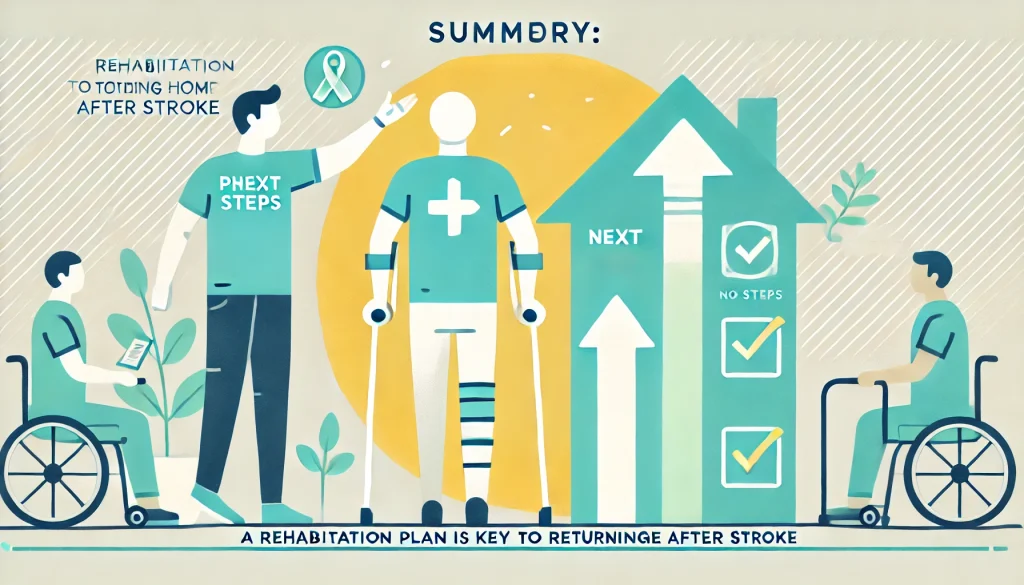
病気やけがで入院した人が、家に戻って生活を始める(在宅復帰)ためには、しっかりとしたリハビリの計画が必要です。病院では医師や看護師、リハビリの先生がいつも近くにいて助けてくれますが、家では環境もサポートの人も限られているため、準備をせずに退院すると大きなリスクが生まれます。
たとえば、家での生活に合った準備ができていないと、転んでけがをしたり、再び入院することになったり、家族が大変な思いをすることもあります。
そのため、退院する前には、医師・看護師・リハビリの先生・ケアマネジャーなど、いろいろな職種の人が集まって「カンファレンス(話し合い)」を行います。ここでは、次のようなことを話し合って、家に帰る準備を進めます。
- 家の中をどう直せば安全に過ごせるか(たとえば手すりの設置など)
- どんなふうに介助すればよいか(手伝い方や声かけの工夫)
- 利用できるサービスの確認(デイサービスや訪問リハビリなど)
家に戻った後も、介護保険を使って福祉用具(歩行器やベッドなど)を借りたり、介護サービスを利用することで、家族の負担を減らしながら本人を支えることができます。
そしてもう一つ大切なのが、本人が「やりたい」と思っていることを大切にして、目標を立てることです。「自分でごはんを食べたい」「買い物に行けるようになりたい」など、そうした思いがあることで、やる気が出て、生活の質もよくなります。
在宅復帰は、ただ家に帰るだけではありません。その人らしく、安心して暮らせるように、チームで準備と家族サポートを続けることがとても大切です。










