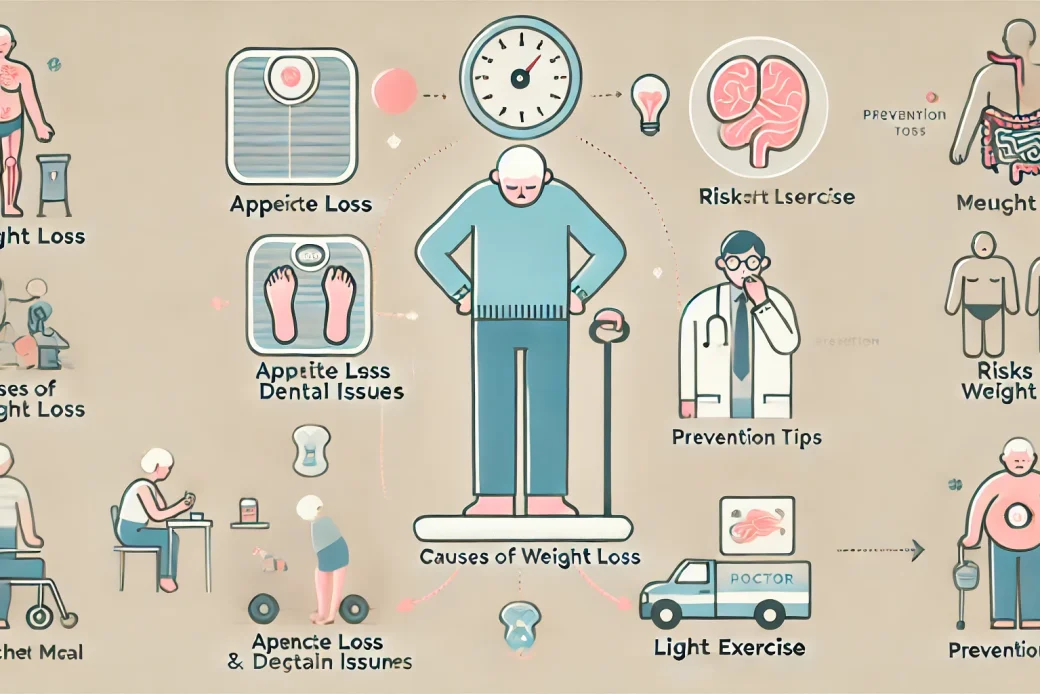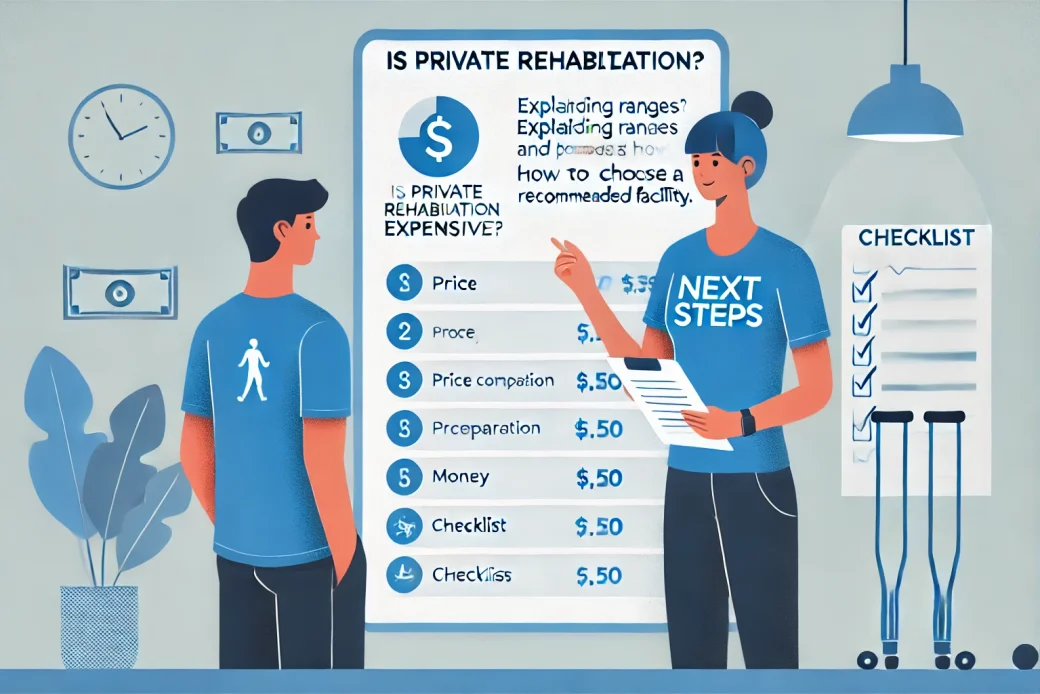リハビリは150日超えたら終了する!?150日ルールの説明と解決策について
2025.01.20
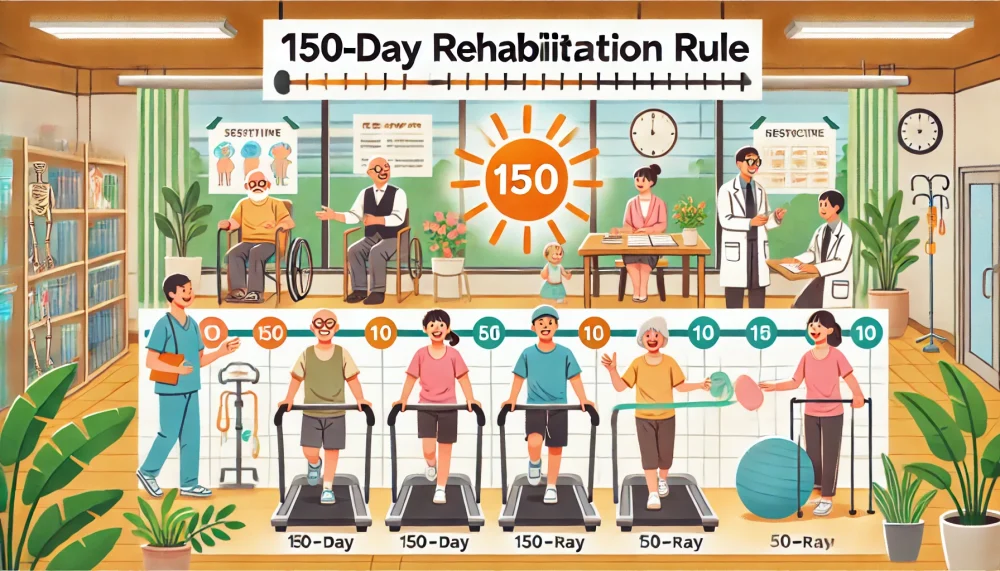
2006年から、運動器疾患のリハビリは、150日を超えたら終了するという流れになりました。
現在リハビリを受けている人は、「期限までに状態がよくなるのか?」「完治しなくてもリハビリは強制的に終了となるのか?」このような不安を抱えている人もいるでしょう。
原則として、運動器疾患のリハビリは150日で終了となりますが、中には終了にならないケースもあります。
仮に症状が残ったままリハビリが終了となっても、リハビリを継続する方法があるので、解決策も踏まえてリハビリのルールについて解説していきます。
目次
なぜリハビリは150日超えたら終了する?標準的算定日数の解説
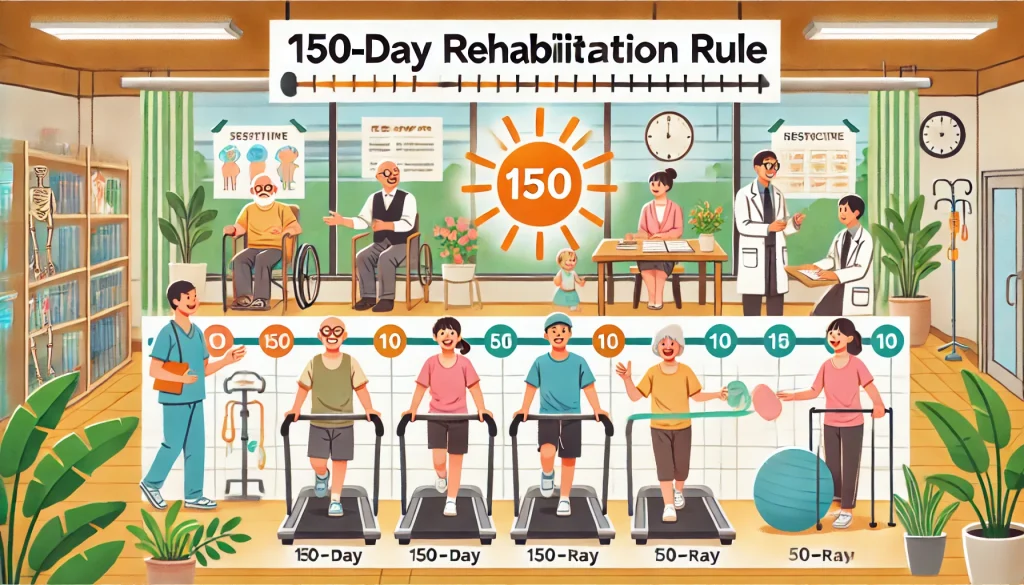
怪我や病気などのリハビリは医療保険が適応となりますが、リハビリできる日数に限りが設けられています。医療保険でリハビリを受けられる期限が過ぎた場合は、リハビリは終了してしまうのでしょうか。リハビリ期限が切れてもリハビリができるケースを解説します。
150日ルールとは?運動器疾患の上限
150日ルールとは、骨折や怪我などが対象になる運動器疾患のリハビリ日数のことです。リハビリが続けられる日数は原因となる疾患名で異なるので注意しましょう。
<疾患別のリハビリ日数>
- 心大血管疾患(150日)
- 脳血管疾患(180日)
- 運動器疾患(150日)
- 呼吸器疾患(90日)
ひと口にリハビリと言っても、疾患毎にリハビリの上限日数が違います。脳卒中など、脳の病気は180日間リハビリができますので覚えておきましょう。
150日超えてもリハビリはできるのか?
原則として、運動器疾患のリハビリは150日超えれば終了となりますが、以下のように例外となるケースもあります。
<標準的算定日数上限の除外対象患者の例>
・高次脳機能障害の患者(失語症、失認症など)
・重度の頚髄損傷患者
・頭部外傷及び多部位外傷の患者
・慢性閉塞性肺疾患の患者
・心筋梗塞の患者
・狭心症の患者
・その他、医師が必要と判断したケース
大事なことは「医師がリハビリを必要と判断する事」です。リハビリは医師の指示の元で行われる行為ですので、医師が継続の必要があると判断すれば、続けてリハビリを受けられます。
労災のリハビリの期限は?医療保険と異なる⁉
医療保険のリハビリは日数に期限がありますが、労災保険制度が適応となっている人には当てはまりません。医師が必要と判断すれば、期間を気にせずにリハビリができるのです。リハビリの継続希望があれば、主治医に相談して、必要性を判断してもらいましょう。
リハビリが終了する前に意識すべきこと!150日前に治す努力も必要
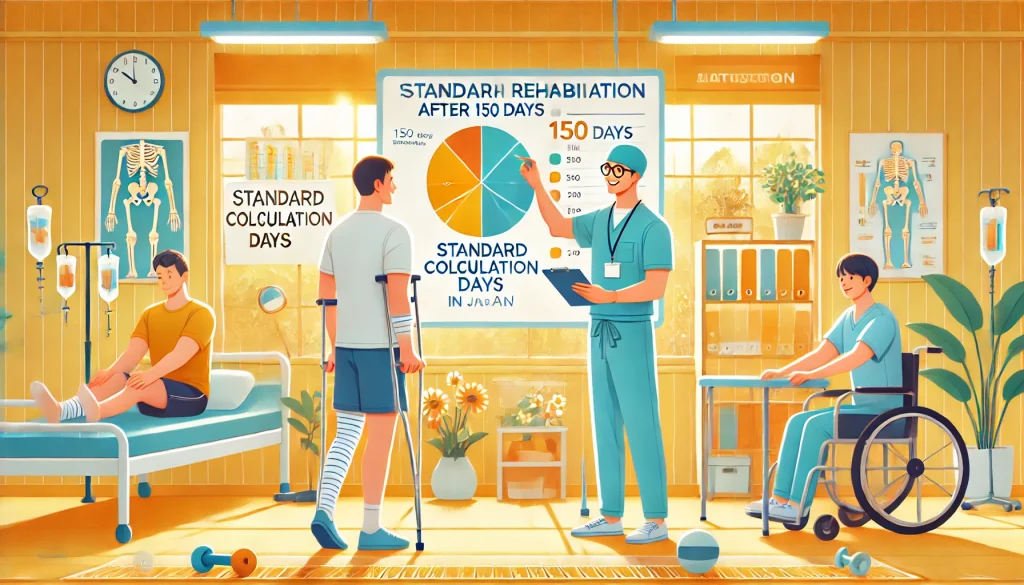
誰もがリハビリの期限切れが近くなれば心配になると思いますが、150日超える前に状態を改善させる意識も必要です。
リハビリの専門家に任せきりで、自分で努力しなければ、リハビリの効果も薄くなりますし、状態が改善しないまま期限切れになることも考えられます。
リハビリ通院中に自分でも意識するべき点について解説します。
期限内になるべくリハビリに通う
リハビリが始まったら病院が決める範囲内で、できるだけ積極的に通いましょう。週に2〜3回の頻度でリハビリを行うと、効果が高いといわれています。
また、リハビリは病気や怪我が発症してからすぐに行うと回復効果が高いです。150日を超えてもリハビリを継続できる方もいらっしゃいますが、処方されてすぐに高頻度で通うのが、症状回復の鍵となります。
自主トレでリハビリの効果を最大限に
リハビリの効果を最大限に発揮するためには、自主トレが重要です。週2〜3回のリハビリに加えて自主トレも行えば、筋力や柔軟性が改善し、痛みも軽くなります。
リハビリの現場では、自宅で行える運動も積極的に指導しています。まだ教えてもらってないという人は、担当のセラピストに自主トレ方法を聞いてみましょう。
生活習慣も見直して再発予防
リハビリが150日超える前に、生活習慣を見直す努力が必要です。身体の状態を改善するためには基盤となる生活習慣を整えましょう。
生活習慣を見直すことで、リハビリの効果も高くなります。
<正しい生活習慣>
- 1日3食しっかり食べる
- 栄養バランスの良い献立を意識する
- 最低7~8時間の睡眠をとる
- 適度な運動を心がける
- 湯船にゆっくり浸かる
- ストレスを貯めないようにする
生活習慣を正すことで、身体や心の不調を改善することができます。リハビリが始まったら、自身の生活習慣も見直すようにしてください。
リハビリ150日超えた人の解決策!介護保険と自費リハビリの選択

リハビリを続けたいけど、150日超えて期限が切れて終了になってしまったという人に、リハビリを継続する方法をお伝えします。医療保険のリハビリの期限がきても、継続してもらえる可能性があるのです。また、医療保険を利用したリハビリ以外の2つの方法を知っていると、選択肢が広がります。
医療保険の期限がきたら主治医に相談する
医療保険でリハビリができる期限がきてしまったり、リハビリ担当スタッフからそろそろ終了する旨を告げられたりしたら、まずは主治医に相談しましょう。
重度の高次脳機能障害や合併症があるなどの除外例にあたる場合は、医療保険を適用したリハビリが継続できるかもしれません。また、医療保険で定められている期限内では症状が改善しないと感じている医師もいるため、症状や回復状況によっては、継続の判断をしてもらえる可能性があります。
現在の状況や日常生活で困っていることや、リハビリの継続希望を主治医に伝えてみましょう。
医療保険のリハビリから介護保険のリハビリへ
主治医に相談しても、医療保険を適用したリハビリを継続できない場合は、介護保険のリハビリを検討します。
介護保険が適用される介護サービスを利用するには介護認定を受ける必要があり、利用できる人が限られるので注意しましょう。
<介護保険を利用できる人>
- 65歳以上で介護サービスが必要になった人
- 40歳以上65歳未満で特定疾病に罹患した人
特定疾病とは、要介護や要支援となる割合が高い病気の事を言います。65歳以上で介護サービスが必要と判断される人や、特定疾病に含まれる人は、医療保険のリハビリ期限が切れても、介護保険のリハビリが適応となるケースがあります。
自費リハビリの選択
現在、自費リハビリ、つまり保険適用外でリハビリを受ける方法もあります。
- 医療保険でのリハビリが終了してしまった
- 介護保険を利用したリハビリが適応とならない
- 現在のリハビリでは回数が足りない
このような方は、自費のリハビリサービスも検討してみましょう。自分の力だけでリハビリを続けるのは、運動が正しいのか不安になりますし、その答えをくれる人もいません。
自費リハビリを利用すれば、身体の調整だけでなく、専門家の目線で運動や生活のアドバイスを受けることもできます。医療保険のリハビリが終了して困っている人は、自費リハビリも選択肢に入れましょう。
参考:厚生労働省「リハビリテーションの標準的算定日数に関する関係団体への聞き取り調査(報告書)」
リハビリテーション150日ルールに関するFAQ

Q1. 運動器リハビリテーションの「150日ルール」とは何ですか?
医療保険(健康保険)を使って運動器疾患のリハビリテーションを受けられる期間に上限を設ける制度です。原則として、発症・手術・急性増悪・初診日のいずれか早い日から150日間が保険適用での算定期間の上限と定められています。
Q2. 150日が経過したら、リハビリは完全に終了しなければならないのでしょうか?
原則として医療保険でのリハビリは終了となりますが、以下のいずれかの方法でリハビリを継続できる可能性があります。
- 例外的な継続(医療保険): 医師が医学的に継続が必要と判断した「除外対象患者」の場合、150日を超えても1ヶ月に13単位(週に2〜3回程度)を限度として医療保険での継続が可能です。
- 介護保険への移行: 介護保険の対象者であれば、介護保険サービスを利用したリハビリに切り替えることができます。
- 自費リハビリ: 全額自己負担となりますが、日数や回数の制限なく集中的にリハビリを継続できます。
Q3. 「除外対象患者」とは、どのような患者が当てはまりますか?
脊髄損傷や重度の頚髄損傷、高次脳機能障害(失語症、失認症など)などの特定の重症例や難病の患者が該当します。これらの患者は、医師が治療継続により状態改善が期待できると判断した場合に、150日を超えても医療保険でのリハビリを継続できます。
Q4. 150日ルールは、すべてのリハビリテーションに適用されますか?
いいえ、運動器リハビリテーションに適用されるルールです。その他のリハビリテーションについては、疾患によって上限日数が異なります(例:脳血管疾患等リハビリは180日、廃用症候群リハビリは120日など)。
Q5. 150日ルールが適用される前に、患者として何を意識すべきですか?
期限内に最大限の効果を出すために、以下の点を意識することが重要です。
- リハビリに高頻度で通う: 特に発症直後は回復効果が高いため、週2〜3回など、できるだけ頻繁に通院することが推奨されます。
- 自宅での自主訓練を行う: 専門家に任せきりにせず、指導された内容を自宅でも継続して実践することが、リハビリ効果を高める鍵となります。
- 生活習慣の見直し: 睡眠や食事などの生活習慣を整えることで、身体の状態が改善し、リハビリの効果も高まります。
まとめ|リハビリは150日超えても選択肢がある

骨折や大きなケガをした時、「さあ、これからリハビリを頑張るぞ!」と思っても、実は医療保険を使って病院やクリニックで受けられるリハビリには、150日間という期限があるんです。簡単に言えば、ケガをしてから150日を過ぎると、原則として健康保険の適用は一旦終了になってしまいます。
「え、じゃあリハビリは終わりなの?」と不安になりますよね。
もし150日経っても、まだ痛みやしびれ、関節の動きにくさなどの後遺症に悩んでいるなら、どうか諦めないでください!
まずは正直に主治医に相談してみましょう。回復が思うように進んでいない場合や、他に治療が必要な症状(合併症)がある場合は、医師が特別に認めることで、健康保険を使ったリハビリを継続できる可能性があります。これは、あなたの体が「まだ治療が必要だ」と判断されたときの、大切な選択肢です。
また、医療保険の期限が来てしまっても、リハビリを続ける方法は他にもちゃんと用意されています。
- 例えば、高齢者や障がいを持つ方向けの介護保険サービス。条件を満たせば、こちらのリハビリに切り替えることができます。
- そして、保険の枠にとらわれず集中的に取り組みたいなら、自費のリハビリサービスも利用できます。費用はかかりますが、自分のペースや希望に合わせたオーダーメイドの質の高いプログラムを選べるのが大きなメリットです。
リハビリ成功の秘訣は「具体的な困りごと」を伝えること
リハビリは、ただ運動するだけではありません。「普段の生活で何が一番つらいか」「どんな動作で困っているか」、この具体的な困りごとを解決するために行うものです。
「階段の上り下りでひざが痛い」「体育で走るのが難しい」など、あなたの学校生活や通勤、日々の生活スタイルに合わせて、困っていることをリハビリの先生や医師にしっかり伝えてみましょう。具体的に伝わるほど、あなたに本当に効果的なリハビリ計画を立ててもらいやすくなりますよ。
自分の体の状態をよく理解し、最適な方法を選んで、日常生活の困り感を少しでも早く解消していきましょう。もし迷ったり、分からないことがあったりしたら、遠慮は不要です。すぐに医師やリハビリの専門家(理学療法士など)に相談するのが、回復への一番の近道です!