
骨折したらリハビリはいつからやるべき?懸念される後遺症とリハビリ期間
2025.03.17
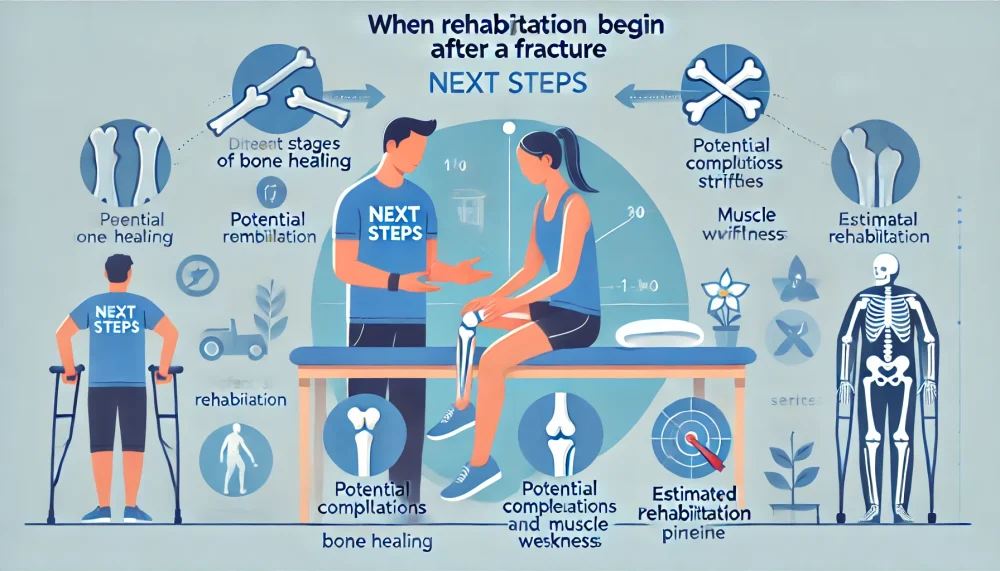
リハビリが必要になる外傷は多いですが、骨折にもリハビリが必要です。近年までは癒合後(骨がくっついた後)からのリハビリとされていましたが、現在は癒合前からリハビリをするのが一般的になっています。
しかし、癒合前からリハビリをすると痛みと伴うことが多々あります。その状況でリハビリをするべきなのでしょうか?また、骨折後にリハビリをしないとどうなるのでしょうか?
今回は、骨折後のリハビリの必要性と後遺症について解説します。また、どれくらいリハビリを続けるべきなのかについてもご紹介します。
目次
癒合すれば終わりではない?骨折にもリハビリが必要な理由

骨折にもリハビリが必要というのは以前よりいわれていました。なぜリハビリが必要なのでしょうか?ここではまず、骨折にもリハビリが必要な理由について解説します。
骨折の治療期間中は筋力低下の傾向に
骨折治療中における最大の懸念は、骨折部位周辺の筋力低下です。治療中は固定を行うため、周辺の筋肉が動かなくなり、拘縮・筋萎縮が起こります。
本来、骨折の治療中は患部に負担をかけないようにするため、固定や荷重軽減の処置を行います。基本的には安静にしなければいけません。そのため、日常動作も制限されます。
また、下半身や脊椎付近の骨折では、治療中寝たきりを余儀なくされます。安静にすべきだからといって寝たきり状態を続けるため、筋力が低下していくのです。
年齢によっては寝たきりリスクが高まるおそれ
骨折した際の年齢によっては、治療後の期間も寝たきりになるリスクが高まるおそれがあります。60代以上の高齢者に多い傾向です。
高齢者の骨折の原因は、骨粗しょう症など骨が弱くなった時に転倒してしまうことで発生します。癒合するまでの期間は数ヶ月間安静にしなければいけません。転倒リスクが若年層より高いからです。
しかし、長期間の安静は筋力低下だけでなく、認知症の発生など寝たきりのリスクが高まるおそれがあります。近年ではリスクを低減するため、手術療法がとられることが多いです。
癒合前からリハビリを行うのが大切
若年層でも高齢者でも、治療期間中に筋力低下のリスクがあります。このリスクをどうやって低減するかというと、骨折の処置後からリハビリを行うのが最適です。
とはいえ、歩くトレーニングなど本格的なリハビリではありません。患部に障らない程度の部位を動かすリハビリが推奨されています。
例えば、肘と手首の真ん中(前腕部)を骨折した場合、指を動かせる場合は日頃から手指を閉じたり開いたりというクセをつけます。また、肘や肩も1日1回動かします。これを癒合前から行うと、可動域制限などの後遺症を軽減することが可能です。
【参考:J-STAGE「骨折に対する効果的なリハビリテーションの展開」】
可動域制限や2次障害など…骨折でリハビリが必要な後遺症とは
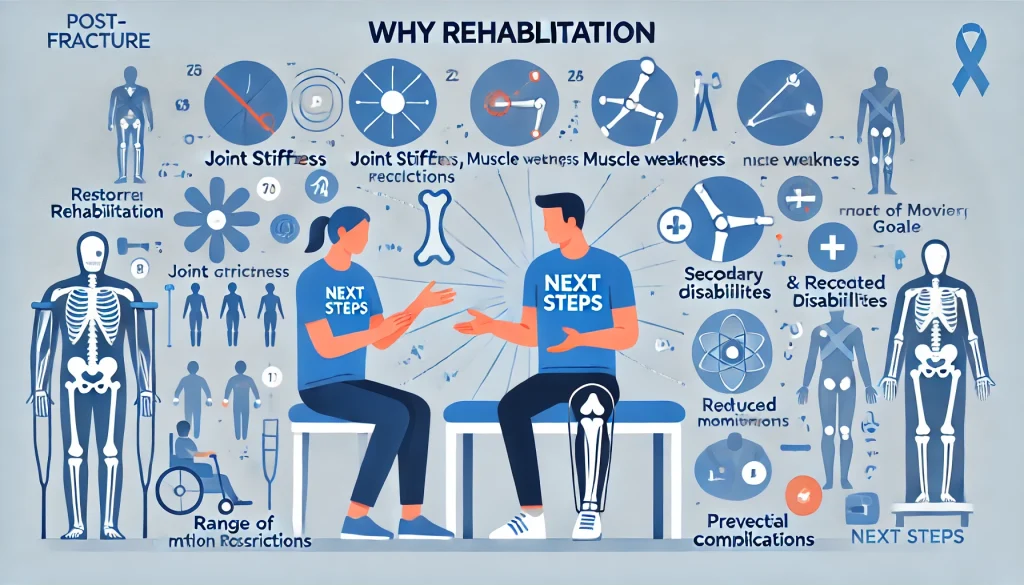
ここでは、骨折した際に起こる可能性がある後遺症について解説します。どの後遺症も、骨折後からのリハビリを行えば軽減が期待できるとされています。
筋肉が硬化することによる関節可動域制限
骨折をすると、患部を固定するのが一般的です。ただ、患部の固定によって関節が動かしづらくなる(もしくは安静にする)ため、関節周囲の軟骨などの軟部組織が少しずつ硬化していくおそれがあります。
軟部組織の硬化が進むと、関節の可動域が狭くなります。これが骨折の後遺症の一つである関節可動域制限です。
また、骨折が外傷性の場合、衝撃によって骨折部分の近くにある関節にも損傷が及ぶこともあります。この関節可動域制限も、後遺症として認定されることがあります。
動かさないことによる筋力低下
骨折時は固定したり安静にしたりといった状態を数ヶ月続けなければいけません。すると固定した患部周囲の筋肉を動かす機会が減るため、少しずつ筋肉は小さくなっていきます。
また、痛みがあるからと日常動作が制限され、普段行う動作が少なくなります。普段使う筋肉も使う機会が減り、全体的な筋力低下のおそれがあるのです。
入院が必要な骨折の場合、最低限の日常動作ができる程度のリハビリを行うことが多いです。しかし、スポーツなどに必要な筋肉は入院中のリハビリでは戻らないため、大抵が退院後のリハビリで取り戻すことが多くなります。
部位によっては運動能力の低下も懸念
骨折した部位によっては、運動能力が低下する可能性があります。特に下半身(脚など)の骨折では注意が必要です。
脚を骨折すると、歩くことが難しくなります。ギプスが取れるまで通常通りに歩行できない状態が数ヶ月続くため、その間に歩行能力が低下してしまうのです。
歩行能力が低下すると、バランス感覚も損なわれ、結果的に全体的な運動能力が落ちてしまう恐れがあります。そのため、下半身の骨折では、歩行トレーニングや、可能な範囲で松葉杖を使わずに歩く練習などのリハビリが行われることが多くあります。
後遺症対策のために…骨折のリハビリはどれくらいから始める?

骨折による後遺症を起こさないためには、リハビリをどれくらいの期間すればよいのでしょうか?ここでは、リハビリを始めるべき時期と続けるべき期間について解説します。
最低でも3ヶ月はかかる見込みをもとう
骨折をした場合、骨が元通りにつながるまで3ヶ月から6ヶ月ほどかかるといわれています。どれくらいの期間になるかは、骨折部位や本人の体力・年齢によって左右されます。
- 炎症期…骨折直後2~3週間。血腫ができて骨折部位が腫れることも。
- 修復期…炎症期から数日後~数週間で移行。骨の修復が始まる。
- リモデリング期…数週間~数ヶ月。本格的に骨が元に戻っていく。
骨折が治るまでは、おおむね上記のような過程を辿るようです。腫れが引いたように見えても骨は修復中。癒合するまでは最低3ヶ月は見たほうが良いでしょう。
基本的には処置後から無理のない軽いリハビリを
近年、骨折のリハビリは癒合する前、早ければ処置後から始めたほうがよいとされています。それは必要以上に安静にすることによる筋力低下や、関節可動域制限を防ぐためです。
ただ、処置直後は血腫ができて腫れていたり、患部周辺まで痛みが及んでいる場合が多いため、リハビリの内容も無理なく軽いものとなります。
意識したいのは患部周囲の関節です。膝、手指、肘、肩周囲の骨を損傷した場合、その近くにある関節は動かす機会が減ってしまいます。少しだけ動かすといった軽いリハビリを毎日続けるだけでも、関節可動域制限のリスクを低減できるでしょう。
骨が癒合し始めたら本格的なリハビリ
骨が癒合し始める修復期に入ると、痛みが少なくなることが多いため、固定処置を継続しつつも本格的なリハビリを始めるケースがよくあります。
ただし、治療期間中は日常動作が制限されることもあるため、全身の筋力が低下するリスクが懸念されます。
そこで、日常動作を少しずつ再開したり、筋力トレーニングなどのリハビリを取り入れていきます。しかし、骨の結合度がまだ十分ではない段階で患部に負荷をかけると、痛みが生じることもあるので注意が必要です。焦らず無理をせず、少しずつリハビリを進めることが大切です。
まとめ|骨折後リハビリの重要性
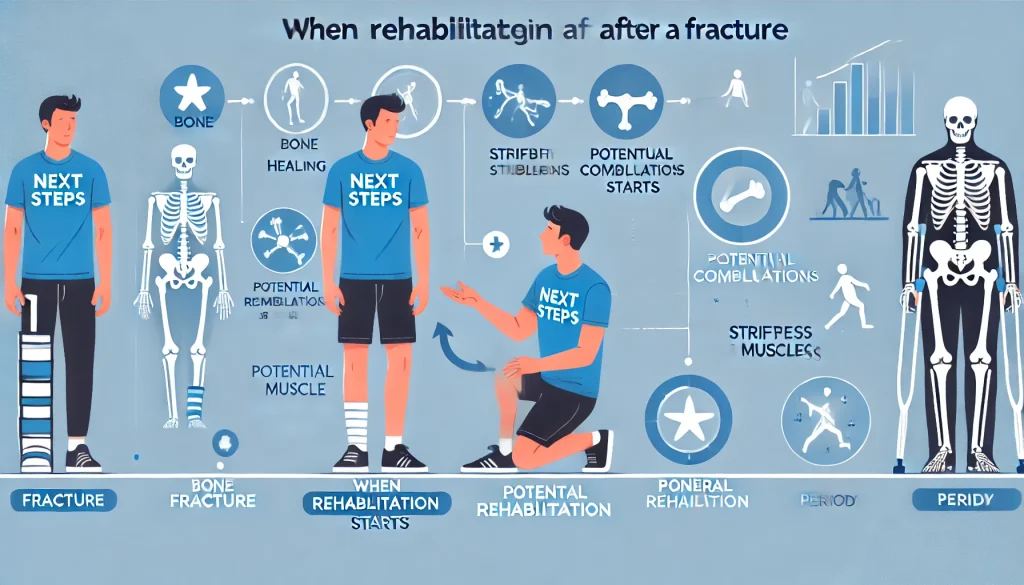
骨折にもリハビリは必要です。骨折は、ただ骨がくっつくのを待つだけではなく、処置後からリハビリを始めることが大切です。なぜなら、ギプスや固定をしている間に関節をほとんど動かさない状態が続くと、関節がかたくなってしまうからです。リハビリを早めに始めることで、関節可動域制限(関節を動かせる範囲が狭くなる症状)などの後遺症を軽減できる可能性があります。
骨折をした後の後遺症を放っておくと、日常生活での動きが制限されることが多く、生活の質であるQOL(Quality of Life)が下がってしまいます。そのうえ、動きが少なくなると、他の病気にかかりやすくなるリスクが高まることも知っておきましょう。
特に、高齢者の場合は認知症や寝たきりのリスクが高まることが指摘されています。歩く機会が減ると、筋力が弱ってしまい、さらに体を動かさなくなるという悪循環に陥りやすいからです。そのため、骨折してすぐの段階からできる限り処置後からリハビリを始め、少しずつ関節を動かしてみたり、無理のない範囲で体を動かすトレーニングを取り入れていくことが大切です。
焦らず、医師やリハビリスタッフの指示をよく聞いて行えば、後遺症や合併症のリスクを抑えながら、日常生活への復帰がスムーズになります。少しでも早い段階からリハビリに取り組んで、元気に動ける体を目指しましょう。









