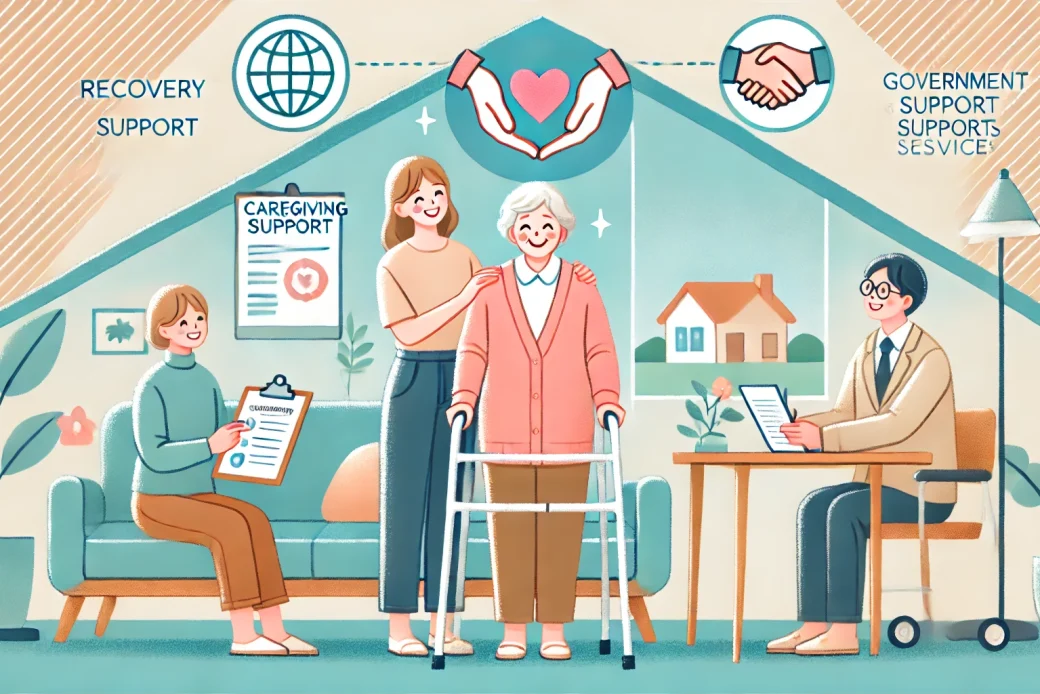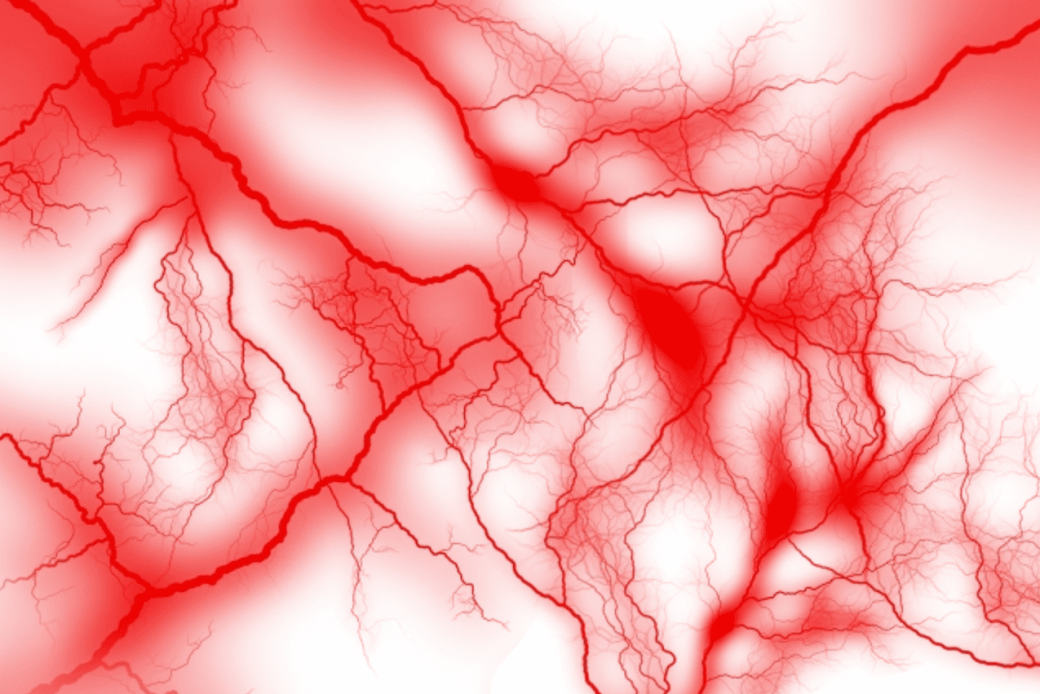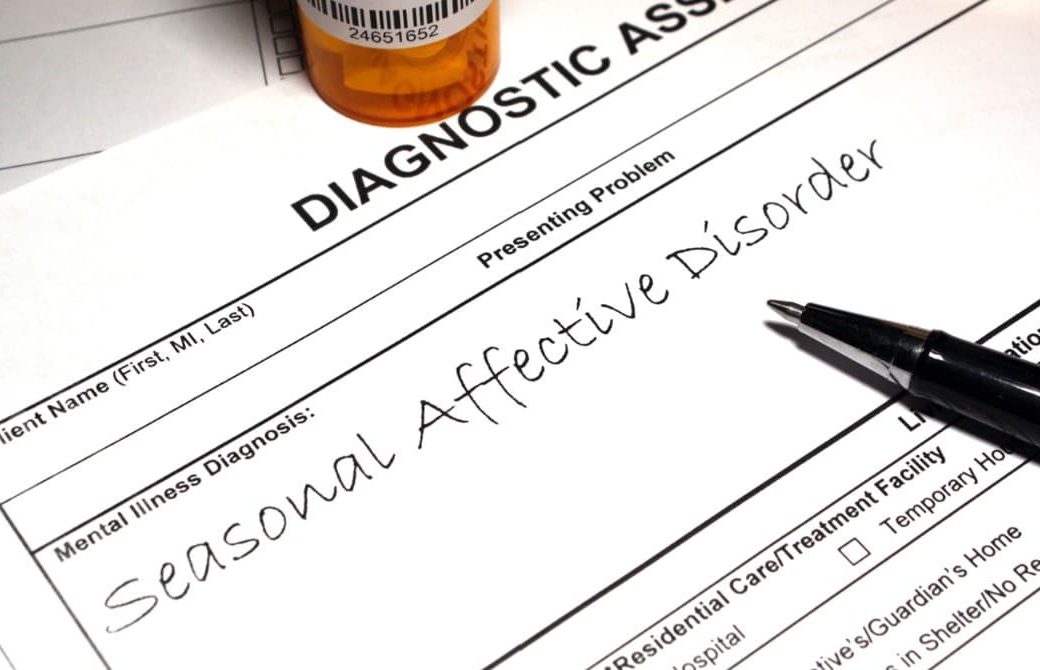神経可塑性とは?脳卒中後の回復を促すリハビリと生活改善のポイント
2025.07.02

脳卒中を発症すると、脳細胞が壊死してさまざまな後遺症が表れます。一度ダメージを受けた脳細胞は回復しないため、後遺症改善には「神経可塑性(しんけいかそせい)」に目を向けたリハビリが重要です。
神経可塑性とは、経験や学習によって脳神経が変化し、新たな運動を獲得する力を指します。「自転車に乗れるようになる」「脳卒中で動かなくなった指が動かせるようになる」など、新たな神経ネットワークの構築が運動に変化をもたらすのです。
神経可塑性は、脳梗塞後遺症を改善して日常生活に復帰するための重要な概念になるため、しっかりと理解を深めましょう。
目次
脳梗塞後の神経可塑性とは?後遺症改善を促す仕組みを解説

脳梗塞後遺症の改善には、神経可塑性が重要です。ダメージを受けた脳細胞の機能を代償するように新たなネットワークを作ることが、後遺症改善につながります。
神経可塑性の概要と重要性を理解しましょう。
神経可塑性とは?概要を解説
「可塑性(かそせい)」とはどのような意味でしょうか?可塑性とは、力を加えて変形させた物質がその形を維持する状態です。可塑性を持つ物質の例を以下にまとめます。
<可塑性を持つ物質>
- 鉄
- プラスチック
- 粘土
神経も可塑性によって新しい神経接続を構成し、その状態が続くことで新しい事を覚えたり新しい運動が可能になったりするのです。
脳損傷後の機能回復
脳卒中の後遺症は、神経可塑性によって改善に期待ができます。例えば、脳卒中後の片麻痺で手足が動かしにくいケースでは、リハビリによって新たな神経ネットワークを構築することで、意識的に動かせるようになる効果に期待ができるのです。
<神経可塑性による機能回復>
- 動かなかった手指が動くようになる
- 歩行機能が向上する
- 認知機能が改善する
脳卒中後は、神経可塑性を意識したリハビリプログラムの実施が重要です。
神経可塑性の重要性について
神経可塑性は、脳卒中に限らず子供の勉強や高齢者の転倒予防にも重要な考えです。もちろん、年齢が若い方が素早く新たな神経ネットワークが作られますが、高齢者になっても神経可塑性による効果は十分あります。
神経可塑性による学習効果や運動の上達は生涯期待できるため、「年だからどうせ意味がない…」と諦めず、継続的にリハビリを行いましょう。
神経可塑性を高めるリハビリ方法は?脳細胞活性化のポイント

脳卒中後のリハビリは、神経可塑性を高めることが重要ですが、やみくもなリハビリではその効果は期待できません。早期の機能改善を目指すためにも、神経可塑性を高めるリハビリ方法と、脳細胞活性化のポイントを抑えておきましょう。
反復練習で脳神経を変化させる
獲得したい運動を反復することで、新たなネットワークが作られて強固になり、神経可塑性を高められます。これにより、脳卒中で動かなくなった手足も、反復したリハビリによって意識的に動かせるようになる効果に期待ができるでしょう。
しかし、反復練習だけでは神経可塑性を高められません。目的意識を持ちながら「自分が何を目標にしているか?」を明確にし、質の高い反復練習を行う必要があります。
個人差を考慮した個別プログラム
リハビリによって身体機能を向上する時は、個人にあったプログラムが重要です。適切な目標を設定し、徐々に難しい課題に挑戦すると効率よく運動を学習できます。また、神経可塑性を高めるためには、難易度や負荷量の調整も大切です。
適切なリハビリを行うなら、専門家に状態を評価してもらい、個別のプログラムを用意してもらいましょう。
心理サポートで患者のメンタルケア
神経可塑性を高めて脳卒中後遺症を改善するには、メンタルケアも欠かせません。脳卒中のリハビリでは、失敗やエラーを気にしすぎる必要はなく、ポジティブな気持ちが運動効果を最大限に引き出します。
また、メンタルケアによるモチベーションの維持も重要です。進捗状況を細かく記録すると身体機能の改善を客観視できるため、モチベーション高くリハビリを続けられるでしょう。
神経可塑性を最大限高める工夫!生活習慣改善が回復のポイント

神経可塑性を最大限高めるには、リハビリだけでなく生活習慣改善も重要です。脳細胞を活性化させる栄養の摂取やストレス軽減、良質な睡眠を意識すると、日々の運動効果がより高まる効果に期待ができます。
生活習慣を具体的にどう改善するのか?深堀していきましょう。
一汁三菜を意識した食事
脳を活性化するには、栄養バランスのよい食事が必要です。献立を難しく考えなくても、和食を中心とした「一汁三菜」を意識すれば、バランスよく栄養を摂取できます。栄養素の中でも、脳機能のサポートには以下のような食材摂取がおすすめです。
<神経可塑性を高める栄養>
- オメガ3脂肪酸を含む食材(青魚、ナッツ類、亜麻仁油、えごま油)
- ビタミンEを含む食材(ナッツ、アボカド、オリーブオイル)
上述した栄養は脳への血流を改善し、神経可塑性を高める効果に期待ができます。主菜や間食を工夫して脳に必要な栄養摂取を意識しましょう。
参考:朝日新聞「脳の活性化に役立つブレインフードとは?種類やレシピ、食べ方のポイントを解説」
適度な運動習慣でストレス軽減
ストレスは脳に悪影響を与え、期待したリハビリ効果が得られません。神経可塑性を高めるためには、適度な運動を行ってストレスを軽減させるのがおすすめです。
<ストレスを減らす運動>
- 息が軽く弾む程度のウォーキング
- 水泳
- ヨガやストレッチ
運動は、自分が好きでリラックスできる種目を選びましょう。無理に苦手な運動を選ぶと、ストレス増加の原因になるため、注意が必要です。
良質な睡眠で集中力の維持
神経可塑性を高めるには、良質な睡眠が取れるように環境を整えることが大切です。睡眠が脳の修復と再生を促し、神経ネットワークを改善します。良質な睡眠は、疲れやストレスを減らし、リハビリ効果を最大限高める効果に期待できるでしょう。
<睡眠のポイント>
- 日中しっかり体を動かす
- 自分にあった寝具を選ぶ
- 夕食をしっかり食べる
良質な睡眠のためには、運動や環境の見直し、食事が重要です。毎日のリハビリを頑張れるように睡眠環境の改善を目指しましょう。
まとめ|神経可塑性を高めることで脳梗塞後遺症が改善する
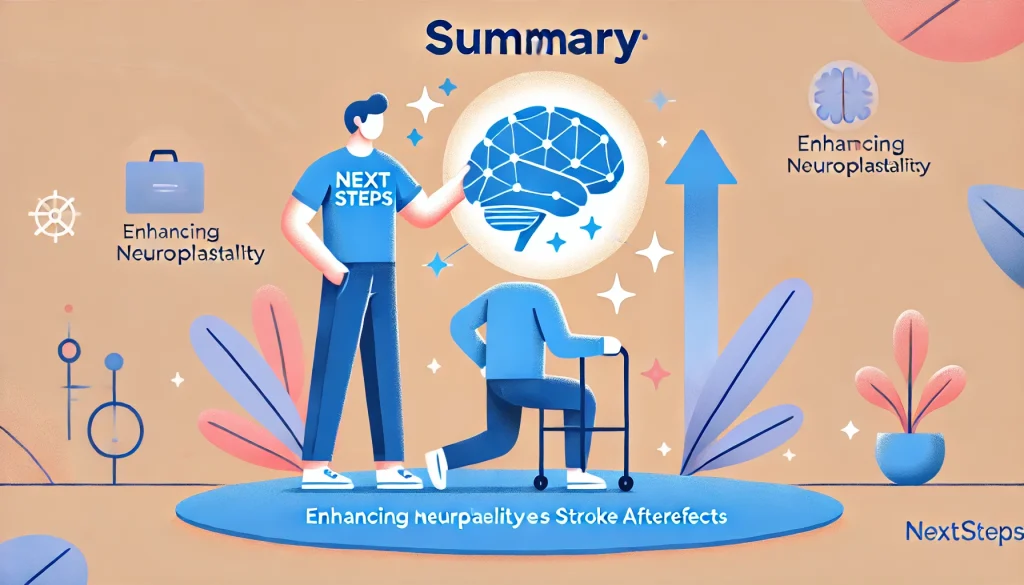
脳梗塞のあとに出る後遺症を少しでもよくするためには、「神経可塑性(しんけいかそせい)」という脳の力を高めることが大切です。
ダメージを受けた脳の細胞は、元どおりにはなりません。だからこそ、脳の別の部分が新しいつながり(神経ネットワーク)を作って、失った力をカバーすることが必要になります。
たとえば、マヒして動かなくなった手や足を動かせるようにするには、同じ動きをくり返し練習することが大切です。さらに、その人に合ったリハビリメニューや、気持ちのサポート(メンタルケア)も大事です。
ただ運動するだけでは十分な効果は出ないこともあるので、専門の療法士に今の体の状態を見てもらうと安心です。
そして、神経可塑性を高めるには、ふだんの生活もとても重要です。
栄養バランスの良い食事や、軽い運動、よく眠ることなど、毎日の生活を見直すことが、脳を元気にしてリハビリの効果を大きくします。
脳梗塞の後遺症を少しでも改善するには、「リハビリの方法」と「生活のしかた」の両方を大切にすることがポイントです。