
バランスの種類によるリハビリの検査・内容を紹介|日常生活をより快適に!
2025.06.23

「歩く時に少しふらつく」「お風呂から上がる時に転びそうになった」など、日常動作に不安を覚える方もいらっしゃるでしょう。バランス能力が低下すると、怪我の原因となるため、早めの対処が必要です。
バランスと一言で表現しても、実は身体のどんな機能によるバランスかによって違いがあります。この記事では、バランスの種類に注目して、リハビリの検査や内容をご紹介します。
日常生活を快適にするために、バランス能力の向上を目指しましょう。
目次
バランスとは何か?能力低下の原因とリハビリでできる体づくり

「バランスが悪い」「バランスが崩れる」などと聞きますが、そもそもバランスとはどんなものなのでしょうか。バランスは、大きく2種類に分られます。バランス能力を改善するリハビリをするために、低下する原因も知っておきましょう。
姿勢反応としてのバランス
姿勢反応としてのバランスは、転びそうになった時に働く反射的な動きを指します。座った状態で体重を右に傾けると、右に倒れないよう、体の左側を縮めて少し右に湾曲するような姿勢になるでしょう。
また、転びそうになったとき、とっさに手を出す動作もバランス反応です。
身体の重心からみるバランス
バランスをとる時は、自分の体がどれだけ地面に触れて、支えられているかが重要です。例えば、立っている時は両足の足裏とその間の範囲、座っている時はお尻・太もも・足の裏で支えてバランスをとっています。
片足立ちが不安定になるのは、体を支える面積が片方の足の裏だけになるので、その面積に自分の重心を入れる必要があるからです。反対に、両足を広げて立つと、体を支える面積が広くなるので安定しやすくなります。
体重を支えられる範囲から重心が出ると、バランスを崩してしまうため、体の動きや姿勢に合わせて体の重心を収める能力が必要なのです。
バランスが低下する原因
加齢や怪我・病気によって、バランス能力は低下します。神経系が衰えたり、障害されたりすると、姿勢反応が出にくくなります。加齢によって筋力が低下すると、「バランスをとろう」という指令が出ても、体重を支えきれなくなったり、動きが遅くなったりする可能性があるのです。
また、動作時は体を支える面積が動きによって変化します。体の機能低下により、重心が支えられる範囲から外れる場合に、ふらつきや転倒につながるのです。
バランス能力別|リハビリでは何をする?検査と内容を紹介
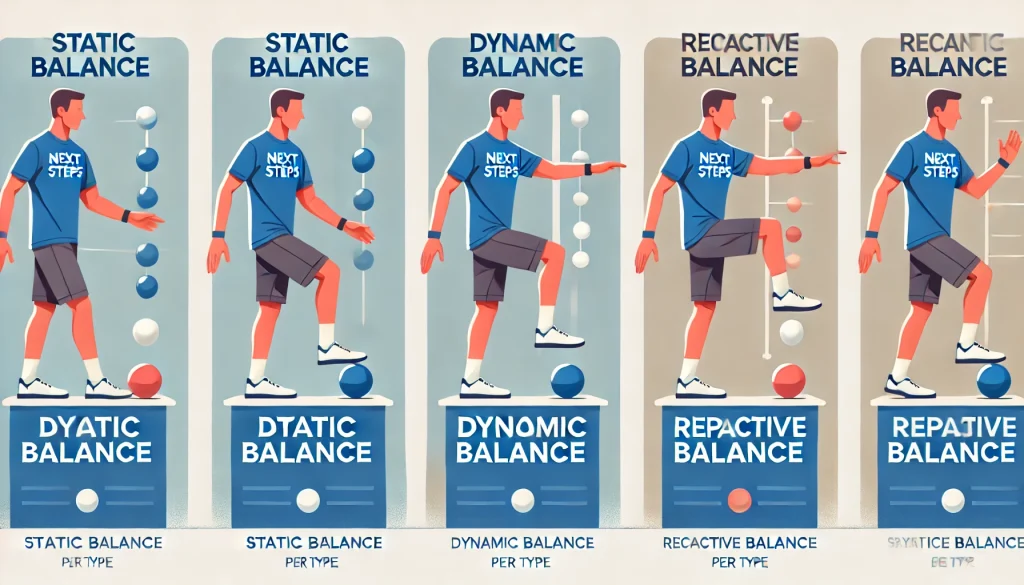
バランス能力が加齢や病気・怪我によって低下した場合、リハビリで改善できる可能性があります。バランス能力によって、リハビリ内容が変化し、ネットなどで調べた内容と違うかもしれません。見通しを持ってリハビリをするために、何をするのかを知っておきましょう。
姿勢反応をみる検査・内容
姿勢反応は、姿勢を保ったり動作時にバランスを崩したりした時の体の反応です。そのため、立ち上がりや方向転換時に体がどのような変化をするか評価・検査します。
姿勢反応を促すリハビリでは、椅子に座った状態で手や足を動かし、動作によって自然なバランス反応を出すトレーニングを行うでしょう。座った状態だけではなく、バランスボールに座ったり、揺れる板の上に立ったりするなど、不安定な姿勢をとってリハビリを行う可能性もあります。
身体の重心のバランスをみる検査・内容
何もしないで立った状態で、重心がどのように動くかを専用の機械を使って計測します。また、動作時にバランスを崩す原因が重心の移動かどうかを観察によって見極める場合もあるでしょう。
体重を支えられる面積から重心が出てしまっている原因が、筋力低下の場合は、コントロールするために体幹・下肢の筋力トレーニングをします。身体の重心を適切な位置に保てるよう、段階付けて動作を行うのもリハビリの1つです。
総合的な評価とリハビリ内容
歩行時のふらつきや動作の始めのバランスが崩れやすい場合、上記の2つのリハビリだけでなく、総合的な評価を実施する可能性があります。例えば、BergBalanceScaleやTimedUp&Goと呼ばれる評価ツールを使って、バランス能力がどの程度かをみるでしょう。
評価結果を元に、歩行・動作・方向転換・段差昇降など、実生活に即したリハビリを実施します。
今からでも遅くない!バランスのリハビリのためにできる3つのこと

加齢によるバランス能力低下や怪我・病気発症から時間が経っている場合、「もう遅いのでは」とリハビリに消極的な方もいらっしゃるでしょう。しかし、脳は再学習する力を持っているため、バランスのリハビリは今からでも遅くはありません。取り組めることを3つおさえておきましょう。
専門家のリハビリを受ける
バランス能力の向上のためには、リハビリ専門のスタッフによるトレーニングが欠かせません。ご自分で取り組む方法もありますが、まずは現在の状態を評価してもらいましょう。
バランス能力が低下していて、動作に不安定さがある場合、安全に配慮しながらご自分にあったリハビリをするのが大切です。また、専門スタッフがいると、モチベーションが低下した時にも継続できる可能性が高まります。
自宅でできるバランス訓練
バランス能力を改善して、動作の安定性を出すためには、週2回以上のトレーニングが必要です。専門スタッフによるリハビリを行っても、利用する制度によっては回数や時間が少ないかもしれません。
そのため、自宅でも安全に行えるバランス訓練をするのが大切です。椅子に座って足を上げたり体幹をひねったりして、身体のバランス反応を高めましょう。立った状態が安定してきた方は、壁に手を添えて片足立ちをするのもオススメです。
自宅で行う時は、必ずつかまれる場所を確保して行うと、転倒予防となります。
日常生活をトレーニングにする
掃除機をかけたり床掃除をしたりするのは、ウォーキングと同等の運動強度だと報告されています。そのため、日常生活でできる動作・作業に取り組むのも立派なトレーニングとなるのです。
少し面倒な家事や外出も、バランス能力や身体機能の維持・向上につながります。できる範囲で体を動かすようにするのが、豊かな生活につながるでしょう。
まとめ|日常生活に必要なバランス能力とリハビリ

年をとったり、病気の後遺症があったりすると、体のバランスをとる力が弱くなることがあります。この「バランス能力」が下がると、転びやすくなったり、歩くのが不安定になったりして、ふだんの生活がとても大変になります。
リハビリの現場では、こうした人たちのためにさまざまなバランスの検査や訓練が行われています。たとえば、片足で立ってみたり、歩くスピードをチェックしたりして、今の状態をしっかり調べます。そのうえで、一人ひとりの体の状態に合わせてリハビリのプログラムが作られていきます。
バランスが悪くなった原因や背景は、人によって違います。そのため、理学療法士などのアドバイスを受けながら訓練を行うことがとても大切です。自分だけでやると、無理をしてケガをしたり、逆に体を悪くしてしまうこともあるからです。
実は、日常生活のちょっとした動作にも、転びそうになるような危険がひそんでいます。たとえば、靴を履くときにふらついたり、少しの段差でバランスをくずしたりすることもあります。
だからこそ、安全に、そして効果的にリハビリを進めるためには、療法士と一緒にコツコツと訓練していくことが大切なのです。










