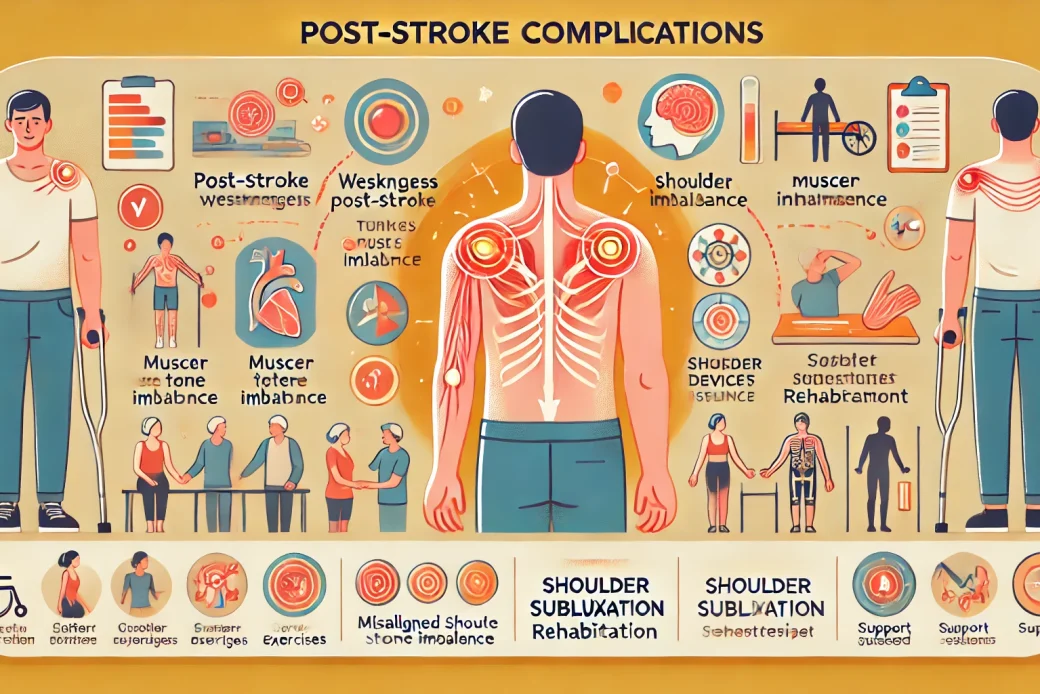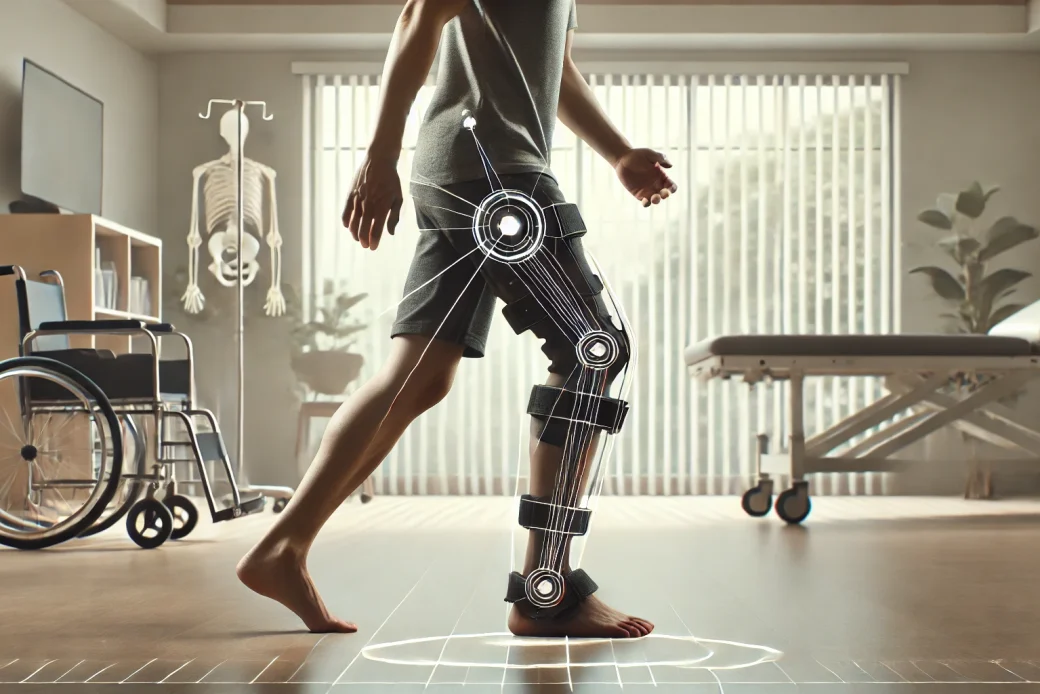くも膜下出血の後遺症なし?…再発の危険性や日常生活で取り組める3つの予防方法
2025.01.29

脳卒中の一つであるくも膜下出血は、予後が悪く命に関わることも少なくない疾患です。
一命を取り留めたとしても後遺症が残ると、これまでどおり日常生活を送ることが困難になるケースもあります。また、くも膜下出血による後遺症なしの場合でも、再発リスクは非常に高いことが特徴です。
くも膜下出血の再発率と危険性を理解し、3つの重要な予防対策を実践することで、再発リスクを大幅に軽減できます。
まずはくも膜下出血とはどのような病気なのかをみていきましょう。
目次
くも膜下出血は後遺症なしの場合でも再発する?再発リスクと治療法について

一般的に予後が悪いといわれるくも膜下出血。後遺症なしのケースや再発のリスクはどれくらいでしょうか?くも膜下出血の病態と治療法、予後をみていきましょう。
くも膜下出血の症状と脳出血との違い
脳は硬膜・くも膜・軟膜という3層の膜で覆われています。くも膜下出血は、くも膜と軟膜の間のくも膜下腔に存在する血管が破れて起こる出血のことです。それに対し脳出血は、脳内の血管が破れて起こる出血を指します。脳の中でも出血する箇所によって異なるというわけです。
くも膜下出血の75〜80%が脳動脈瘤という、脳の血管の一部がこぶ状に膨らんだものの破裂によって発症します。
それまでに経験したことのない激しい頭痛が主症状で、吐き気・嘔吐にも見舞われ、そのまま意識消失することも少なくありません。
くも膜下出血の再発リスク
くも膜下出血が起こると、出血した部分にかさぶたが作られ、一時的に止血されます。しかし、その止血は十分でなく非常にあやうい状態であり、再発のリスクは高まるのです。
再出血は発症から24時間以内が一番起こりやすいとされており、1ヵ月以内に約50%が再出血するといわれています。後遺症がなく、発症前と変わりのない生活をしていても油断はできません。
再出血の場合の症状は重く、死亡率は40〜50%と非常に高くなります。また後遺症が残る可能性も高くなるため、再発の予防は予後に大きく関わることがわかります。
急性期にほどこされる治療について
くも膜下出血は、再発により死亡や後遺症が残る可能性が高まるため、再発予防がそのまま治療となります。
急性期の治療には、開頭手術によるクリッピング術や脳血管内治療によるコイル塞栓術が行われます。
初回の出血後、できるだけ早期に手術を行って再発を予防し、重症化を食い止めることが求められます。また、手術はくも膜下出血の後遺症なしを目指すものでなく、再発防止によって救命することが主目的であることを理解しておきましょう。
くも膜下出血の後遺症なしは何%?社会復帰が難しいとされる予後と後遺症

くも膜下出血による後遺症なしの場合でも再発の可能性はあります。では後遺症なしの頻度はどれくらいでしょうか?一般的に起こりやすい後遺症とともに確認しましょう。
くも膜下出血の後遺症なしの確率
くも膜下出血が起こった場合、後遺症なしや軽度の割合が1/3、治療を受けることなく死亡する割合が1/3、後遺症を残す割合が1/3ほどです。
仮にくも膜下出血後の後遺症なしでも、再発のリスクは常にあることを覚えておく必要があります。くも膜下出血の主な原因である未破裂の脳動脈瘤が潜んでいるかもしれません。後遺症がないから安心できるというわけではないのです。
どのような後遺症が想定されるのか?
くも膜下出血の後遺症は、出血部位や出血量などにより異なります。一般的に発生しやすい後遺症は以下のとおりです。
- 運動麻痺
自分の意思で手足を動かせない
- 高次脳機能障害
注意力、記憶力、言語、感情制御などの認知機能に障害が生じ、日常生活に支障をきたす状態
- 嚥下障害
食べ物や飲み物のがうまく飲み込めない
- 感覚障害
手足のしびれや視覚異常など
あらわれる症状はさまざまで、複数の症状がみられることも少なくありません。後遺症がある場合、身体や認知機能の症状に応じたリハビリを実施する必要があります。
参考:秋田県立循環器・脳脊髄センター「くも膜下出血と脳動脈瘤について」
退院後のリハビリについて
くも膜下出血の発症直後から退院まで行われるリハビリは、主に低下している機能の回復を目的に行われます。一方、退院後のリハビリは、機能の維持やさらなる回復を目的に、日常生活動作の獲得を目指します。
後遺症が重度の場合、回復には辛抱強い継続的な取り組みが必要であり、リハビリを継続できる環境の整備が極めて重要です。
〈再発予防〉くも膜下出血は後遺症なしでも再発を避けるための生活を

すでにお伝えしているように、くも膜下出血の後遺症なしの場合でも再発のリスクは潜んでいます。再発を避けるために必要な生活習慣を確認しましょう。
【3つのポイント】くも膜下出血の予後が順調でも
くも膜下出血の後遺症なしでも、再発予防を常に心がける必要があります。再発予防の3つのポイントは以下のとおりです。
- 生活習慣を整える
再発予防で重要なのが高血圧の予防です。禁煙や禁酒に努め、塩分を控えたバランスのよい食生活を心がけましょう。特に喫煙は高血圧の危険因子のため、禁煙することは血圧管理において重要です。また、できるだけストレスのかからない生活を心がけましょう。
- 定期的な運動やリハビリの実施
適度な運動習慣をつけ、高血圧を予防しましょう。ウォーキングやジョギングなどの有酸素運動がおすすめです。またリハビリも重要ですが、無理なく継続できる環境づくりが必要です。
リハビリには訪問リハビリやオンラインリハビリという選択肢もあります。通所の必要がなく自宅という慣れた環境で行えるため、継続しやすいというメリットがあります。また、専門家により個々に応じたリハビリや必要なアドバイスを受けられることもメリットです。
- 定期受診をする
くも膜下出血の再発予防では、脳動脈瘤の早期発見が最も大切になります。脳動脈瘤の早期発見には、定期的な受診や検査が必要です。
くも膜下出血は再発の可能性が高く、再発時の死亡・重症化のリスクも非常に高い疾患です。定期受診により、継続的に管理をしていきましょう。
リハビリ時に家族が心がけること
くも膜下出血後の再発予防を本人だけで行うのは困難であり、家族や回りの協力が不可欠です。
よりよい生活習慣を身につけられるよう食事管理や禁煙のサポートなどをする他、段差をなくしたり手すりをつけるなどの転倒防止対策も必要です。
リハビリの継続にあたり、精神的なサポートも欠かせません。リハビリは長期に渡ることが多く、自信喪失や意欲の低下が起こりやすくなります。不安や孤独感を軽減できる関わりを続けましょう。
また、リハビリ計画を専門家と共有し、適切で効果的なリハビリが行えるよう支援することも大切です。
くも膜下出血の予後と再発予防に関するFAQ
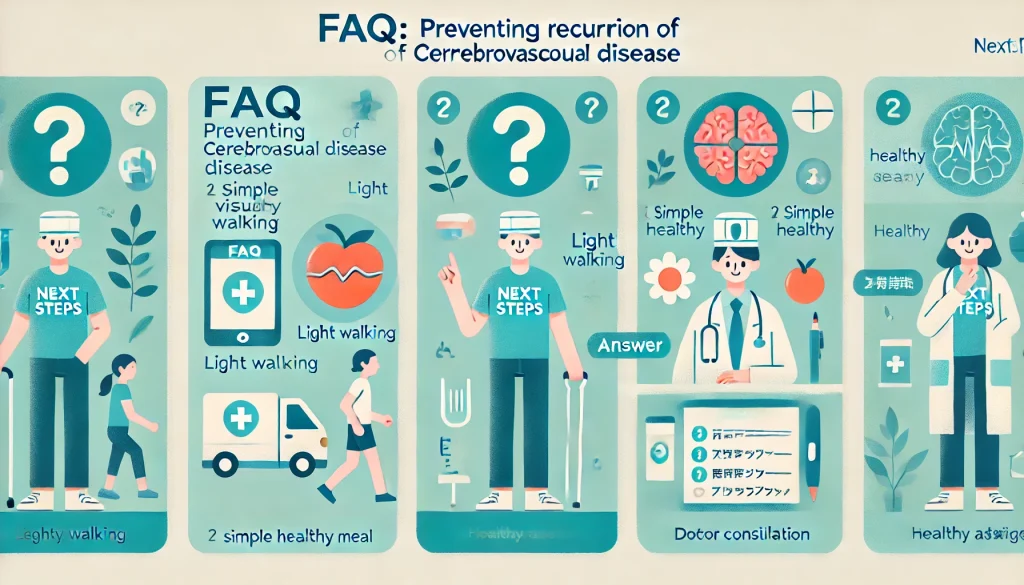
Q1. くも膜下出血の「再発リスク」はどれくらい高いですか?
A. くも膜下出血は、一度発症すると再発リスクが非常に高いことが特徴です。特に初回の出血後、1ヵ月以内に約50%が再出血するといわれています。再出血は症状が重篤化し、死亡率も40〜50%と非常に高くなるため、後遺症の有無にかかわらず、徹底した再発予防が欠かせません。
Q2. くも膜下出血で「後遺症なし」または軽度で済む確率はどれくらいですか?
A. 一般的に、くも膜下出血を発症した場合、約1/3が後遺症なしまたは軽度の障害で済み、約1/3が重い後遺症を残し、残りの約1/3は治療を受けることなく死亡するとされています。後遺症なしの場合でも、再発リスクは常にあるため、安心はできません。
Q3. 日常生活で取り組むべき、再発予防の3つの重要なポイントは何ですか?
A. 再発を避けるための3つのポイントは、「生活習慣を整える」「定期的な運動やリハビリの実施」「定期受診」です。特に高血圧の予防や禁煙は再発予防に極めて重要です。また、再発の鍵となる脳動脈瘤の早期発見には、定期的な受診が欠かせません。
Q4. くも膜下出血後に想定される、主な後遺症にはどのようなものがありますか?
A. 出血の部位や量により異なりますが、一般的には運動麻痺(手足の動きの障害)、高次脳機能障害(記憶力・注意力・感情制御の障害)、嚥下障害(飲み込みの困難)、感覚障害(しびれ、視覚異常)などがよく見られます。複数の症状が複合的に残ることも少なくありません。
Q5. 退院後のリハビリ継続において、家族はどのようにサポートすべきですか?
A. ご家族の協力は不可欠です。本人の食事管理や禁煙のサポートなどの生活習慣の見直しを支えるほか、転倒を防ぐための住環境整備(段差解消など)も重要です。また、リハビリは長期にわたることが多いため、精神的なサポートを継続し、本人の意欲を維持できるよう支援することが大切です。
まとめ|くも膜下出血は後遺症なしでも再発予防が必要

くも膜下出血とは、脳を包む膜のうち「くも膜」という場所の下で起こる出血のことです。脳の血管が何らかの原因で破けて血が漏れ出すと、脳の周りにある脳脊髄液(のうせきずいえき)という液体の中に血液が混ざってしまい、強い頭痛や意識障害を引き起こすことがあります。このようなくも膜下出血の後遺症は、出血した位置や出血の量などによって、症状の重さが大きく変わります。
後遺症なし、または軽度の後遺症であれば、普段の生活に大きな支障が出ることは少なくなります。たとえば、少し疲れやすいと感じる程度であれば、日常生活をほぼいつも通りに続けられる場合もあります。一方で、重い後遺症が残った場合は、手足のマヒや言葉がうまく話せないなど、生活のあらゆる場面でサポートが必要になることがあります。
しかし、後遺症がない、または軽い場合であっても、再発のリスクがあることには変わりありません。くも膜下出血は一度起こると、将来もう一度同じような出血が起きる可能性が高まるといわれています。そのため、医師の指示を守りながら、薬の服用や生活習慣の見直しなどの適切な再発予防対策を続けることがとても重要です。これは、今後の人生にわたって続けていく必要があります。
さらに、予防やリハビリを本人だけで行うのは、体力面でも精神面でも大きな負担がかかります。そこで、家族や友人と協力しながら、無理をしすぎないことが大切です。また、理学療法士や作業療法士などのリハビリの専門家のサポートを受けることで、日常生活の動作を安全に行う方法や、体力を維持・向上させるトレーニングなどを学ぶことができます。こうした周囲の協力を得ながら、再発を予防し、できるかぎり質の高い生活を送れるようにしていきましょう。