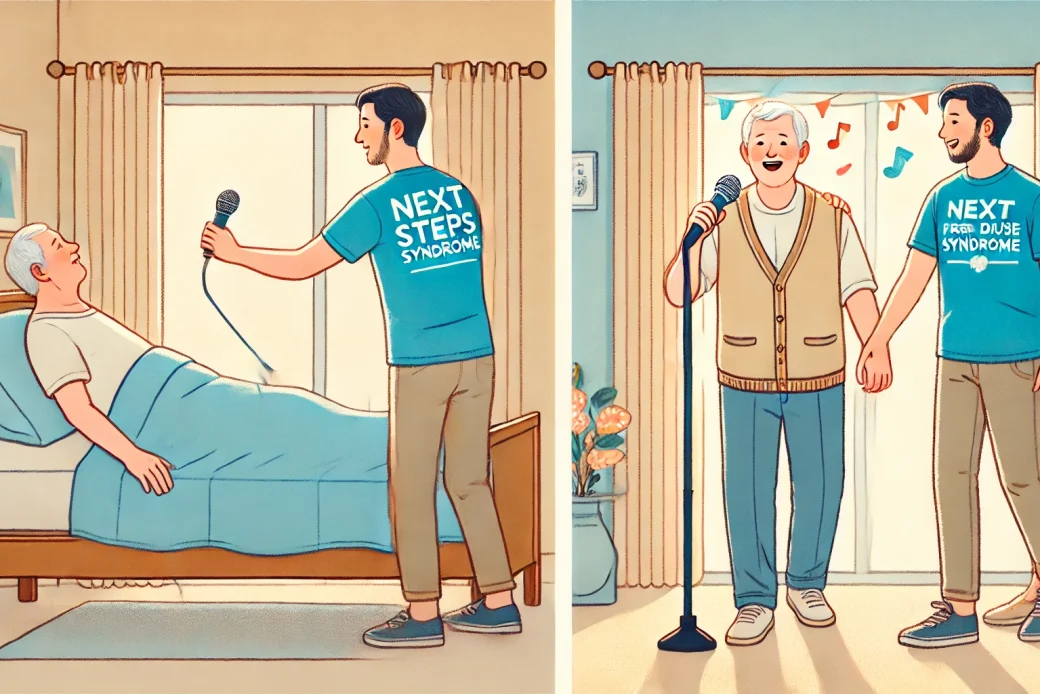脳梗塞後の廃用症候群|杖なしで仕事復帰した高齢女性の話
2025.10.16

「仕事に戻りたいけど、歩くのに杖が必要で仕事にならない…」
脳梗塞で入院した後、60代女性の彼女はこんな悩みを抱えていました。
入院前と比べて運動時に疲れやすくなった。物を持って移動する筋力がないから買い物も満足にできない。退職後に生活していくための貯金を増やしたいけれど、仕事するときにも杖が必要で満足に働くこともできない。
でも、まだ仕事を続けたいという強い思いがあった彼女は、覚悟を決めてリハビリに取り組みました。その結果、「これからの人生を楽しむために必要なものが何か」を考えるきっかけになったそうです。
この事例では、廃用症候群とは何か、なぜ長期入院が危険なのか、そして実際にリハビリで改善した事例を紹介します。
目次
廃用症候群って何?なぜ脳梗塞で起こるのか

廃用症候群。聞き慣れない言葉かもしれませんが、別名「生活不活発病」とも呼ばれる疾患です。
廃用症候群とは、病気やケガによる活動性の低下、または脳梗塞などの手術後の長期入院で過度の安静状態が続き、筋力が減少して起こる運動能力の低下のことです。
つまり、動かないことで身体の機能が落ちてしまう状態ですね。
高齢者は特に注意が必要
高齢になると、関節などに痛みが生じることから動くことが億劫になったり、自力で動けるうちから車いすなどを使用したりすると、さらに身体を動かす機会が減少して廃用症候群が進行しやすくなります。
そして高齢者は身体能力の衰えが早く、脳梗塞による入院などで1週間寝たきりの状態が続くと約10%〜15%の筋力が失われるとされています。
たった1週間で10〜15%も筋力が落ちるんです。これは深刻な問題です。
高齢者が長期入院したり、寝たきり状態や住環境に不便があったりする場合、外出するのが億劫になってしまうので、危険な廃用症候群が発症してしまう可能性が高くなります。
長期入院は危険|高齢者が廃用症候群になったらどうする?
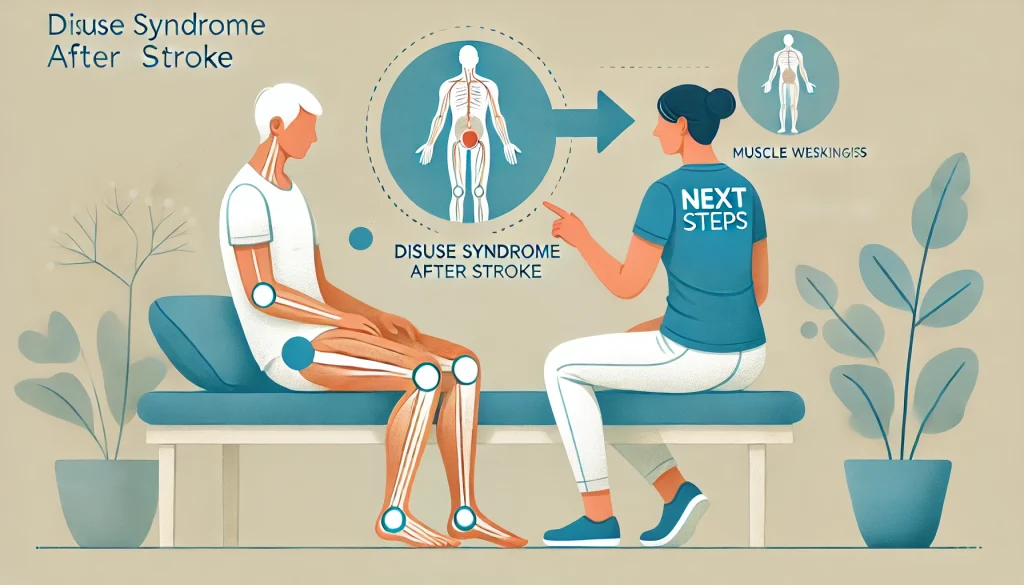
廃用症候群の治療には、萎縮した筋肉を動かす運動が必要です。
初期のリハビリでは、散歩をする程度の運動や、エレベーターを使わずに階段を上るなど日常生活に運動を取り入れてみるのがおすすめです。
ラジオ体操に毎日取り組んだり、ベッドに横になっているときでも「寝たまま足首を動かす」など気がついたときに体を動かすと効果的でしょう。
身の回りのことは自分でやる
排泄や食事など基本的な身の回りの簡単な作業は、自分でできるようにサポートしてもらいながら行うと身体機能の衰えが穏やかになります。
「危ないから」と家族が何でも手伝ってしまうと、本人の能力はどんどん落ちていきます。できることは自分でやることが大切です。
自宅でできる簡単なリハビリ
筋肉を維持するためにはリハビリが最も有効です。
具体的には、こんな運動があります。
- 仰向けになり、片足ずつ上げる運動
ベッドや布団の上で仰向けになって、片方の足をゆっくり上げます。膝は曲げても伸ばしてもOK。左右交互に行いましょう。
- 座った状態でつま先を上げる
椅子に座って、つま先を上げたり下ろしたりする運動です。ふくらはぎの筋肉を鍛えられます。
無理のない範囲で行うことが大切です。
「歩けないなら歩くしかない」廃用症候群を克服した60代女性の声

脳梗塞による入院で廃用症候群を患っていた彼女は、こんな悩みを抱えていました。
「入院前と比べて運動時に疲れやすくなった」 「物を持って移動する筋力がないので買い物も満足にできない」
退職後に生活していくための貯金を増やしたいけれど、仕事するときにも杖が必要なので満足に働くこともできません。
手段を選ばず回復したい
そんなとき、彼女は「手段を選ばず回復したい」という強い思いから、まずは生活していくための筋力をつけるためにも自費訪問リハビリの施設に問い合わせしてみました。
「歩けないなら歩くしかない」
覚悟を決めていた彼女のリハビリは順調に進みました。
長距離の移動には車椅子を使用しますが、仕事中は「つかまりながらやる方法」を教えてもらいました。完全に元通りというわけではないけれど、仕事を続けられる状態まで回復したんです。
身体的改善だけでなく心身のフォローもしてもらい、「感謝の気持ちでいっぱい」とのことです。
自費訪問リハビリは「なるべく早く回復したい」希望を叶える

実は、医療保険を使ったリハビリには期間制限があります。
現在の医療保険の制度では、脳血管障害では150日、高次脳機能障害を伴う重篤な脳血管障害でも180日までと、リハビリの期間が決められています。
長くても180日程度しかリハビリを受けられないため、生活していくための動きが難しくても期間が過ぎればリハビリ終了です。
これが医療保険のリハビリの限界です。
自費訪問リハビリには期間制限がない
一方、自費訪問リハビリに、リハビリ期間の制限はありません。
本人が望む限り、何ヶ月でも、何年でも続けられます。
この女性のように「なるべく早く回復したい」「症状が改善されるなら手段を選ばない」という方には、自費訪問リハビリが向いている廃用症候群の改善方法と言えるでしょう。
医療保険のリハビリで期間が終了した後も、自費でリハビリを続けて改善した例は多くあります。
廃用症候群のサイン|こんな症状があったら要注意

以下のような症状があったら、廃用症候群が始まっているかもしれません。
- 少し歩いただけで息切れする
- ちょっとした段差で転びそうになった
- 以前より疲れやすくなった
- 立ち上がるのに時間がかかるようになった
- 重い物が持てなくなった
こんな経験があれば、筋肉の量はほぼ確実に減っているでしょう。
早めに対策を始めることが大切です。
日常生活に運動を取り入れよう
廃用症候群を予防したり、改善したりするには、日常生活に運動を取り入れることが大切です。
特別なトレーニングは必要ありません。
- 散歩を日課にする
- エレベーターではなく階段を使う
- ラジオ体操を毎日やる
- 寝たままでも足首を動かす
- 気がついたときに体を動かす
こうした小さな積み重ねが、筋力を維持し、廃用症候群を予防します。
いつまでも自分の足で元気に動き回ったり、まだまだ現役で仕事をしたりしたい方は、日常生活に運動を取り入れて若々しい体を保ちましょう。
よくある質問
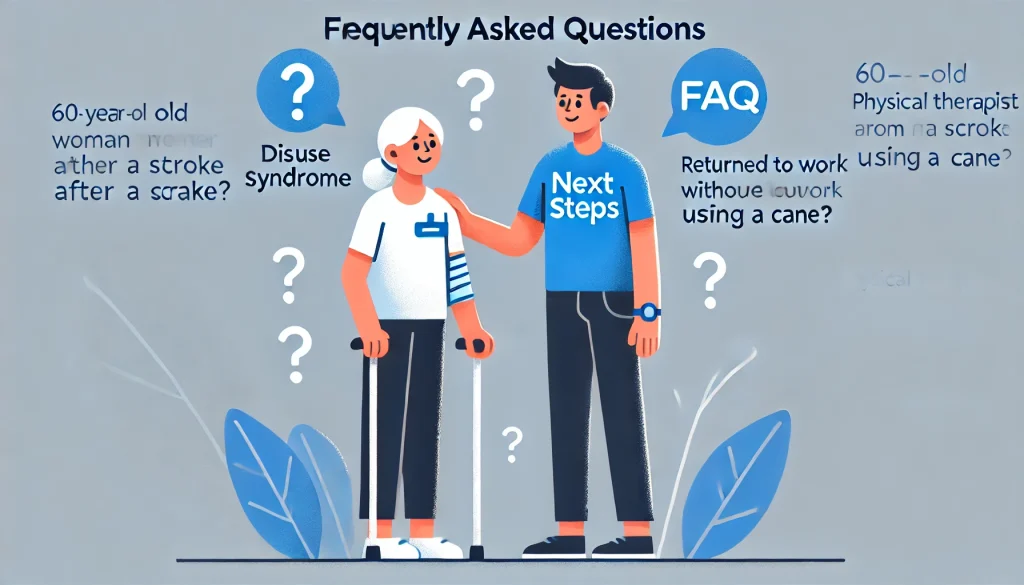
Q:廃用症候群は治りますか?
A:はい、適切なリハビリを行えば改善します。萎縮した筋肉を動かす運動が必要です。ただし、放置すると進行してしまうので、早めの対応が大切です。
Q:入院してどれくらいで廃用症候群になりますか?
A:高齢者の場合、1週間の寝たきりで約10〜15%の筋力が失われます。2週間、3週間と長くなるほど、筋力低下は進みます。
Q:医療保険のリハビリが終わった後はどうすればいい?
A:自費訪問リハビリという選択肢があります。医療保険には期間制限がありますが、自費リハビリには制限がないので、本人が望む限り続けられます。
Q:自宅でできるリハビリはありますか?
A:はい、仰向けになって片足ずつ上げる運動、座った状態でつま先を上げる運動など、簡単なものがあります。無理のない範囲で続けることが大切です。
Q:家族が何でも手伝ってしまうのは良くない?
A:本人ができることまで家族が手伝ってしまうと、能力がどんどん落ちていきます。排泄や食事など、基本的な身の回りのことは、自分でできるようにサポートしながら見守ることが大切です。
最後に
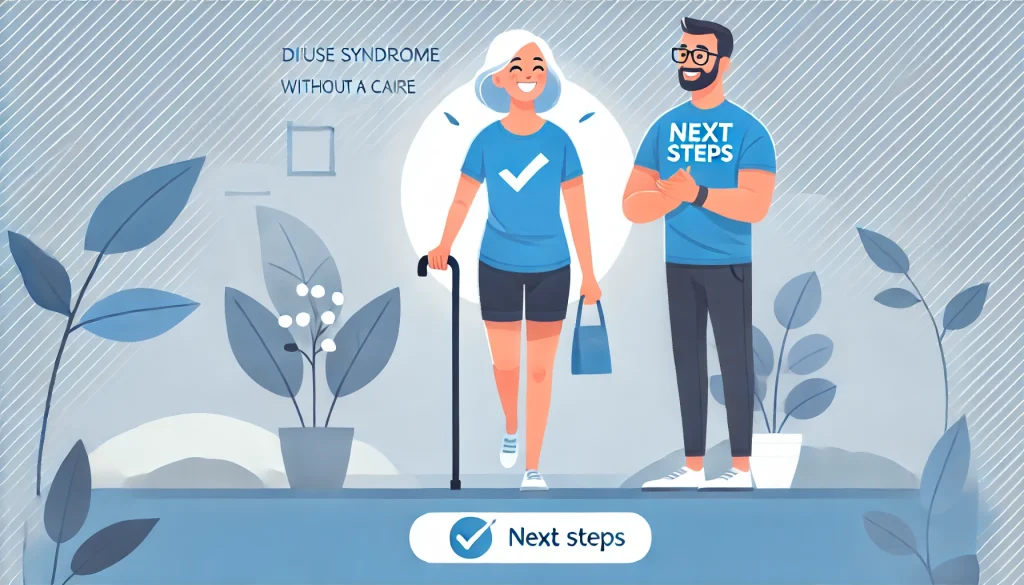
脳梗塞で入院して廃用症候群になった彼女は、「歩けないなら歩くしかない」という覚悟でリハビリに取り組みました。
長距離の移動には車椅子を使うものの、仕事中は「つかまりながらやる方法」で働けるようになり、仕事を続けることができています。
完全に元通りとはいかなくても、工夫次第で生活の質を保つことはできるんです。
廃用症候群は、病気やケガによる入院で長期間寝たきり状態になると発症しやすくなる疾患です。でも、適切なリハビリと日常生活での運動で改善できます。
「少し歩いただけで息切れする」「ちょっとした段差で転びそうになった」。こんな経験があれば、筋肉の量は確実に減っています。
まだまだ現役で仕事をしたい、自分の足で元気に動き回りたい。そう思っているなら、今日から日常生活に運動を取り入れてみませんか。
散歩、階段の利用、ラジオ体操。小さなことから始めて、若々しい体を保ちましょう。