
寝たきり予防に重要なリハビリについて|具体的な方法と日常生活の注意点
2025.05.19
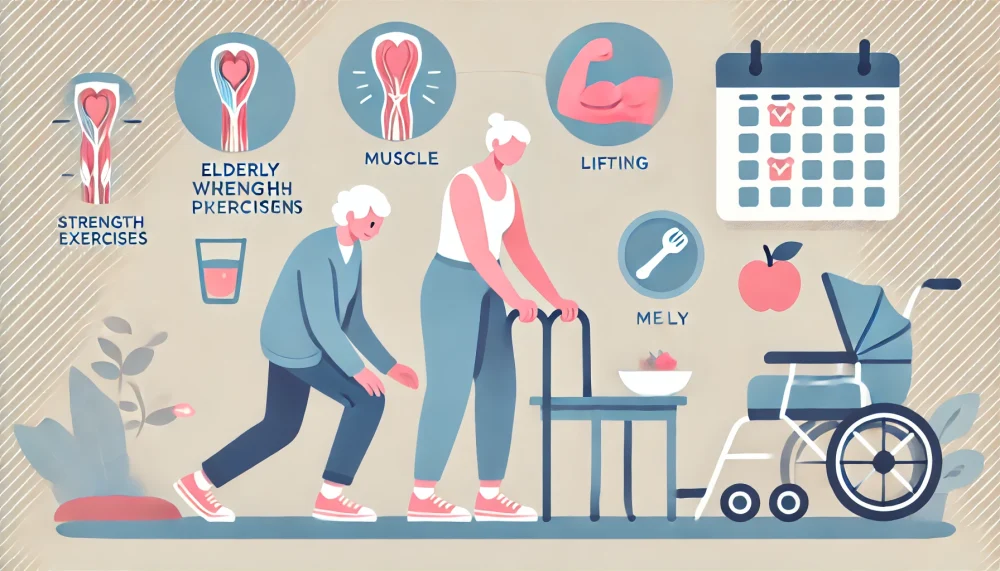
病気や怪我が原因で安静期間が長く続くと「寝たきりにならないか?」と心配になる人も少なくないと思います。1998年時点で、在宅で寝たきり生活を強いられている人が35万6千人いると報告されており、身近な問題となっています。寝たきりにならないためには、適切な予防やリハビリが重要です。
今回は、寝たきりを防ぐための具体的なリハビリ方法や日常生活の注意点について解説します。
目次
寝たきりは予防とリハビリが重要!高齢者が注意すべき筋力低下

寝たきりの状態から回復するのは難しく、予防やリハビリが重要です。特に高齢者は安静期間が長くなるほど寝たきりになる危険が高くなります。高齢者には注意すべき筋力低下や状態悪化にはいくつか種類があるので解説します。
全身の機能が低下する廃用症候群
高齢者は廃用症候群をきっかけに寝たきりになることがあります。廃用症候群とは、怪我や病気による長期間の安静、寝たきりによって全身の機能が低下する状態です。例えば、1週間寝たきりの状態では10〜15%の筋力低下が起こると言われています。高齢者は2週間で2割の筋肉が委縮するという報告もあり、筋力は思ったより早くやせ細ると思ってください。
廃用症候群は筋力低下に限らず、立ちくらみなど循環器の問題や褥瘡(床ずれ)などの合併症も引き起こします。廃用症候群から寝たきりに繋がらないように早期から予防する事が重要です。
筋肉量の減少を示すサルコペニア
寝たきりの状態はサルコペニアを悪化させるので注意が必要です。サルコペニアとは、「加齢に伴う筋肉量の減少や身体機能が低下した状態」の事を指します。65歳以上の高齢者のうち15%がサルコペニアに該当すると言われており、身近な問題となっています。
サルコペニアの状態では、歩行困難から転倒につながり、将来的に介護が必要な状態になってしまいます。「手足が細くなった」、「椅子から立ち上がりにくい」と言った自覚症状がある人はサルコペニアの可能性があります。
サルコペニアは正しい食事や運動習慣によって改善が期待できるので、自身の生活を見直してください。
精神、認知面に影響及ぼすフレイル
フレイルの状態が悪化する事も、寝たきりの原因になるため、注意が必要になります。フレイルとは「加齢と共に心身の活力が低下した状態」の事を指し、筋力だけでなく、精神的な側面に影響を及ぼしているのが特徴です。
フレイルの判定に用いられる基準があり、3つ以上当てはまるとフレイルと断定されます。
<フレイルの基準>
- 体重減少(年間4.5kgまたは5%異常の体重減少)
- 疲れやすい(何をするのも面倒だと週に3~4日以上感じる)
- 歩行速度の低下
- 握力の低下
- 身体活動量の低下
フレイルの状態では、感染症や怪我が重症化しやすいため、寝たきりの原因になりやすいと言われています。フレイルは要介護手前の状態です。廃用症候群やサルコペニアと同様に早期予防が重要になります。
寝たきり予防に効果的なリハビリは?具体的な方法とポイント

寝たきりにならないためには、早期からの予防が必要です。安静期間が長くなると、関節可動域の低下や筋力低下により、動くことが困難となります。動きやすい身体を保つためには、リハビリが重要です。具体的な方法とポイントを解説します。
マッサージで心身をリラックスさせる
寝たきりを予防するために、硬くなっている筋肉のマッサージを行いましょう。マッサージによって、血液やリンパの流れが改善されるので、関節周りが硬くなるのを防ぐ事ができます。他にも、リラックス効果によって精神面にもポジティブな影響を与えることも特徴です。
ストレッチや筋力トレーニングの前にマッサージを行うことで、リハビリ効果が高まります。マッサージは、対象者の全身状態も把握できるためリハビリの序盤に行う事をおすすめします。
ストレッチで関節可動域を広げる
安静期間が続くと、全身の関節周りが硬くなり、可動域が狭くなってしまいます。関節の可動域が狭くなるとさまざまな悪影響を及ぼします。
<関節可動域低下による影響>
- 寝返りや起き上がりなどの動作が行いづらい(活動性が低下する)
- 関節を動かしたときに痛みが出る
- 筋力トレーニングの効果が半減する
高齢者は1〜2週間安静にしているだけで、関節周りが顕著に硬くなります。関節可動域はストレッチによる予防が効果的です。「気持ち良い」と感じる程度の強度でゆっくりと関節を広げるようにストレッチしましょう。動作に直結するため、体幹や下肢の関節中心に行うのがおすすめです。
簡単なトレーニングで筋力強化
筋力低下は寝たきりの原因になります。寝たきり予防のためにも、簡単なトレーニングを行い、筋力を強化するように心がけましょう。ベッドの上でもできる運動があるので、積極的に運動してください。
<ベッド上でもできるトレーニング>
- SLRトレーニング(片足をゆっくり上げたり、下げたりする)
- ブリッジ(お尻を上げ下げする)
- 腹筋運動(おへそを覗き込むように、頭を持ち上げる)
「少し疲れた」と感じるぐらいの回数で行うと効率よく筋力が強化されます。ストレッチやマッサージで可動域が広がった状態で行うと効果的です。筋肉はトレーニングによる刺激がないとすぐにやせ細ってしまいます。リハビリで筋力低下を予防する意識が重要です。
【寝たきり予防】リハビリ以外でも気を付けたい3つのポイント
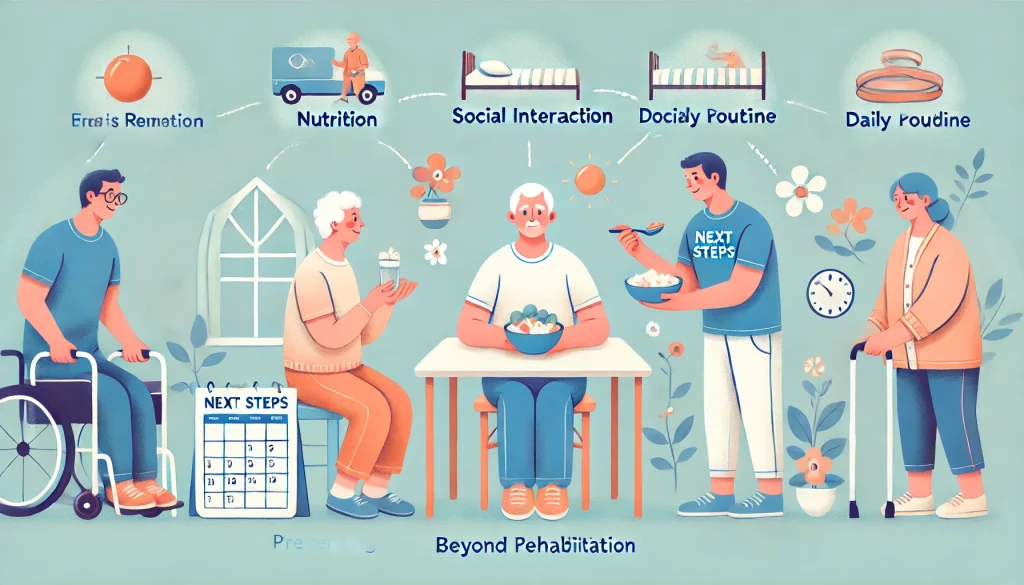
寝たきり予防にはリハビリによるストレッチや筋力トレーニングが重要になりますが、リハビリ以外でも気を付けるべきポイントがあります。リハビリの効果を高めるために、栄養摂取や認知症予防が重要です。具体的な内容を解説します。
適切な栄養摂取
寝たきり予防のために、適切な栄養摂取が重要です。高齢者になると、栄養の偏りによって筋力低下が起こる事も問題視されています。バランスよく栄養を取る事が大事ですが、特にタンパク質の摂取を意識しましょう。
<タンパク質について>
- 肉、魚、卵、大豆製品、乳製品に多く含まれる
- 1日3回タンパク質が含まれる主菜を食べる(特に朝が重要)
- 認知症予防には魚がおすすめ(EPA、DHAの働き)
タンパク質は筋肉の元になる栄養素です。朝食でタンパク質多めの食事を取ることで、筋肉量がアップするという研究報告もあるので、朝食の内容を見直してみましょう。
高齢になると認知症も不安になると思います。青魚に含まれるEPAやDHAは認知症予防にも効果が期待できるため、積極的な摂取をおすすめします。
他者との交流で認知症予防
認知症が進行すると、寝たきりに繋がる恐れがあるため、注意が必要です。怪我や病気で安静期間が長いと認知機能が低下します。他者との交流が少なくなると、脳への刺激が減るため、認知症が進行します。
家族との会話に加えて、他者との交流が重要です。引きこもりがちにならないよう、デイサービスなどを利用して積極的に他者との交流を行いましょう。
「人の多いところは苦手」という人は、計算や塗り絵など、脳に刺激が加わるアクティビティを行って認知症を防ぐようにしてください。
リハビリ以外でも自分で運動する
寝たきりを予防するためにはリハビリ以外でも運動する意識が重要です。「リハビリの時間だけ動かせばいい」という意識では、運動量が足りないので、思ったような効果を得ることはできません。
「自分でリハビリする方法がわからない」という人は、動かせる部分を動かしたり、痛みのない部分を動かすだけでも効果的です。
他にも、寝ている時間を減らすだけでも効果があります。ベッドを起こす時間を増やしたり、車椅子で過ごす時間を増やすだけでも、循環器の機能低下を防ぐ事ができるでしょう。リハビリ以外の時間も体を動かして、寝たきりを予防するようにしてください。
まとめ|寝たきりを予防しよう!リハビリが鍵!

寝たきりを防ぐためには、リハビリがとても大切です。 特に高齢者は、体を動かさなくなると筋肉や体力が急激に落ちてしまい、寝たきりになる危険があります。こうした状態を「廃用症候群(はいようしょうこうぐん)」や「サルコペニア(筋肉の減少)」、また「フレイル(体力の衰え)」といいます。
病気やケガで動けないときも、できるだけ早いうちからリハビリを始めることが大切です。
リハビリでは、マッサージやストレッチ、筋力トレーニングを行います。特に、体の中心部分(体幹)やお尻の周りの筋肉を鍛えるトレーニングがおすすめです。 これらは自宅でも簡単にできるので、リハビリの時間以外でも積極的に取り入れましょう。
また、リハビリ以外でも大切なポイントがあります。それは、栄養をしっかり摂ることと、認知症を予防することです。 筋肉のもとになるタンパク質(肉、魚、卵、大豆製品など)を意識して食べることで、筋力の低下を防ぐことができます。
さらに、認知症を防ぐには、人と積極的に交流したり、趣味やゲームなどを楽しんで脳に刺激を与えることが大切です。
一度寝たきりになると、元の状態に戻るのは難しいため、寝たきりにならないように早めの予防が重要です。 病気やケガをする前から健康的な生活を心がけ、自立した毎日を送りましょう。










